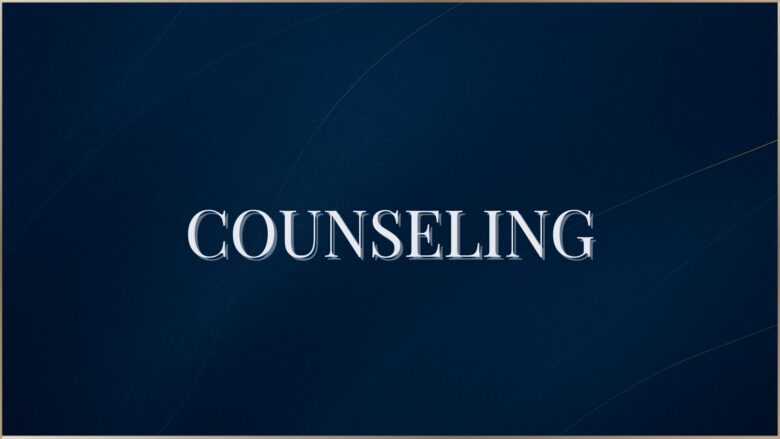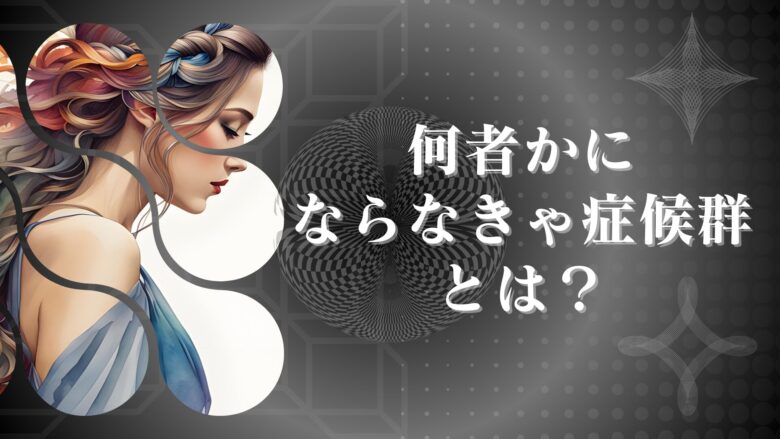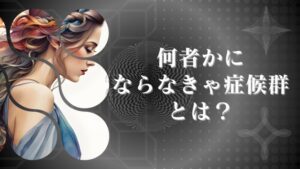おにぎり
おにぎり何者かにならなきゃ症候群って、なんなん?



何者かになりたいという強迫観念って、感じやね。
ネットに「何者かにならなきゃ症候群」という言葉があります。何となく字義通りに解釈すると、「病的に何者になりたいという承認欲求をこじらせた状態」のように見えてしまいますが、定義はよくわからない言葉ですね。なんせ、症候群ってついてしまっているのが、混乱の元凶です。
そんな感じですから、「何者かにならなきゃ症候群」とはなんなのかについて、気になりますよね。結論から言うと、「何者かにならなきゃ症候群」とは「自分はまだ何者でもない」と感じて焦っている状態のことであり、正式な疾患名ではありません。「何者かにならなきゃ症候群」に陥る原因としては、以下の通りです。
何者かにならなきゃ症候群に陥る原因
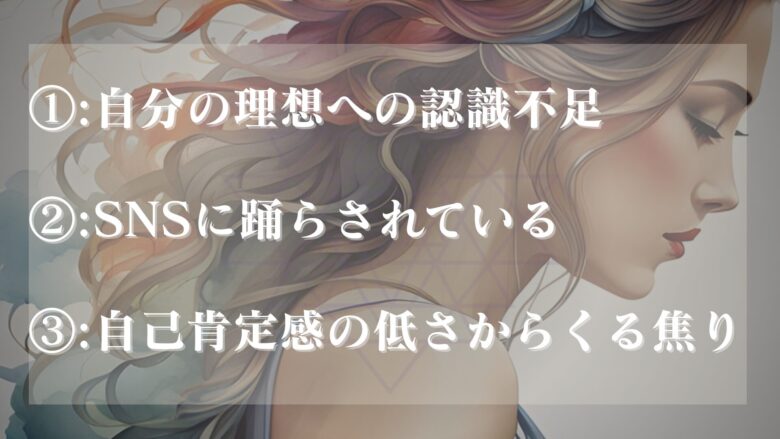
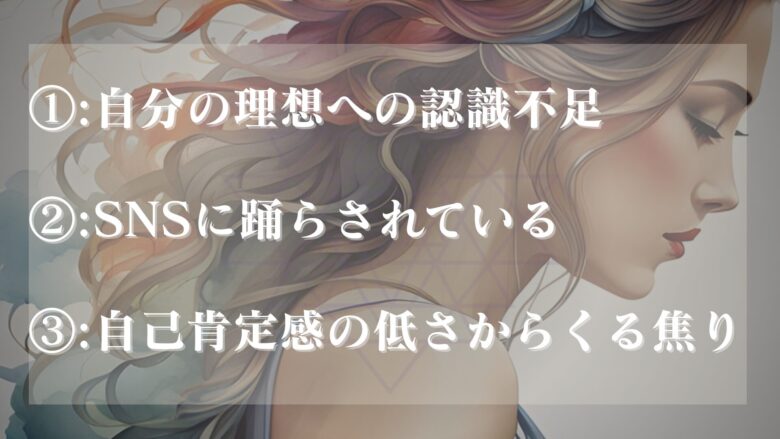



特に、自己肯定感の低さからくる焦りが主因やね。
「何者かになりたい」と思う方は、正直な所、何者かになりたいのではなくて「自分のことを愛し受け入れたい」という気持ちを「何者かになりたい」という欲望や言葉に置き換えているだけなのが実態です。彼らに本当に必要なのは、何者かになることでなく自己肯定感を高めることといえます。
なお精神状態が安定していればこそ、自己肯定感が格段に上がりやすくなりますので、日々のメンタルケアを徹底したいものです。自己肯定感が高まれば、何者かになりたいという思いは消え去るでしょう。とはいえ、自力で効果的なメンタルケア対策をきちんと行うのは、なかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
何者かにならなきゃ症候群とは何か?





何者かにならなきゃ症候群とは、なんなん?



んじゃ、詳しく見ていこうかの。
結論から言うと、「何者かにならなきゃ症候群」とは、「自分はまだ何者でもない」と感じて焦っている状態を表す俗語です。当然、DSM5に記載される正式な疾患名ではありません。
なお、エリクソンの理論にのっとれば「何者かにならなきゃ症候群」の特徴としては、以下の3要素があると考えられますね。
「何者かにならなきゃ症候群」の特徴
- 認欲求の強さ:他者からの評価や「すごい」と言われることを強く求める
- 自己評価の低さ:自分の現状や成果を過小評価し常に「もっと」と思ってしまう
- 目標の曖昧さ:何を達成したいのか具体的でないまま「何かすごいことをしなきゃ」と焦る
なお、この「何者かにならなきゃ症候群」は若年層に多いとされていますが、いわゆる「中年の危機」を迎えた成人たちにも同様のことが言えるでしょう。



たしかに、残りの人生が少なくなってきたら焦るよなあ、、。
いずれにせよ、「何者かにならなきゃ症候群」とはアイデンティティの危機に関連した状態ですので、ここから脱却するには深い内省やそれに基づく行動を通して、アイデンティティを構築・再構築、そして自己肯定感の向上などを行っていく必要があるといえます。
何者かにならなきゃ症候群に陥る3つの原因





何者かにならなきゃ症候群に陥る原因って、何なん?



原因は、おもに以下の3つやね。
何者かにならなきゃ症候群に陥る3つの原因
- 原因①:自分の理想への認識不足
- 原因②:SNSに踊らされている
- 原因③:自己肯定感の低さからくる焦り



それぞれ、詳しく見ていこう!
原因①:自分の理想への認識不足
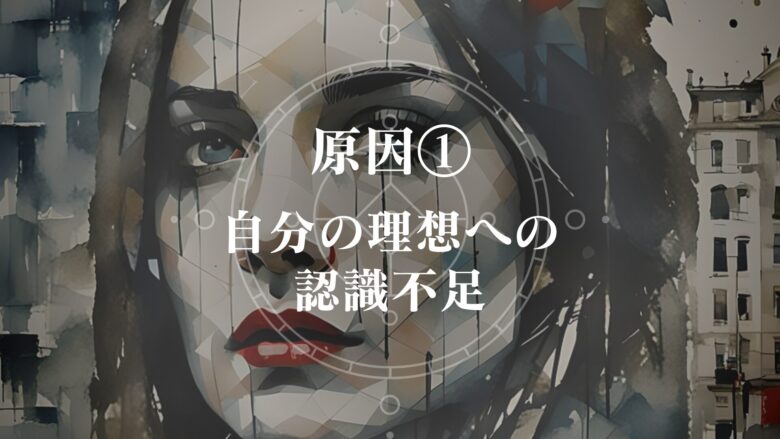
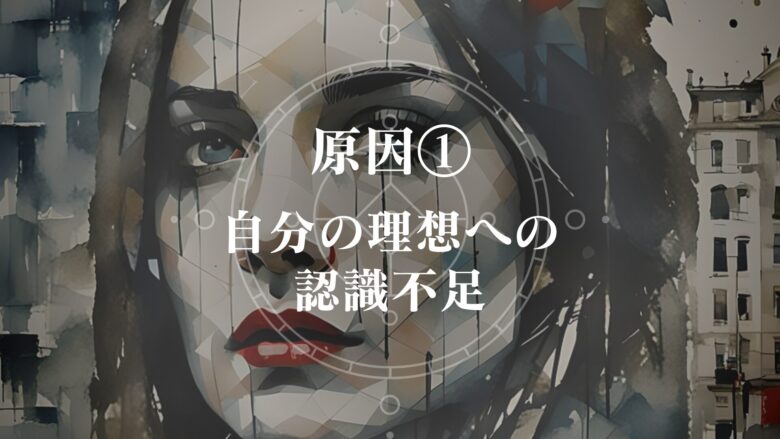
何者かにならなきゃ症候群に陥る原因の1つ目は、「自分の理想への認識不足」です。
多くの人が「何者かにならなきゃ」と感じる背景には、自分の理想像が曖昧であることが挙げられます。実際、心理学の以下の研究によれば、具体的かつ達成可能な目標を設定することで動機が高まり、満足感が得られやすくなる一方で、目標が不明確だと不安が増大するとされていますね。



確かに、目的設定がないと空回りしやすいね。
例えば、若年期は「有名になりたい」「すごい人になりたい」といった抽象的な願望を持つ人が多いですが、こうした抽象的な願望は具体的な行動に結びつかず、焦りを生むだけに終始することが非常に多いです。
さらに言えば、現代社会は情報過多で多様な選択肢がありますから、なおのこと「なんかしないといけない気がするけど、結局何をしていいかわからない」といった悪循環に陥りやすくなりますね。
原因②:SNSに踊らされている


「何者かにならなきゃ症候群」に陥る原因の2つ目は、「SNSに踊らされている」です。
SNSは「何者かにならなきゃ症候群」を増幅する主要な要因であり、ただでさえ厄介な「何者かにならなきゃ症候群」の症状をさらに悪化させます。



わかる、、SNSは、あまりにすごい人が多くて病むよね。
というのも、SNSの利用により社会的比較、特に「上方比較」(自分より優れた人との比較)が促進され、それが自己評価を下げる原因となってしまうから。
きっとあなたもInstagramやXで、インフルエンサーや成功者の「キラキラした生活」を見て、自分の平凡さを自覚し、不安や焦りが感じたという経験をしたことがあるでしょう。
実際、2021年の以下の研究では、SNSの過剰な使用が10代・20代のメンタルヘルスに悪影響を及ぼし、特に自己肯定感の低下や不安障害のリスクを高めることが報告されています。
Xの投稿でも、「SNSを見ると自分が何者でもない気がしてしんどい」という声が多く、SNSがこの症候群の引き金となっていることが明確です。
原因③:自己肯定感の低さからくる焦り
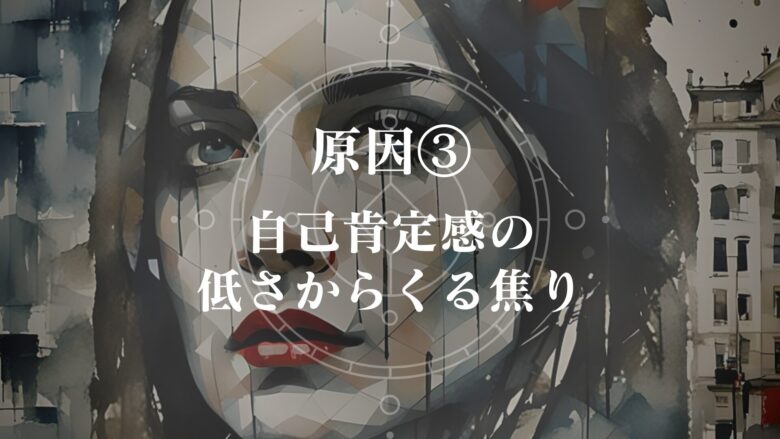
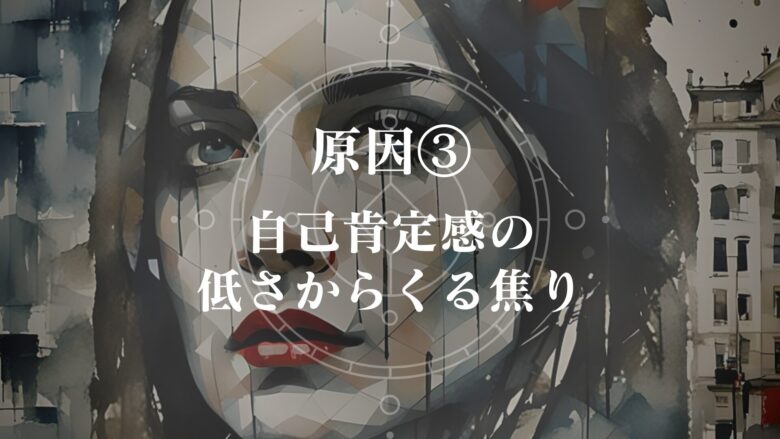
「何者かにならなきゃ症候群」に陥る原因の3つ目は、「自己肯定感の低さからくる焦り」です。これが、「何者かにならなきゃ症候群」の原因の大元といえるでしょう。
自己肯定感が低いと承認欲求が肥大化して自分を認められるようになるために、「何かしなくてはいけない」と過剰に焦りを感じてしまうものです。



自己肯定感が低いと、承認欲求強くなってしまうよねえ。
事実、ローゼンバーグの自己肯定感尺度に基づく研究では、自己肯定感が低い人は他者からの承認を強く求め、失敗や「普通であること」を過剰に恐れる傾向がることが報告されていますね。
さらにいえば、認知行動療法(CBT)の視点では、自己否定的な思考パターン(例:「自分はダメだ」「もっとすごくなければ」)がこの焦りを強化するといえます。
Xの投稿でも、「自分に自信がなくて何かすごいことをしないと価値がない気がする」という声が散見され、自己肯定感の低さがこの症候群の大きな要因であることがわかりますね。
何者かにならなきゃ症候群から脱却したいならすべき5つの方法





脱却するためには、どうしたらいいん?



以下の5つの方法をためしてみよう!
つぎは、「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法について、紹介していこうかと思います。
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法は、以下の通りです。
何者かにならなきゃ症候群から脱却したいならすべき方法
- 方法①:自分の大事にしたいものの明確化
- 方法②:幸せを追い求めるのをやめる
- 方法③:マインドフルネスを実践する
- 方法④:自分が今何者かを考える
- 方法⑤:不完全で完全と意識を変える



それぞれ、詳しく見ていこう!
方法①:自分の大事にしたいものの明確化


「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法の1つ目は、「自分の大事にしたいものの明確化」です。
前述のように、自己肯定感の低さや目標設定のあいまいさ、特に自己肯定感の低さに関しては「何者かにならなきゃ症候群」の主要因ですが、「自分の大事にしたいもの」を明確にすることでこの2つの要因に対して根本的な対策が可能になります。



そういうもんなん?
というのも、「自分の大事にしたいもの」は生きる方針を航海における羅針盤のように与えるので、迷いがなくなりますし、それに沿って生きそれを自覚するたびに「自分はきちんと望む方向を進んでいる」と再認できた自己肯定感が高まるから。この好循環に入ってしまえば、人生は勝ち確です。
たま、以下の研究では内発的動機(自分の価値観に基づく目標)が明確な人は、外部のプレッシャーに左右されず、満足感が高いと報告されていますから、ストレス耐性や逆境耐性も上がるでしょう。
参考: Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The “What” and “Why” of Goal Pursuits*. Psychological Inquiry
自分の価値観をはっきりさえる対方は、まずは、以下のステップを実践するのがいいでしょう。
紙に「何が自分を幸せにするか?」、「どんな人になりたいか?」、「自分の人生にどうあってほしいか」を書き出していく
書きだした項目を「最も大事」「そこそこ大事」に分類していく
例えば、「家族との時間を大切にしたい」なら、週末に家族と過ごす時間を確保するように計画するなど
より詳細に自分の価値観を明確にして自己肯定感を高めたい方は、手間はかかりますがぜひ以下の記事で紹介しているアプローチを試してみて下さいね。
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいなら自分の大事にしたいものを明確にしよう
方法②:幸せを追い求めるのをやめる
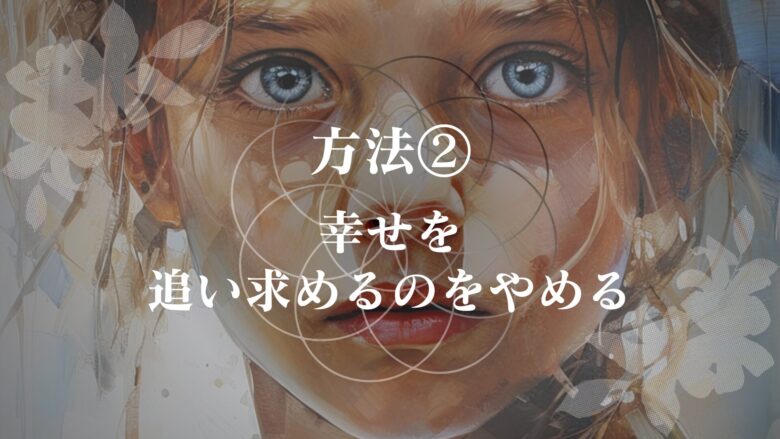
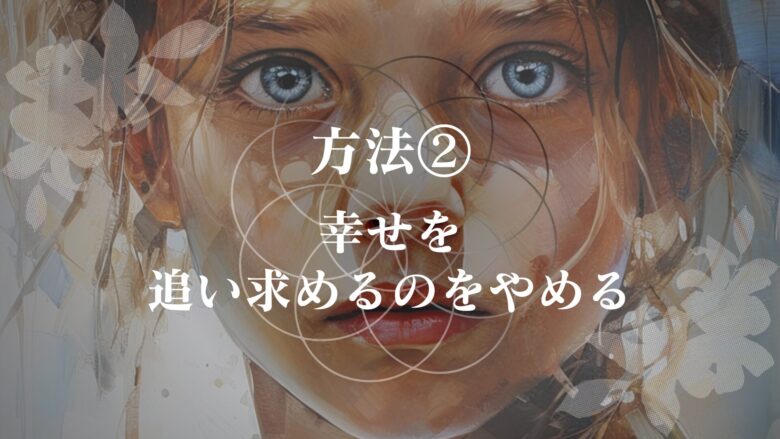
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法の2つ目は、「幸せを追い求めるのをやめる」です。
「幸せにならなきゃ」というプレッシャー自体が焦りを増幅するので、幸せを追い求める姿勢から「現状の生活の中に幸せを見出す」という姿勢に転換を図っていきましょう。



え?幸せを追い求めるのをやめるの?
実際、幸せを追い求める生き方をしていると、どんどんと幸せに対するハードルが高まっていくいわゆる快楽ジャンキーに近しい状態になってしまいます(ヘドニックてレッドミル効果による。幸福順応とも)。
事実、幸せになることを強く望む人ほど、日常での幸福感が低く、孤独や落胆を感じやすいという研究報告が存在していますね。
参考:Can seeking happiness make people unhappy? Paradoxical effects of valuing happiness.
そのため、幸せを直接追求していくのではなく、自分の生活の中に「これは幸せだと感じられるな」と思う要素を見出していく方が賢明といえるのです。
ちなみに、以下の研究では幸福を直接追い求めるよも、意味や目的を重視する生き方の方がメンタルヘルスに良い影響を与えるとされいますから、前述のように「自分の大事にしたいもの」を見つけるのも大事ですね。
参考:Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being.
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいなら:幸せを追い求めるのをやめよう
方法③:マインドフルネスを実践する
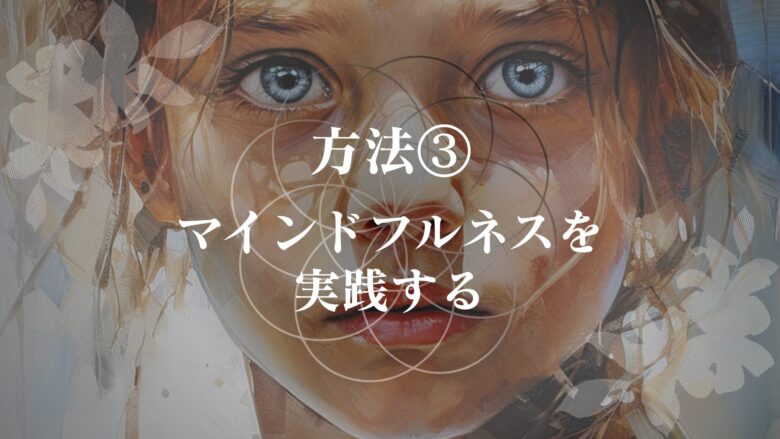
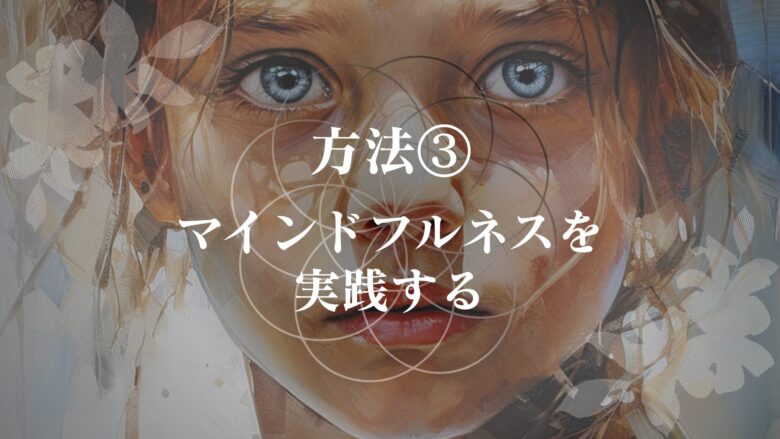
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法の3つ目は、「マインドフルネスの実践」です。
マインドフルネスは、現在の瞬間に意識を集中させ、過去や未来の不安から解放されるアプローチのこと。事実、以下の研究では、マインドフルネス瞑想がストレスや不安を有意に軽減し、自己受容を高めることが示されています。



ふむ、じゃあ、具体的な実践手順はどんな感じ?
なお、マインドフルネス瞑想の具体的な実践手順は、以下の通りです。
マインドフルネス瞑想の実践手順
静かな場所で、椅子や床に楽に座る(横になっても可)。スマートフォンや時計を近くに置き、5分タイマーをセット。
背筋を軽く伸ばし、肩をリラックス。目は軽く閉じるか、床の一点を見つめる。
息を鼻から吸い口から吐き、呼吸に意識を集中。吸う時に「お腹が膨らむ」、吐く時に「空気が抜ける」と感じる。思考が逸れたら、優しく呼吸に戻す(これが重要!)。
呼吸を続けながら、体の感覚(足、腹、胸など)を順に観察。緊張やざわつきがあれば、ただ「気づく」だけにとどめる。
タイマーが鳴ったら、ゆっくり目を開け、体の感覚や気持ちの変化を軽く振り返る。
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならマインドフルネスを実践しよう
方法④:自分が今何者かを考える
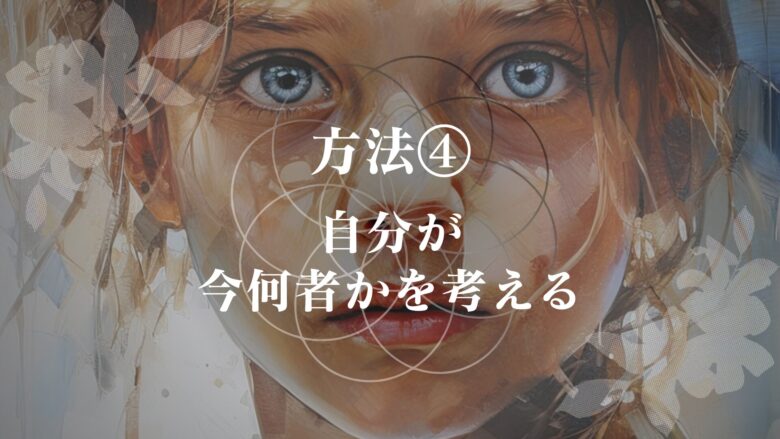
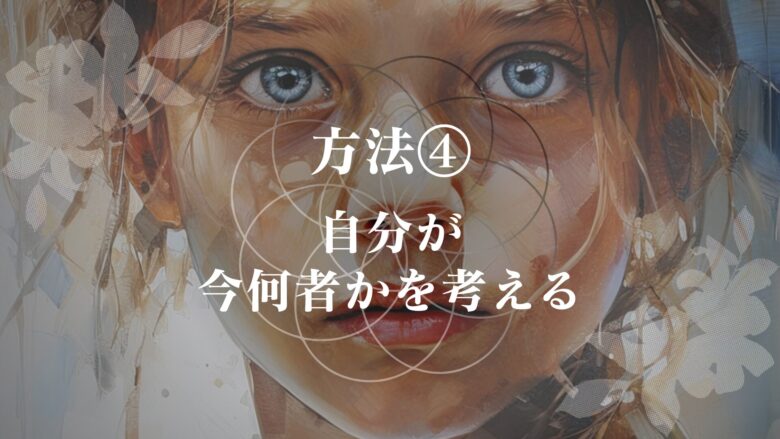
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法の4つ目は、「自分が今何者かを考える」です。
人は何かと「何者かになりたい」と思うものですが、正直、「何者か」にはなるものではなく「勝手に気が付いたら周りから評価されてなっているもの」でしかありません。結局、前述のように「何者かになりたい」という願いの正体は、「自分をもっと好きになりたい、受け入れたい」という渇望感でしかありません。



自分をもっと好きになりたい渇望感、、、そうかもしれんね。
いずれにせよ、「何者でもない」という感覚は、現在の自分を過小評価している可能性が高いので、まずは以下の取り組みを実践したうえで、「自分が他人から何者に見えているのか」を自覚することから始めるのがいいでしょう。
- 自己棚卸し:これまで達成したことや得意なことをリストアップする
- 他者の視点を借りる:信頼できる人に「自分の良いところ」を聞いてみる。
上記を実践して、まうは「何者かにならなきゃ」ではなく、「今すでに価値ある自分」に気づいていきましょう。無用な渇望感は、捨ててもっと身軽に生きていきましょう。
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいなら自分が今何者かを考えよう
方法⑤:不完全で完全と意識を変える
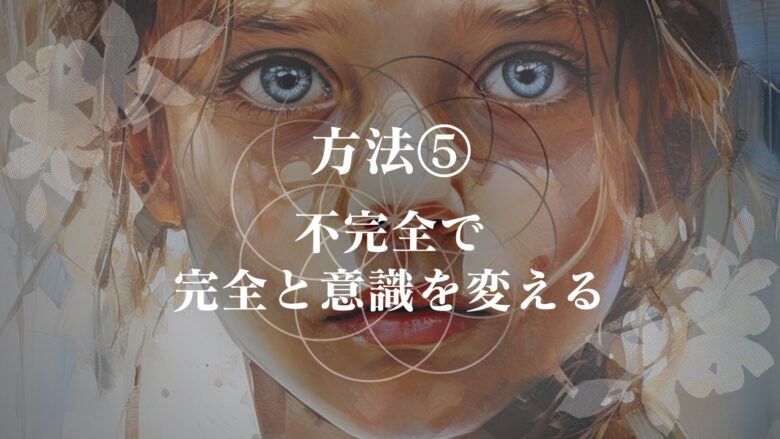
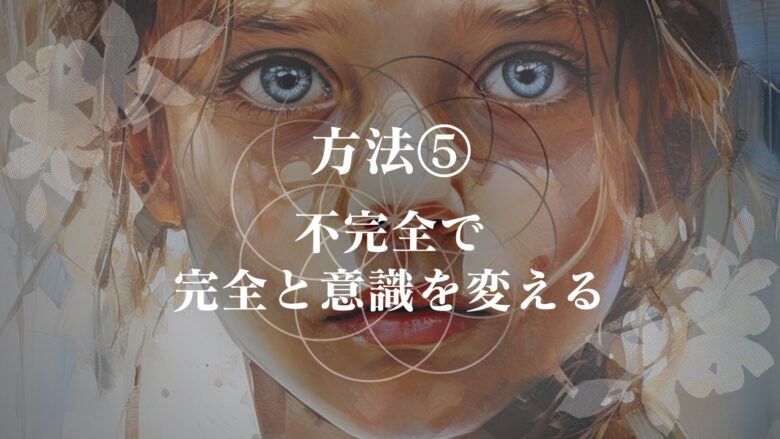
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいならすべき方法の5つ目は、「不完全で完全と意識を変える」です。
「何者かにならなきゃ症候群」に陥っている人の中には、「過度に理想化された自己像を追い求める不健全な完ぺき主義」をとっている方がままいます。こうした姿勢は自己受容の点から最悪なので、自分の不完全性を受け入れる姿勢を醸成していくのがおすすめですね。



ああ、、わかる。この姿勢取ると病むよね。
実際、人間は誰しも優れた部分と劣った部分の集合体であり、総体としてみたら非常に不完全です。ただ、それこそが完全、つまり「調和の取れた状態」でもあるので、不完全であることを悔いる必要は本来ありません。つまり、人はみな「不完全で完全」といえます。
なお、自己受容を高めたい方は、まずは以下のアプロ―チと実践していくといいでしょう。
- 「まあいいか」の習慣:小さな失敗や未達成を「まあいいか」と受け流す
- ロールモデルを見直す:完璧に見える人(例:インフルエンサー)も不完全であることを意識する
また、自己受容を高めるためには、セルフコンパッション(平たく言えば自分への思いやり)も有効です。セルフコンパッションの実践について、詳しくは以下の記事を見てみて下さいね。
「何者かにならなきゃ症候群」から脱却したいなら不完全で完全と意識を変えよう
何者かにならなきゃ症候群に関するFAQ





何者かにならなきゃ症候群に関して、まだ気になることが、、。



んじゃ、最後に疑問にこたえていこう!
最後に、何者かにならなきゃ症候群に関する疑問について、答えていこうと思います。
FAQ①:「何者かにならなきゃ症候群」は精神疾患?
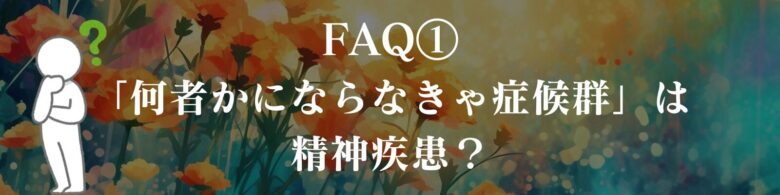
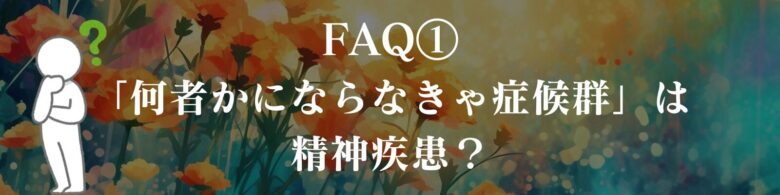
「何者かにならなきゃ症候群」は精神疾患ではなく、「自分はまだ何者でもない」と感じ焦っている状態をあらわす俗語です。心理学的には、この状態は社会的比較やアイデンティティ危機による産物といえるでしょう。
FAQ②:若者だけが「何者かにならなきゃ症候群」に悩む?
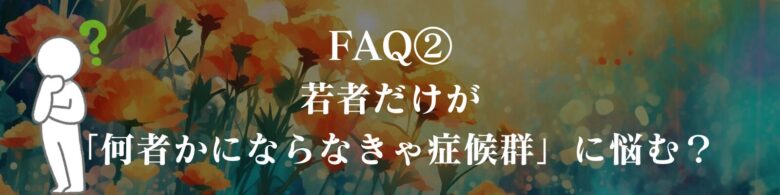
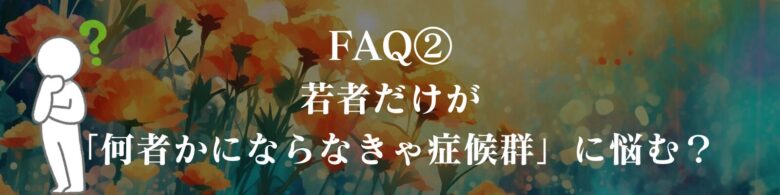
たしかに、「何者かにならなきゃ症候群」は若年層に多いと思いますが、どの年代でも発生し得ます。例えば、キャリアの転換期やライフイベント(例:転職、子育て終了)でアイデンティティを見失う中高年もこの焦りを感じることがあります。
実際、以下の研究では、40代の「中年危機」が類似の心理状態を引き起こすとされていますね。
FAQ③:周囲に「何者かにならなきゃ症候群」の人がいたらどう接すればいい?
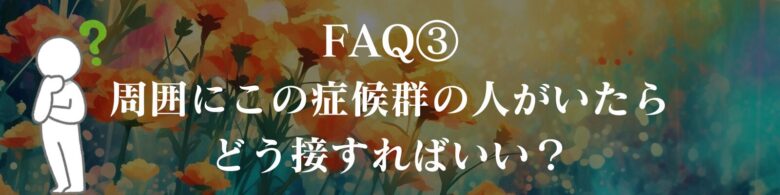
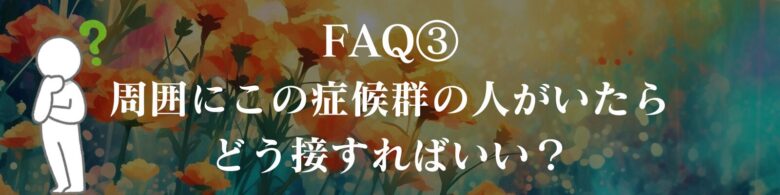
「何者かにならなきゃ症候群」の人に対しては、あえて共感的な傾聴、そして過剰なアドバイスを避けて無条件の肯定的関心により相手の自己受容をうながすのが得策でしょう。
例えば、具体的な強みを提示しつつ「今のあなたでも十分色々な事をできている」と気付きを与えるのがいいかもしれません。
参考:Client-centered therapy; its current practice, implications, and theory.
何者かにならなきゃ症候群とは「自分はまだ何者でもない」と感じ焦っている状態!まずは自分の人生で大事にしたいものをはっきりさせよう!


何者かにならなきゃ症候群とは、「自分はまだ何者でもない」と感じ焦っている状態のことです。何者かになりたいと思っている方は、何者かになることを望んでいるというよりも、「自分が自分のことをもっと愛したい、受け入れたい」と思っているというのが実情といえます。
自己肯定感をあげていくためには、人生で大事にしたいものを明確にしそれに従って生きるのが大事ですから、まずは大事にしたいものを見つけるのが大事でしょう。またその際はその土台となる心の安定をきちんと確保する必要もあります。日々きちんとメンタルケアを徹底し、精神状態を整えるように努めていくのが最善です。



精神が安定していてこそ、自己肯定感健全に育つんや!
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、人間関係と人生を豊かにしていくための下地を整えていきましょう!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\