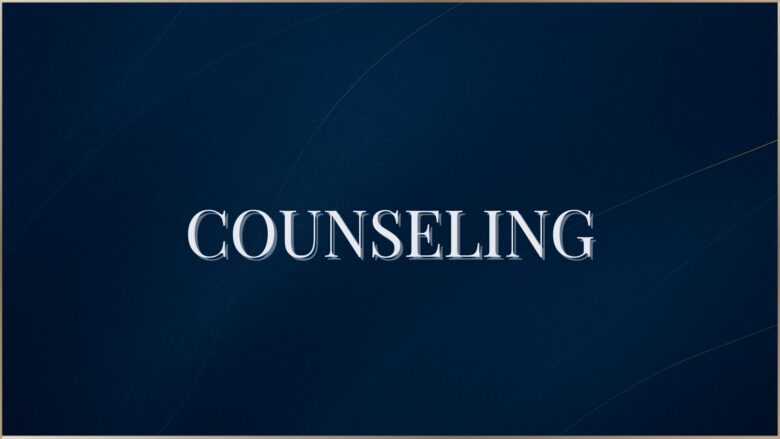おにぎり
おにぎり人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇って、誰の名言?



喜劇王のチャップリンやね。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言があり、しばしばネット上で使われているのを目にします。フレーズ内に悲劇と喜劇が同居しており、少し不思議な印象を受ける名言です。正直、私は「なんか変わった名言だな。誰の名言だ?」と気になっていました。
ですから、「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言が、誰によるものか気になりますよね?結論から言うと、「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言は、喜劇王のチャップリンによるものです。なお、この名言からわかる人生をポジティブに生きる秘訣は以下の通り。
人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇からわかるポジティブに人生を生きる秘訣
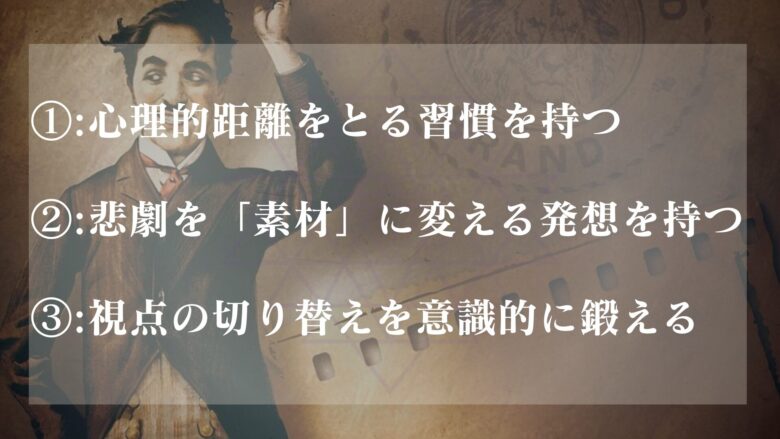
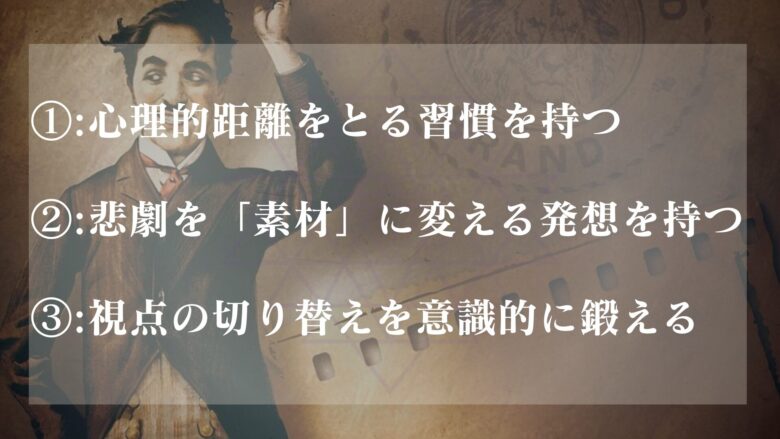



特に、心理的距離をとる習慣を持つのが大事や!
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からは、自分の経験をとらえる視点取り次第で、逆境耐性を高められるという教訓が得られます。また逆境耐性を高めるためには、マインドフルネスなどを習慣化して意識の使い方を体得する必要もあるでしょう。
意識の使い方に習熟すれば、不安や恐怖を感じても相手にせず自分の人生を快適に生きていくことが可能になります。そのため、日々マインドフルネスを活用したメンタルケアを徹底した方が賢明です。とはいえ、自力でこうしたメンタルケア対策をきちんと行うのは、なかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言の起源
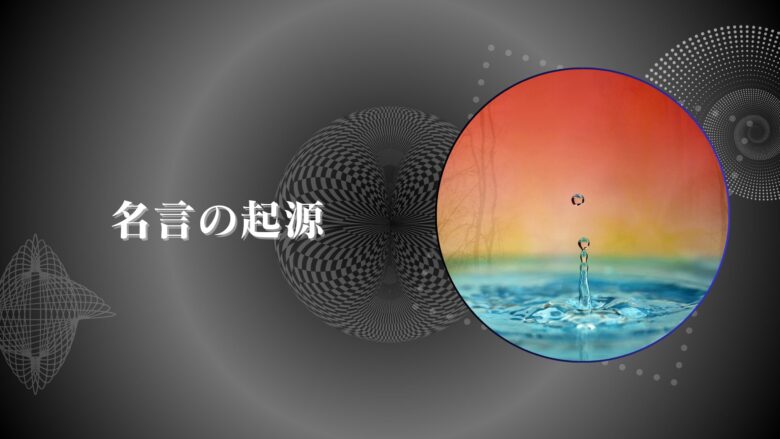
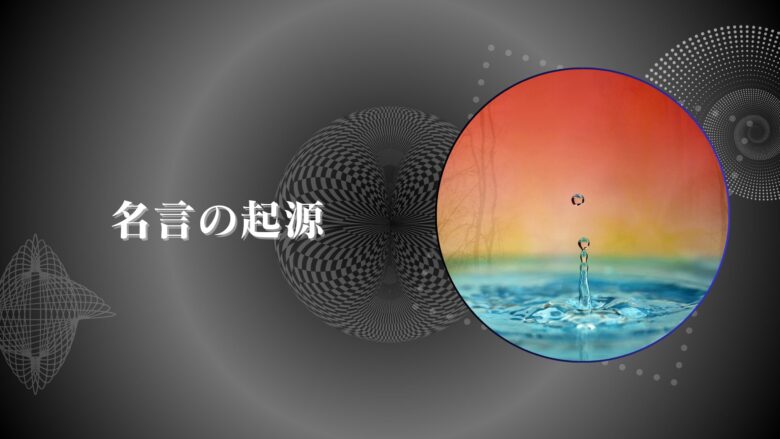



この名言の起源ってなんなん?



有力なのは、リチャード・ラウドの解説文やね。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」とは、世界の喜劇王の一角であるチャールズ・チャップリンによる名言であり、原文は以下の通りです。
Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.
引用:Goodreads
この名言の起源・出典については諸説ありますが、最も有力なものは「1972年にニューヨークのフィルハーモニーホール(現リンカーン・センター)で開かれたA Salute to Charlie Chaplinというイベントで配布された公式パンフレットに掲載された映画批評家リチャード・ラウドによる解説文」という説です。



へー、そんな起源には諸説あるんかあ。
なお、チャップリン自身は1916年の著書『Charlie Chaplin’s Own Story』の冒頭において、「人生はそれ自体コメディであり、悲劇か喜劇かは見方次第で両者の差は紙一重だ」と書いています。
ここでは映画用語である「クローズアップ、ロングショット」を用いた比喩は使われていませんが、当時から彼の脳内には「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」の原型があったことが見て取れますね。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言に込められた思い





この名言には、どんな思いが込められてるん?



ちょっと、込められた思いについて見ていこう!
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言には、「どんな痛みも、視点を変えれば物語になる」というメッセージが、込められていると思われます。
というのも、チャップリンの人生と作品が、「悲劇(痛み)→喜劇(物語)への変換」という構造で一貫しているからです。では、ここで彼の人生史と悲劇と喜劇を対応させて俯瞰してみると、以下の通り。
| 年代 | 出来事(現実) | 近くで見たら(悲劇) | 遠くから見たら(喜劇/意味) |
|---|---|---|---|
| 1889年 | ロンドンの貧民街に生まれる | 不衛生で貧困、教育もほぼ受けられず | 後の「小さな浮浪者(トランプ)」キャラのリアリティと温かさの源泉 |
| 1890年代半ば | 父アル中で死亡、母精神疾患で施設へ、自身も孤児院入り | 幼少期に両親と離別、極度の飢えと孤独 | 『キッド』で描かれる親子愛と路地裏のユーモアの原風景 |
| 1903〜1913年 | 劇団・ミュージックホールで下積み | 舞台裏の劣悪環境、低賃金 | “身振り一つで観客を笑わせる”技術を磨き、後のサイレント映画の核に |
| 1914年 | キーストン社で映画デビュー | 才能を誤解され、当初は粗暴キャラ配役 | トランプ役の発明により、世界中の笑いのアイコンに |
| 1921年 | 『キッド』公開 | 孤児の悲劇を演じながら自らの過去と向き合う | 世界中が笑いと涙で共感、芸術的評価確立 |
| 1931年 | 『街の灯』制作 | 大恐慌下、無声映画に固執し批判される | ラストの笑顔で“悲劇と喜劇が同居する”表現を完成 |
| 1940年 | 『独裁者』公開 | ナチス風刺で政治的に物議 | ラストの演説は希望と人間愛を全世界に届ける |
| 1952年 | アメリカ入国拒否(マッカーシー時代) | キャリア中断、事実上の亡命 | スイスで静かに創作継続、『ニューヨークの王様』で風刺に転化 |
| 1972年 | 「A Salute to Charlie Chaplin」で米国復帰 | 20年の不遇を経ての帰還 | 観客総立ちの拍手 → 人生そのものがドラマチックな“喜劇”に |
| 1977年 | 逝去(88歳) | 生涯にわたりスキャンダルや批判も多かった | 世界的レガシーとして、悲劇も喜劇もすべて作品に昇華した人生 |
上表からわかるように、彼の人生は幼少期の極貧・孤児生活からのスタートであり、当時は耐え難い現実(悲劇)に間違いありませんでしたが、後に『キッド』やトランプ役の原風景として作品に昇華(物語)されています。
さらに言えば、晩年の政治的亡命という屈辱も、後の風刺作品や復帰劇のドラマとなっています。そして、彼の映画は、クローズアップで人物の切実な感情を映し、ロングショットで状況全体の滑稽さを見せる構造を多用しており、彼の映画と人生は同じような構図をとっている点がわかりますね。



まあ、言われてみればそうだね。
彼の「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言は、「人生で遭遇するいかなる悲劇であっても後になって考えてみれば自分の素晴らしい人生という物語の一ページになるのだから、前を向いていきていこう」といった力強いエールと解釈できそうな気がしますね。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からわかるポジティブに人生を生きる3つの秘訣





何か、この名言からわかることってあるん?



せやなあ、以下の3つかな。
つぎは、「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からわかるポジティブに人生を生きる秘訣について、見ていきたいと思います。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からわかるポジティブに人生を生きる秘訣については、以下の通りです。
人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇からわかるポジティブに人生を生きる秘訣
- 秘訣①:心理的距離をとる習慣を持つ
- 秘訣②:悲劇を「素材」に変える発想を持つ
- 秘訣③:視点の切り替えを意識的に鍛える



それぞれ、詳しく見ていこう!
秘訣①:心理的距離をとる習慣を持つ
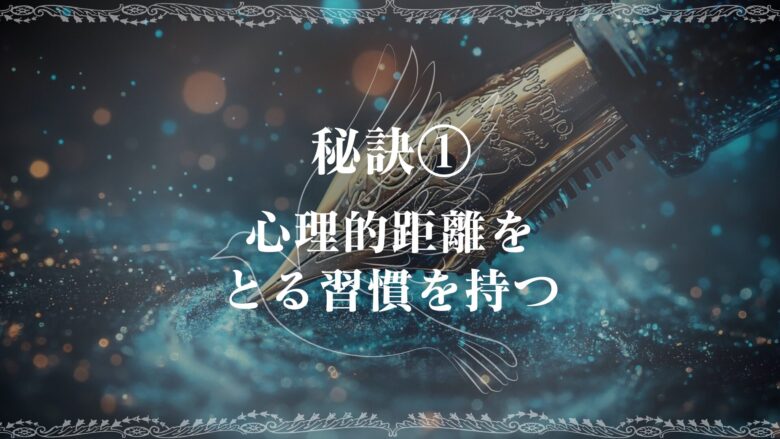
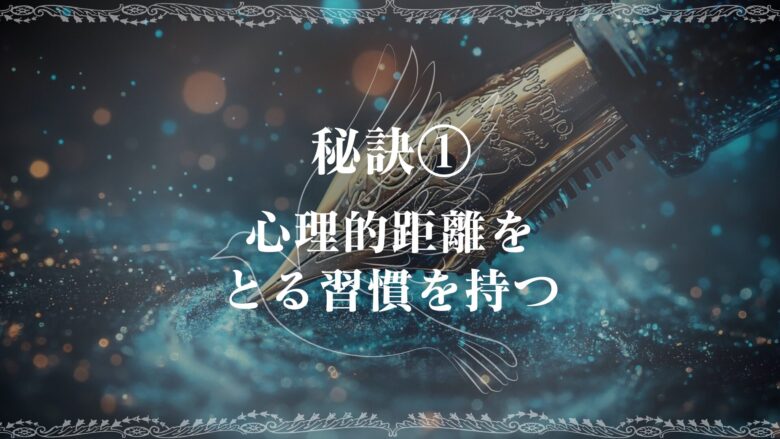
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からわかるポジティブに人生を生きる秘訣の1つ目は、「心理的距離をとる習慣を持つこと」です。
時間的・空間的・社会的に距離を置くことによって、人は物事をより抽象的まつ広い視点で捉えられるようになります。そう様な視点が確保できれば、目先の感情に圧倒されず、建設的な意味づけがしやすくなるものです。



距離をとると、冷静になれるんね。
事実、以下の研究では、ストレスフルな出来事を「自分を第三者視点で観察する」ことで、感情の強度が下がり、長期的な学びや解決策を見出しやすくなることが示されています。
参考:Making meaning out of negative experiences by self-distancing.
そのため、ある時に体験したつらい体験も後で振り返ってみたら、冷静にそのつらい体験から学びなどのポジティブな側面を見出せたりするわけです。それを事前に理解しそう考える事を習慣化していればこそ、つらい出来事に直面しても必要以上に絶望しないで済む可能性が高まります。
また、嫌な出来事があったとき、「これは1年後の自分にとってどう見えるだろう?」と問いかける習慣をもつのも、効果的でしょう。
秘訣②:悲劇を「素材」に変える発想を持つ
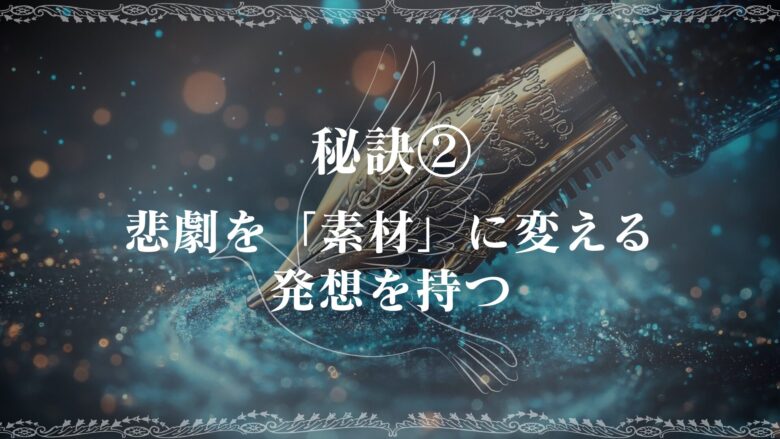
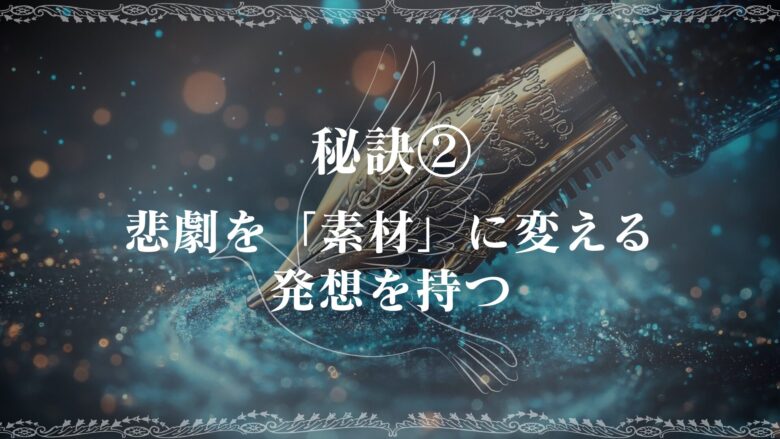
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からわかるポジティブに人生を生きる秘訣の1つ目は、「悲劇を「素材」に変える発想を持つこと」です。
人生の中で遭遇する悲劇も乗り越えてユーモアをもってとらえることができるようになれば、それこそ「自分の人生の物語の中にポジティブな意味での素材として組み込める」様になります。



ふむ、ユーモアかあ、、。
事実、以下の研究では、ネガティブな出来事をユーモアに変換することは感情の再評価として働き、ストレス反応を減らすことが報告されたり、困難な経験を人生の意味・人間関係・価値観の再構築につなげた人ほど幸福感・人生満足度が高まることが報告されていますね。
参考
Target Article: “Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence”.
Humour as emotion regulation: The differential consequences of negative versus positive humour.
例えば、失敗談を友人に話すときに、意図的に笑いどころを作ったり、困難を「この経験が小説や映画ならどう描かれるか?」と考える事は効果的でしょう。
なお、ユーモア自体を高めたい方は、以下の記事を見てみてくださいね。
秘訣③:視点の切り替えを意識的に鍛える
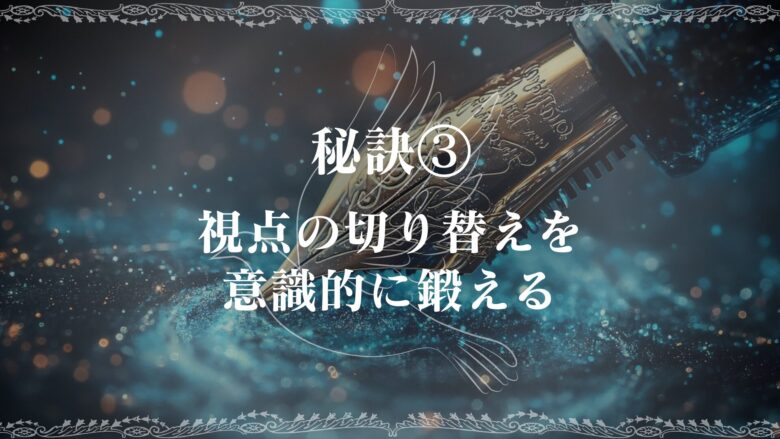
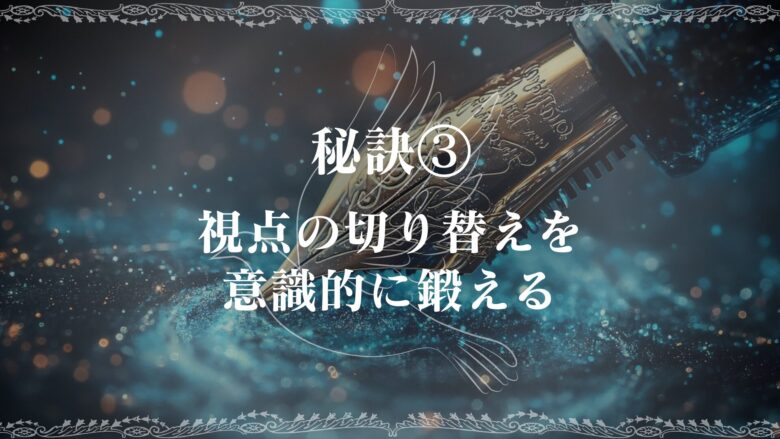
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言からわかるポジティブに人生を生きる秘訣の1つ目は、「視点の切り替えを意識的に鍛えること」です。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言は、体験を評価する際の視点取りの重要性説くもの、もっといえば、心理的柔軟性の重要さを説いたものともいえます。



心理的柔軟性かあ。
なお、心理的柔軟性は、ACT(Acceptance and Commitment Therapy)の中核概念であり、ストレス耐性や幸福度と強く関連するものです。
参考:Psychological flexibility as a fundamental aspect of health
心理的柔軟性を高めるためには、まず一つの出来事に対してあえて複数の見方を試してみましょう。そして、さらに心理的柔軟性を高めたいのであれば、自分の大事にしたいものを見つけそれに沿って生きていくようにするのが最善です。
自分の大事にしたいものを見つけたいのであれば、以下の記事を参考にするのがおすすめです。手間はかかりますが、きっと自分の大事にしたいものが見つけられるでしょう。
人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇に関するFAQ





まだ、気になることがあるんよね。



んじゃ、最後に疑問にこたえていこうかの!
最後に、人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇に関する疑問について、答えていきたいと思います。
FAQ①:チャップリンの他の名言で似たテーマのものはある?
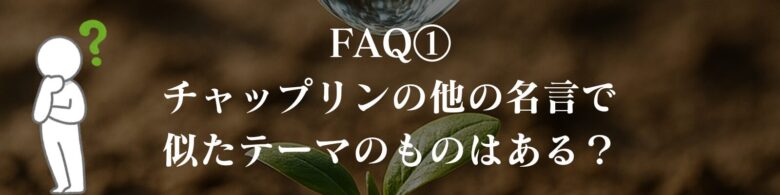
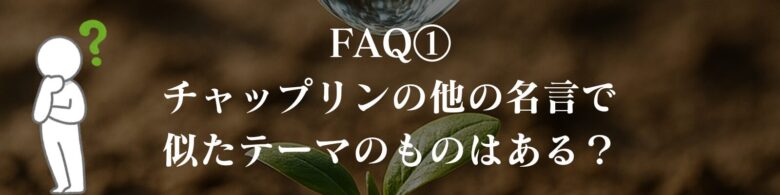
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」と似たテーマのものとしては、「笑いなくして、私は人生を乗り越えられなかっただろう」があげられるでしょう。
この名言は、ユーモアが人生の困難を乗り越える力になることを強調しているという点が、共通しています。
FAQ②:この名言を日常でどうやって思い出す?
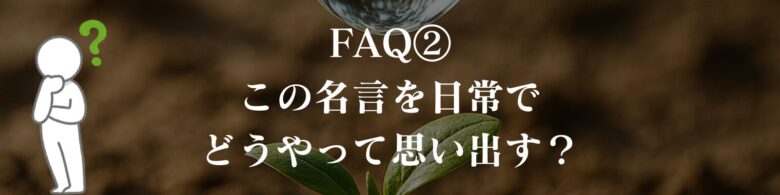
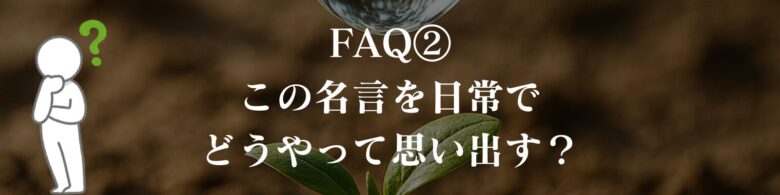
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言を活用するためには、視覚的リマインダーや習慣化が有効です。例えば、スマホの壁紙に名言をセットしたり、朝のルーティンで「今日の悲劇をどう喜劇に変える?」と自問する習慣をつけるといった感じですね。
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」はチャップリンの名言!
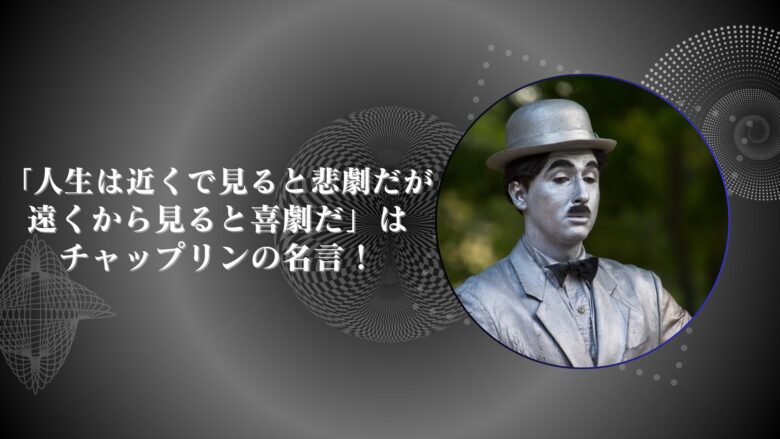
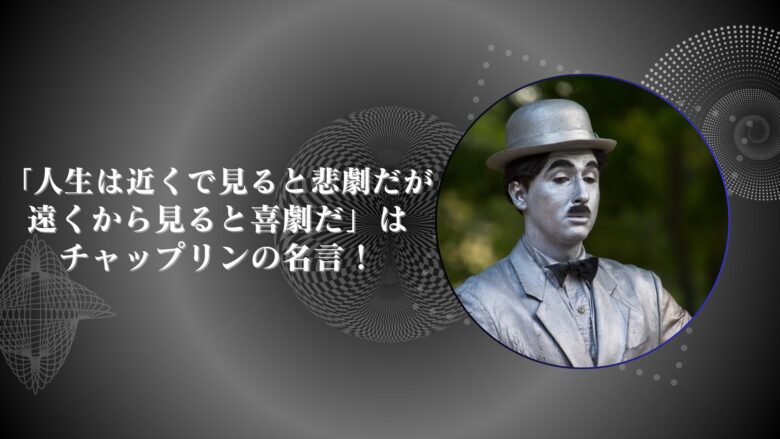
「人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見ると喜劇だ」という名言は、チャップリンによるものです。この名言からは、逆境耐性を高めるためにいかに視点取りが重要であるかという教訓が得られます。また、逆境耐性を高めるためには、日々マインドフルネスなど各種メンタルケア方法を実践するのも大事です。
マインドフルネスの実践により意識の使い方がうまくなれば、不安や恐怖といったネガティブな感情に直面しても理性を保って冷静に目の前の課題と向き合うことができます。そのため、日ごろからマインドフルネスを活用したメンタルケアを徹底していくことが、非常に重要です。



マインドフルネスで意識の使い方を体得するのは、めっちゃ大事!
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、どんな逆境にも負けず生きるための下地を整えていきましょう!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\