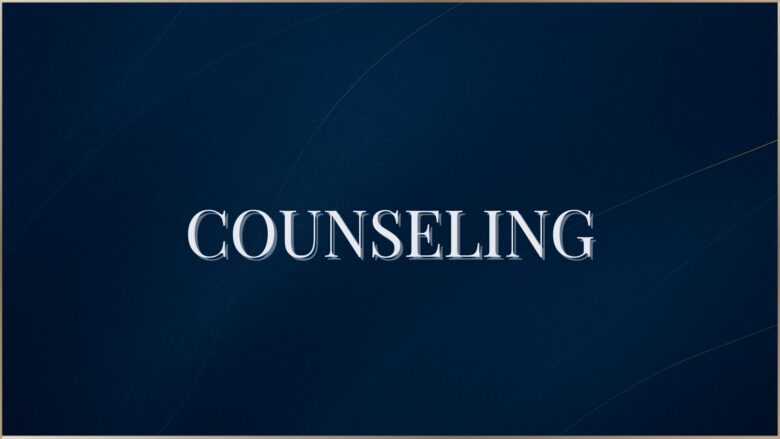おにぎり
おにぎり真の弱者は助けたくなるような姿をしていないって、ガチ?



んー、一理はある!一理はね。
最近、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」とネットなどでよく言われますが、今までの人生を振り返ってみて「確かに、、」と思う方も多いかもしれます。それと、エックスなど各種SNSを見てみても、納得してしまう方も多いでしょう。
そんな感じですが、実際の所、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」は本当なのか、気になりますよね?結論から言うと、あくまでも私の経験やその他関わってきた人たちの発言などから考えると、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には、一理あります。
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には一理ある理由
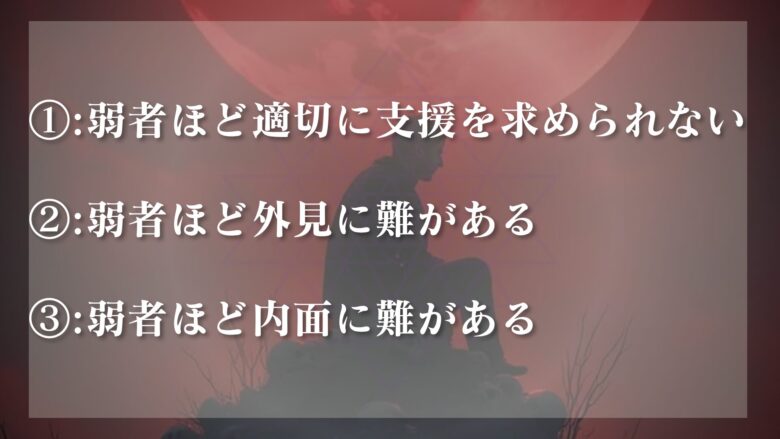
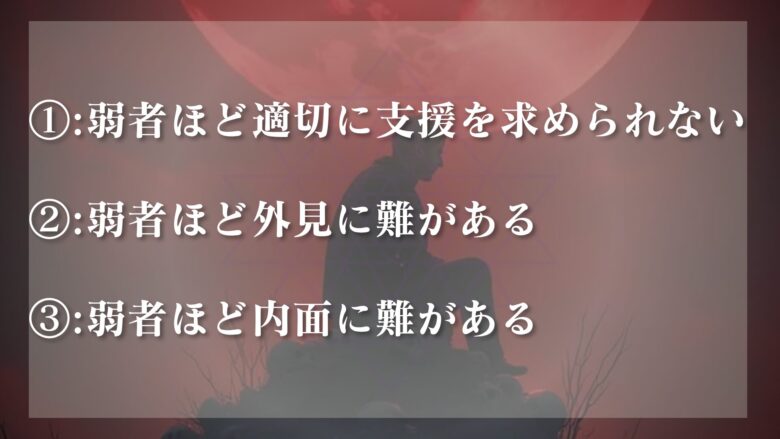



弱者ほど内面に難があるのが一番の要因よなあ、、、。
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」という言葉は、「弱者ほど汚らわしく醜い外見だ」と解釈されがちですが、実際は内面(無感謝、不愛想、無配慮など)の醜悪さやそれがにじみ出た雰囲気をしているといった方が正確です。弱者ほど内面に難があるので、万が一のために誰しも内面はよくしておくに限ります。
ちなみに、公式ラインでは「人との関わりをうまく築きたい」、「誰かの期待じゃなく自分の意志で生きたい」、そんなあなたのために不定期で心理学的ヒントを発信しています。ただ今LINE登録者限定で、心の軸を取り戻すための限定記事や表ではあまり言えない実践知ベースの限定記事のパスワードをプレゼント中。
あなたの生き方を少しずつ再構成していくヒントをお届けします。今すぐ登録して、あなたのペースで心を整えていきましょう!
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には一理ある3つの理由





真の弱者は助けたくなるような姿をしていないは、ガチなん?



せやな、一理はあるんやで。
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」は、かなり強烈な表現であり、実にセンセーショナルですが、事実の一側面をきちんと投影した表現であり一理あるといえます。
そこでまずは、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」に一理ある理由について、見ていきたいと思います。「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」に一理ある理由は、以下の通りです。
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」に一理ある理由
- 理由①:弱者ほど適切に支援を求められない
- 理由②:弱者ほど外見に難があることが多い
- 理由③:弱者ほど内面に難があることが多い



それぞれ、詳しく見ていこう!
理由①:弱者ほど適切に支援を求められない
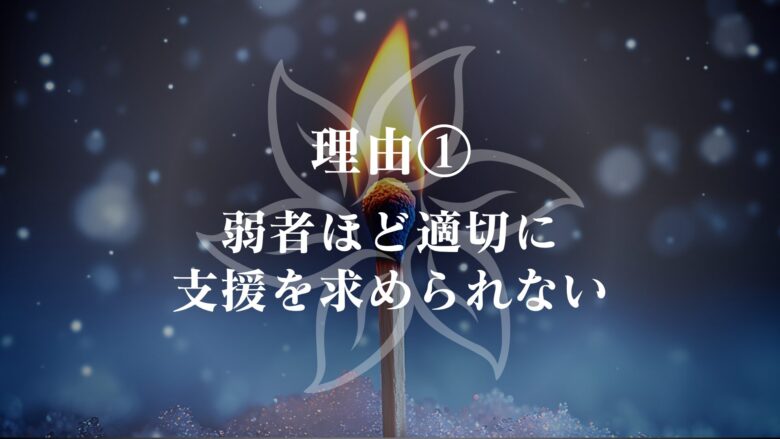
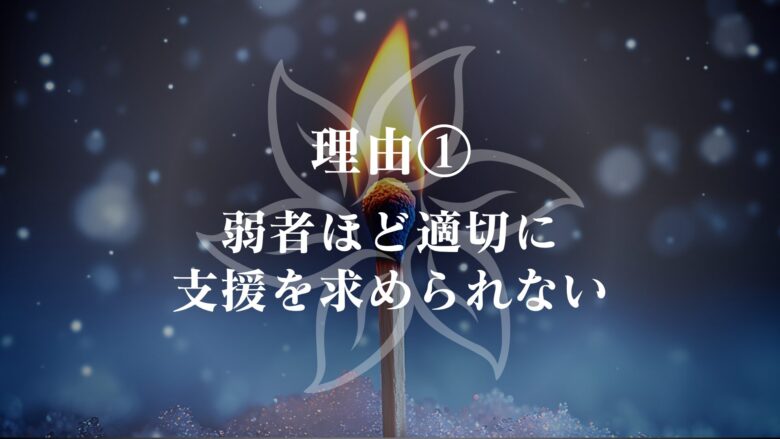
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には一理ある理由の1つ目は、「弱者ほど適切に支援を求められない」です。
人は他者の感情や苦境を、感情的に共感できるとき支援行動に動きやすいとされています。逆に、苦境が曖昧だと介入が減ることが多数の実験で示されています。特に、「明らかな苦痛・顕在化したニーズ」は援助を誘発するものです。



なるほど、みんな思っているより人の事気にかけてるんやな。
そのため、「困っているならとにもかくにも助けてほしいと声をあげることが大事」なわけです。そうでなければ、誰もその人が何に困っているかorそもそも助けてほしいのかすらわかりませんからね。しかし、いわゆる真の弱者といわれる人ほど、自己表現がつたなすぎたり変なプライドを守って、助けを求められません。
これでは「助けたい」と思う人がいても、助けようがないですよね。真の弱者は自分が困っていて助けてほしいと思っているということを、表明することに困難を抱えていることがかなり多い印象があります。
理由②:弱者ほど外見に難がある
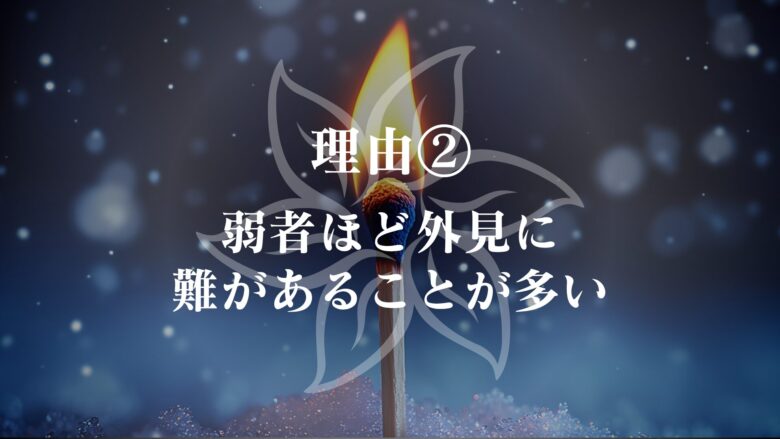
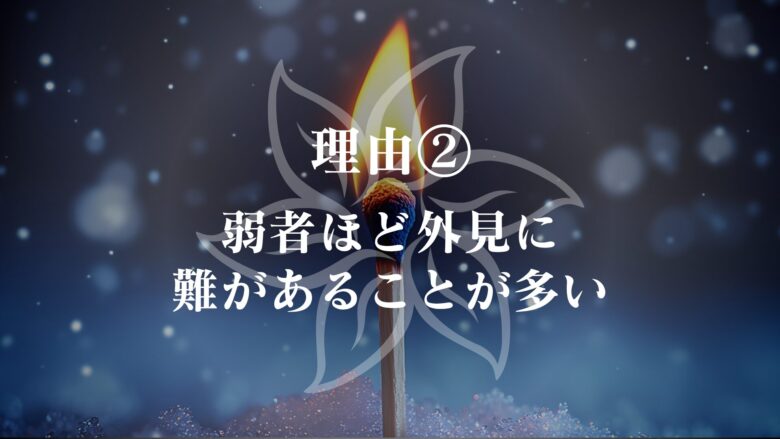
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には一理ある理由の2つ目は、「弱者ほど外見に難がある」です。
いささか私の偏見も入ってしまうと思いますが、真に助けが必要な弱者とされるような人ほど、文字通りの清潔感が非常に欠如した不衛生的な見た目をした人が多い印象があります。また、後述するような「嫌悪されるような内面」がにじみ出たような雰囲気をまとった顔つきをしている気もしますよね。



もう、ボロカスに言いすぎやろ。
たまに「真の弱者ほどブサイクだ」みたいな感じでとらえる方がいますが、ここでいう「姿」とは造形の話というよりも、顔つき(人相)とか気遣いのなさがよく見て取れる雰囲気といったそっちの意味で外見に難があるといった感じです。
つまり、あまりにも不愛想とかあからさまにいつも不機嫌そうで攻撃的、、、等といった中々言語化しにくい雰囲気が問題の核心なんですよね。しかし、本人にもそれなりに事情があるわけで、そこは中々「執拗に非難するのは違うのでは?」、、と思う所ですよね。不愉快な人の気持ちもわかりますけど。
理由③:弱者ほど内面に難がある
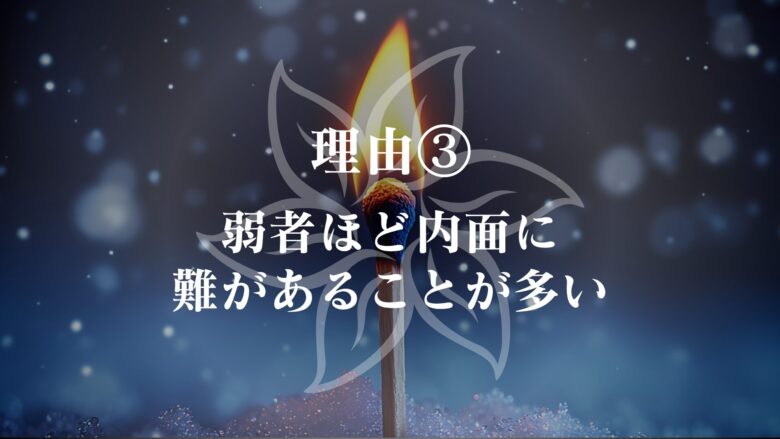
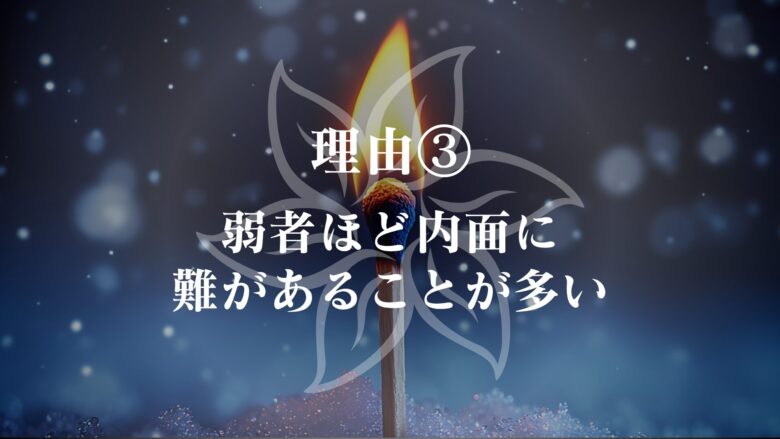
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には一理ある理由の3つ目は、「弱者ほど内面に難がある」です。
前述のように、支援がうけられるかは外見に左右されることも多いですが、それ以上に支援側は「その対象が支援するに値するような人間性であるか」という内面要素を基準に支援するかどうかを決める傾向にあります。



やっぱ、大事なのは人間性なんやね。
実際、CARIN原則によれば、行為の原因(自業自得かどうか)、恩返しの可能性、態度の良さ、同一性(関係性)といった4つが判断基準になり、これらを示せない人は援助が得にくくなるとされています。
たとえば、「不愛想、ノーリアクション、無感謝、傲慢に八つ当たりしてくる」あたりがそろうと、個人的に結構しんどい気がしていますね。あとは、手を貸したとしても、平気で裏切ってくるなんてこともあるでしょう。もう、恩義もくそもあったものではない、、、みたいなね。
私の知り合い等から聞いた話で恐縮ですが、特にクレーマー気質でプライドが無駄に高く何かと他人をこき下ろすといった謎の攻撃性を発揮している人の中に、かなり支援が必要そうな人(詳しくはあえて語らないが、、)が多いようですね。まあ、何となく、エックスな度を見ていると、納得してしまう所がありますねえ、、。
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」の起源
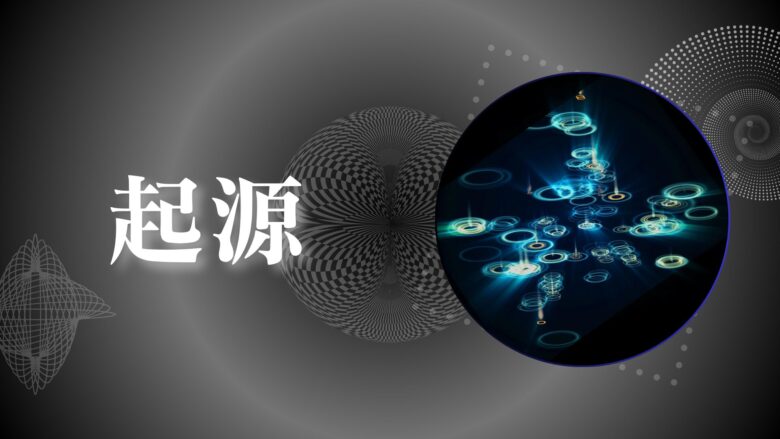
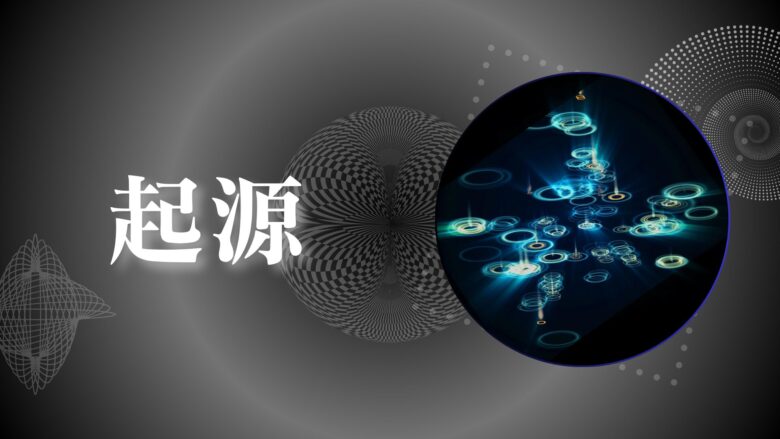



「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」の起源って?



正直、はっきりしなんよね。
決論から言うと、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」という言い回しの起源について、確たることは何も言えません。一般に、この言葉の起源をロシアの小説家であるトルストイに求める向きもありますが、実際に典拠となる一文は確認できないので、おそらく思い込みで拡散されたものと思います。
ちなみに、トルストイの作品内には似たような表現として「the children who need love the most will always ask for it in the most unloving ways(最も愛を必要とする子どもは最も愛らしくないやり方で求める)」といったものがあり、これは現状教育界で広く引用されているようです。
この言葉は臨床心理学者Russell Barkley が教師の言葉として取り上げたことで普及した



よくあるよねえ、思い込みで拡散されるの。
そのため、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない、助けるべき弱者は私たちが助けたいと思える姿をしていない」という言い回しは、「トルストイならいいそうだ」ということで勝手に納得されて、拡散されてしまったといえるでしょう。
真の弱者に落ちないために大事な3つのこと





真の弱者には落ちたくないなあ、、、。



ふむ、ならば、以下の事に気をつけるといいぞい。
つぎは、真の弱者に落ちないために大事なことについて、ふれていきたいと思います。真の弱者に落ちないために大事なことは、以下の通りです。
真の弱者に落ちないために大事なこと
- 最低限嫌悪されない見た目を作る
- 必要なら積極的に助けを求める
- 感謝と努力をきちんと示す



それぞれ、詳しく見ていこう!
最低限嫌悪されない見た目を作る


真の弱者に落ちないために大事なことの1つ目は、「最低限嫌悪されない見た目を作る」です。
人には病原性を検出する仕組みが備わっているのでを、汚れや不潔さが明確だと回避・不信感がかんきされてしまい、援助しようという気持ちが起こりにくくなります。そのため、別に整形して少しでも美形に近づく、、なんてことはしなくていいとしても、衛生的な身なりを心がけるのはマストです。



ふむ、そらそうやな。衛生的なのは大事よな。
実際、外見・衣服・身だしなみが整っていると、接近・助力の心理的ハードルが下がります。
参考:Disgust as an adaptive system for disease avoidance behaviour
具体的な指針としては、以下の様な事に気を付けたいですね。
- 髪に関してはベタつき・フケ・寝ぐせはゼロにする
- 肌の乾燥・脂・荒れを整える(特に「テカリ」は不潔印象を強化)
- 服はシワ・毛玉・ヨレなしをいしき。(清潔な色味(白・淡色系)が有利)
- 口臭・体臭は対人距離1mで「無臭」レベルがとりあえずの目標
- 場に合わない格好もできるだけしない
ちなみに、余談ではありますが、生物は本能的にベビースキーマに対して庇護欲がわくものなので、可能な人はメイクなどを活用してベビースキーマ的印象を強めるのもありだと思います。実際、中顔面が短く余白の少ない小顔な人は見ている感じ、男女ともに誰かに助けてもらいやすい印象ですから。
逆を言うと、面長で余白が多い顔だと「この人は一人でもなんとなるね」といった印象を持たれやすく、あまり助けてもらえない感じがします(ここら辺が男性が気にかけてもらえない事が多い理由の1つだと思っている。男性は女性に比べると明らかに余白多めの面長が多いので)。
とりあえず、できる事からでいいので、改善していきたいものです。
真の弱者に落ちないためには最低限嫌悪されない見た目を作ろう
必要なら積極的に助けを求める
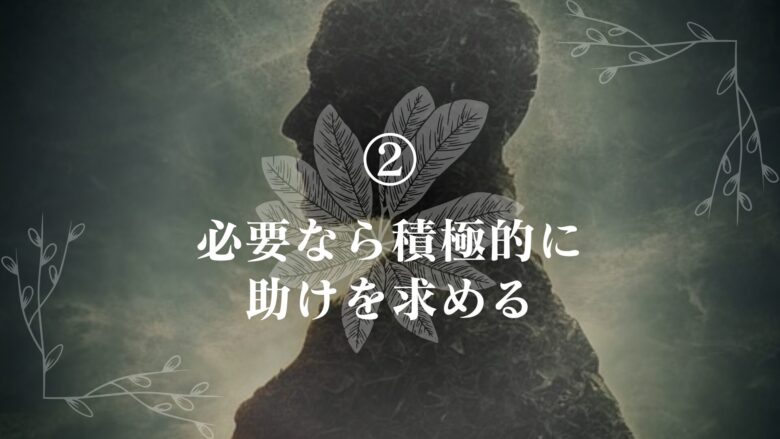
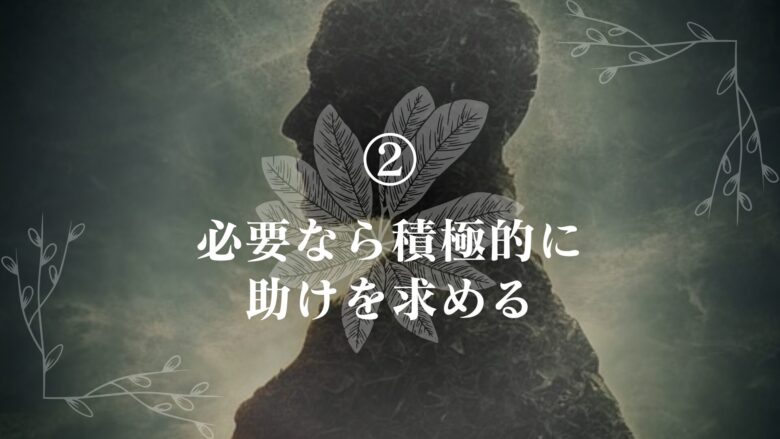
真の弱者に落ちないために大事なことの1つ目は、「必要なら積極的に助けを求める」です。
前述したように、助けを求める事がない限り、周囲の人も社会も「助けてもいいのだろうか?どんな支援が必要なんだろうか?」と思うので、正直困っていそうだと思ってもなかなか手が出せません。



たしかに、助けを求めない事には、、、だよね。
そのため、真の弱者に落ちないためには、「自分は~にこまっています!助けて下さい!」みたいにきちんと他人に助けを求められるようになっていく必要がありますね。ここに関しては、マストですね。
相手に助けを求める際は、後述するように自分の努力等をしっかりと示すことが重要です。助けを求めるときに、求め方もきちんと考えると効率的ですね。なお、マインドフルネス瞑想等各種ストレス対策をお困っておくと、冷静かつ適切に支援を求めやすくなると思います。マインドフルネス瞑想については、以下の記事を見てみて下さいね。
真の弱者に落ちないためには必要なら積極的に助けを求めよう
感謝と努力をきちんと示す
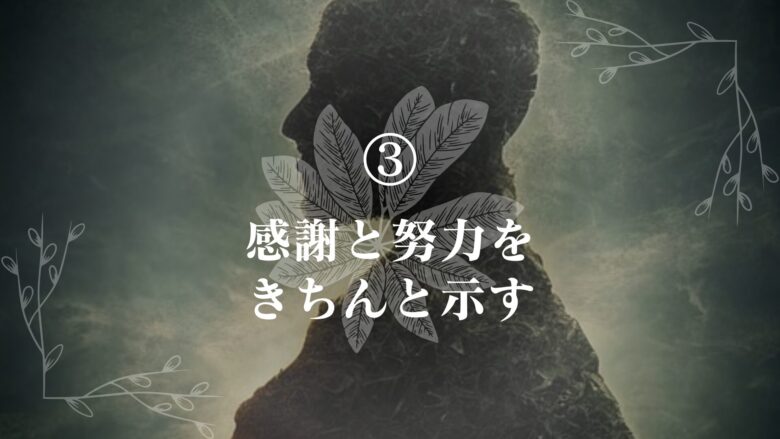
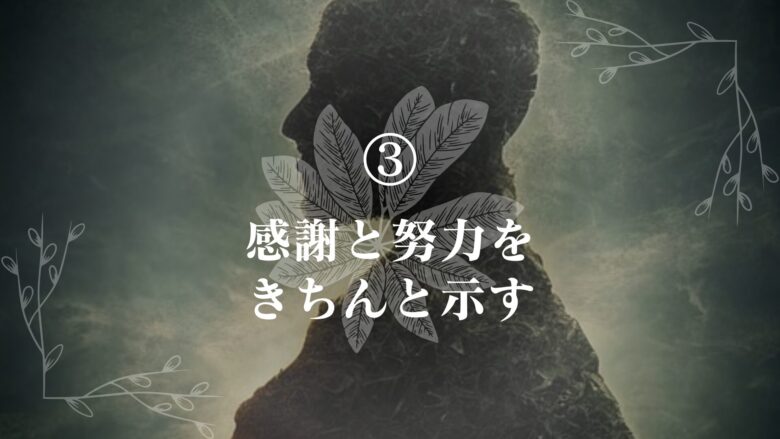
真の弱者に落ちないために大事なことの3つ目は、「感謝と努力をきちんと示す」です。
相手の支援したいという気持ちを引き出すためには、感謝と努力を示すのが何をおいても重要ですね。な実際、人はまず意図=温かさを、その次に実行力=有能さを見るとされています。どちらか一方だけだと「怠けている」「寄生的」とみなされるリスクがあるので、両方の印象を作ることが重要というわけです。



ふむ、確かに努力と感謝は大事やなあ。
例えば、言い方などについては、それぞれ以下の様に気を付けていくといいと思います。
- 言い方・態度:頼むときは短く具体的に(“今、○○のために○○が必要です”)+相手の好意に対する事前の感謝表現
- 自助の見せ方:自分が既に取っている努力(計画、)を簡潔に示すことで“control(原因が自分の無策ではない)”を示す。
- 有能さのシグナルとして、簡単な自助プランや期限を示す(例:「来月までには~をする」など)。これは受け手が「支援が効果的に使われるだろう」と判断しやすくなる。
真の弱者に落ちないためには感謝と努力をきちんと示そう
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」に関するFAQ
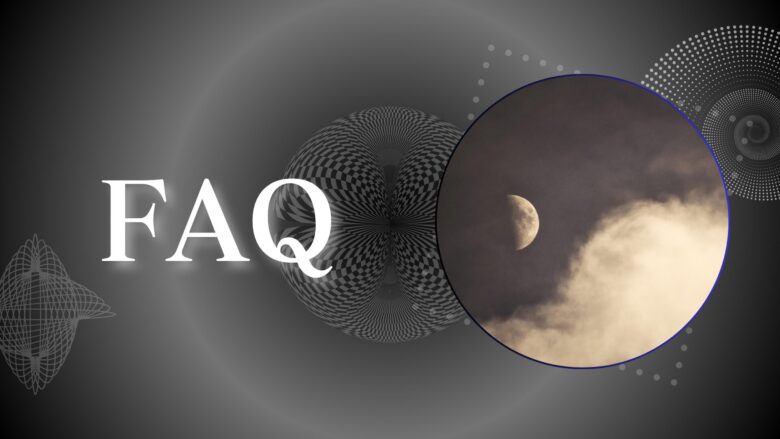
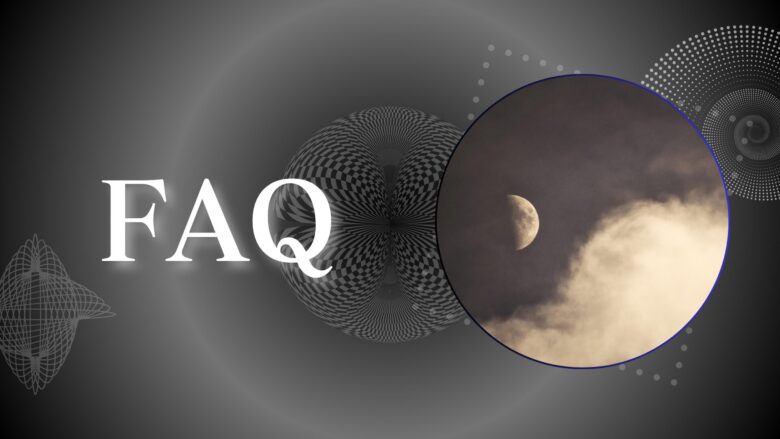



まだ、気になる事があるんよねえ。



んじゃ、最後に疑問に答えていこうかのお。
最後に、「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」に関する疑問について、回答していきたいと思います。
FAQ①:弱者に対して「努力を示せ」は酷では?
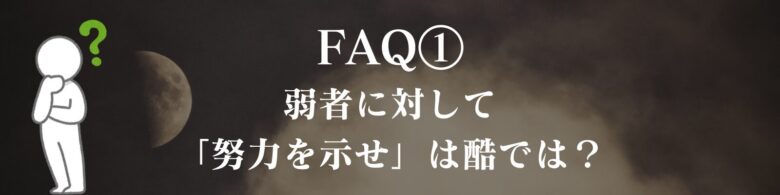
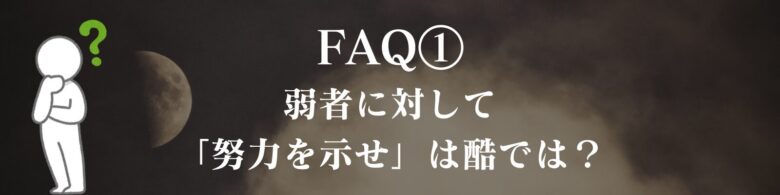
努力といっても、「まずはできる事から」で十分だと思います。ただ、「努力のフリ」ではなく「小さな一歩を共有すること」が非常に重要です。
具体的に言うと、相手にアドバイスをもらってからそのの提案を「とりあえず実践してその結果を共有する」という形をとると、非常に効果的でしょう。素直に実践し結果を共有してくれる人には、誰しも助けてあげたいという気持ちになりますからね。
FAQ②:助けを求めるのが恥ずかしい場合は?
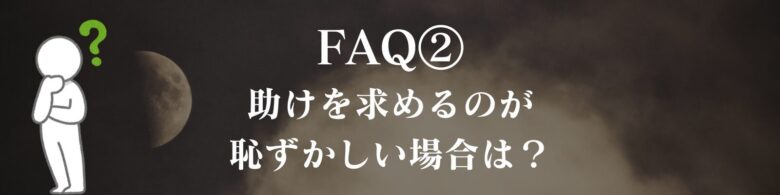
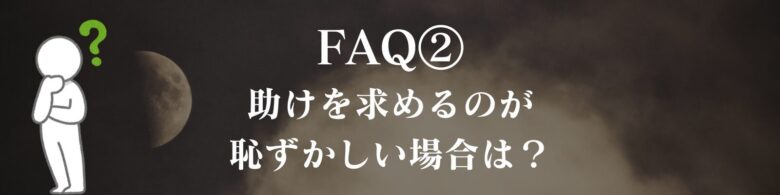
たしかに、他人に助けを求めるのは人によっては、かなりの心労です。ただ、助けを求めない事には、周りの人も助けていいのかわからないので、何もできません。そのため、日頃から少しづつでも相手に弱みを自己開示しつつ、助けてもらえる関係性を作っていくのが大事です。
例えば、「昨日は言えなかったけど、実は〇〇で困っています」などと前置きを入れて、あとでもいいのできちんと助けを求めるようにした方がいいです。
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」には一理ある!万が一にそなえ対策自体はしておこう!
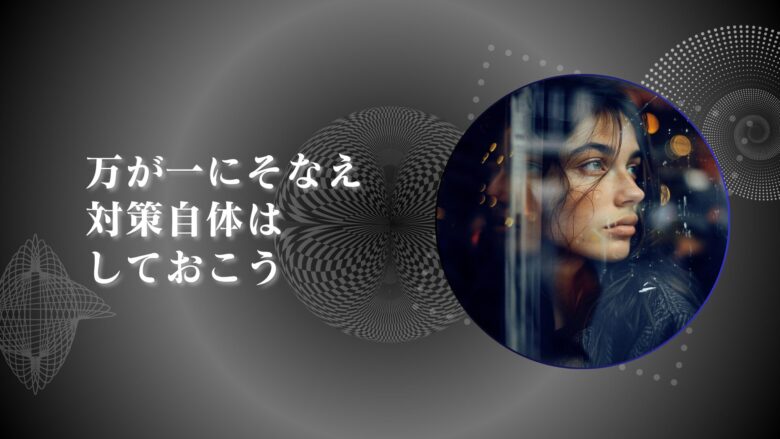
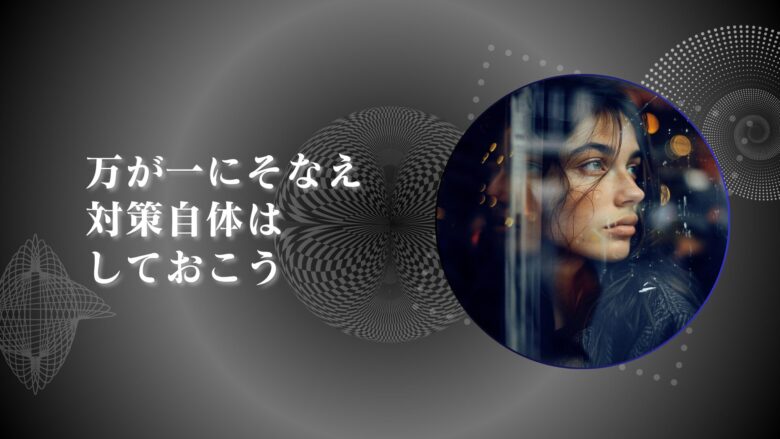
「真の弱者は助けたくなるような姿をしていない」という言葉には、一理あります。この言葉では「姿」という言葉が使われていますが、ここでいう「姿」とは純粋な造形のことではなく醜悪な内面とそれが反映された雰囲気や行動のことです。
結局、この言葉は弱者ほど内面に難があるという話といえます。誰でもいつ弱者に落ちるかなんてわからないので、そうした万が一のために誰しも内面はよくしておくに限りますね。内面はいきなり良くしようとしても、土台無理ですからね。



結局、きれいごと抜きで、内面の問題なんよな。
ちなみに、公式ラインでは「もっと自分を理解したい」、「人との関わりをうまく築きたい」、そんなあなたのために不定期で心理学的ヒントを発信しています。ただ今LINE登録者限定で、心の軸を取り戻すための限定記事や表ではあまり言えない実践知ベースの限定記事のパスワードをプレゼント中です。
あなたの生き方を少しずつ再構成していくヒントをお届けします。心の成長を始める第一歩として、今すぐ登録を!