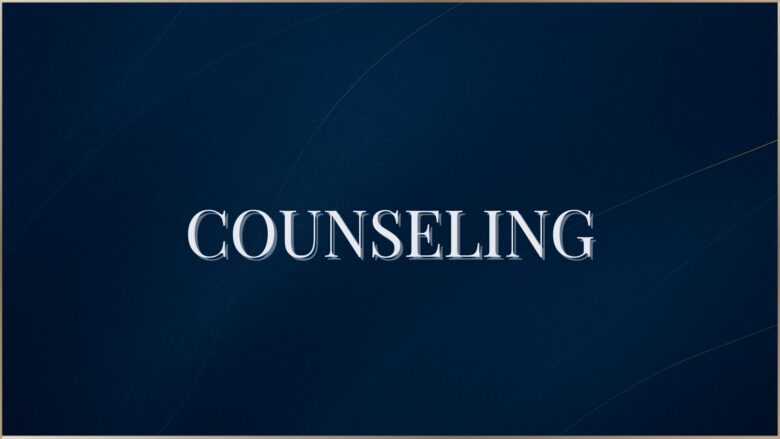おにぎり
おにぎり自分が良ければ他人はどうでもいい人は、どんな神経してるん?



まあねえ、以下の4つが原因でそうなっていると思うんよね。
世の中には一定数、「自分がよければ他人はどうでもいい」という自己中の極みのような人がいるものです。こうした人にかかわったことがある方はわかると思いますが、「よくもまあ、ここまで自分のことだけ優先しようとできるな、、」と乾いた笑いが出てきてしまうほど呆れます。
そんな感じですが、自分が良ければ他人はどうでもいいという人は、なぜこんな正確になってしまっているのか、気になりますよね?結論から言うと、自分が良ければ他人はどうでもいいという人がそうなってしまっている心理的原因としては、以下の様なものが考えられます。
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因
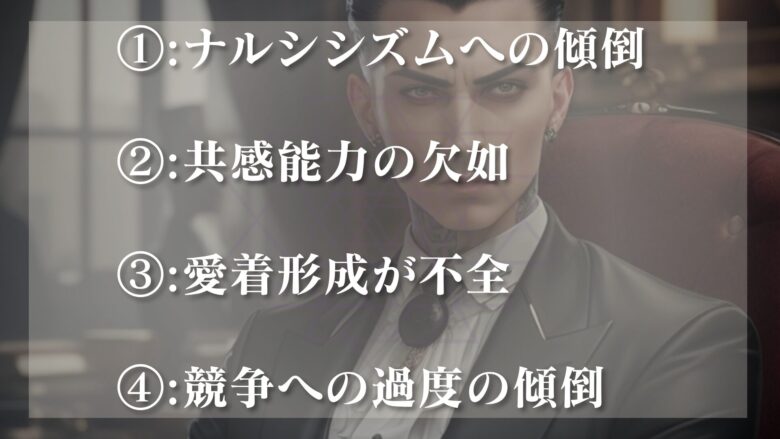
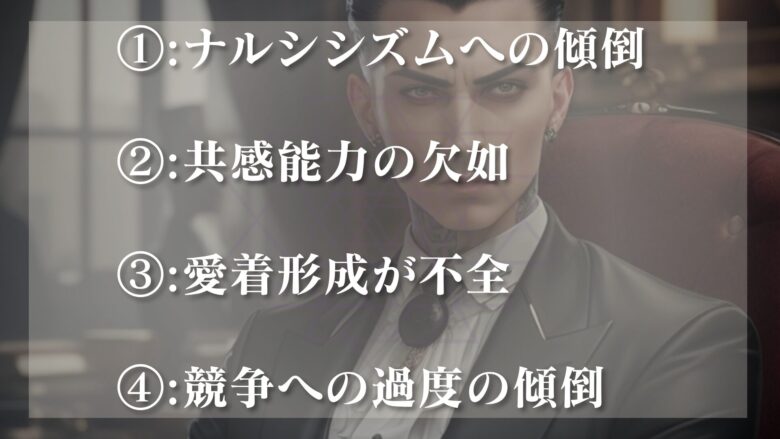



最も一般的なのは、共感力の欠如やね。
こうした人とは距離を置くのが一番ですが、知らないうちに自分もなっているかもしれません。自分のことは意外と、正しくわかっていなかったりするものですからね。そのため、本記事でふれているような方法と使って、一度深く内省し自分の認知の再構成を試みるのもいいと思います。
ちなみに、公式ラインでは「人との関わりをうまく築きたい」、「誰かの期待じゃなく自分の意志で生きたい」、そんなあなたのために不定期で心理学的ヒントを発信しています。ただ今LINE登録者限定で、心の軸を取り戻すための限定記事や表ではあまり言えない実践知ベースの限定記事のパスワードをプレゼント中。
あなたの生き方を少しずつ再構成していくヒントをお届けします。今すぐ登録して、あなたのペースで心を整えていきましょう!
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因
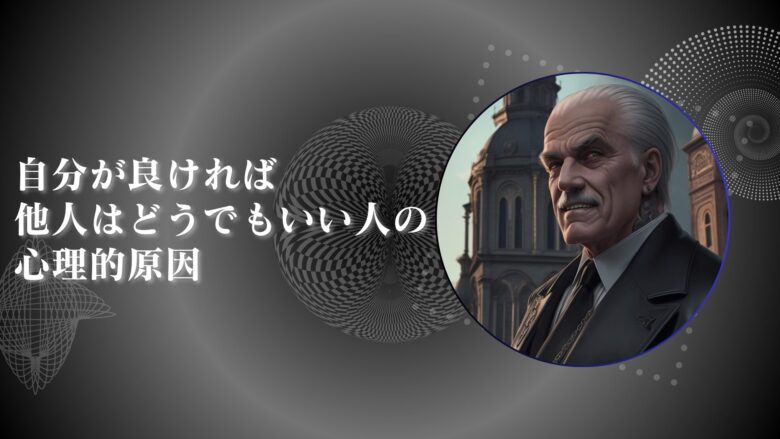
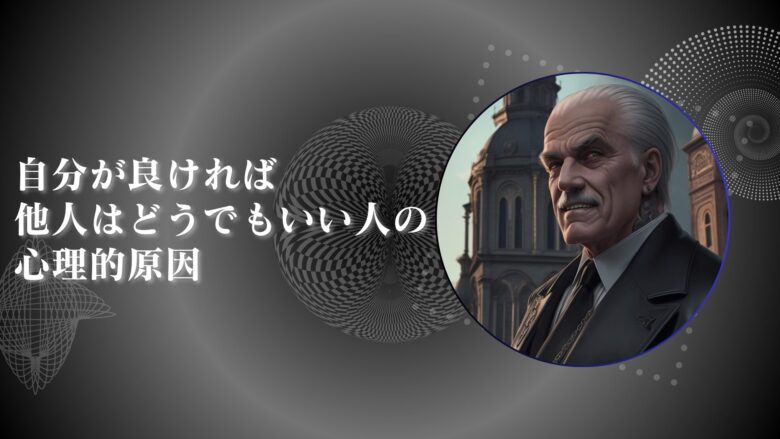



自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因とは?



以下の3つやなあ。
まずは、自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因について、見ていきたいと思います。自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因は、以下の通りです。
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因
- 心理的原因①:ナルシシズムへの傾倒
- 心理的原因②:共感能力の欠如
- 心理的原因③:愛着形成が不全
- 心理的原因④:競争への過度の傾倒



それぞれ、詳しく見ていこう!
心理的原因①:ナルシシズムへの傾倒
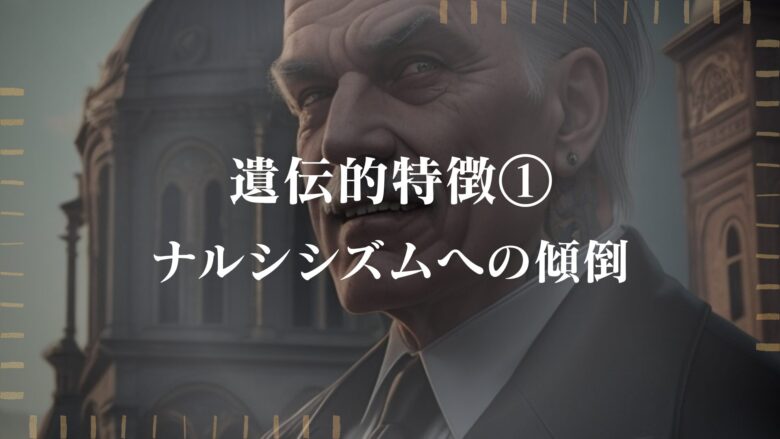
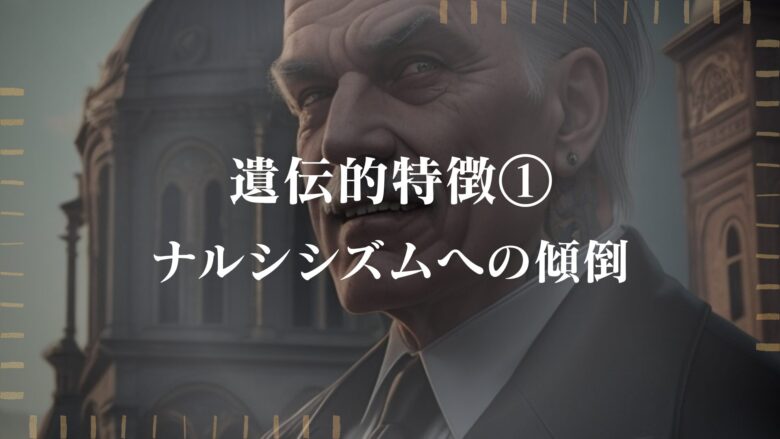
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因の1つ目は、「ナルシシズムへの傾倒」です。
「自分さえよければいい」という態度は、特に極端な自己中心性は臨床的にはナルシシズム・自己中心性パーソナリティ障害(NPD)に相当する場合があります。主な特徴は自己の誇大表示、賞賛欲求、共感の欠如などです。



ナルシストは、確かに自分のことしか考えてなさそう。
実際、ナルシシズムの一部の側面(例:対人敏感性の欠如、優越感を保つための操作的行動)が他者軽視に結びつくとされていますので、ナルシストの度合いが強いと長期的には人間関係が破綻するリスクが高まるでしょう。
心理的原因②:共感能力の欠如
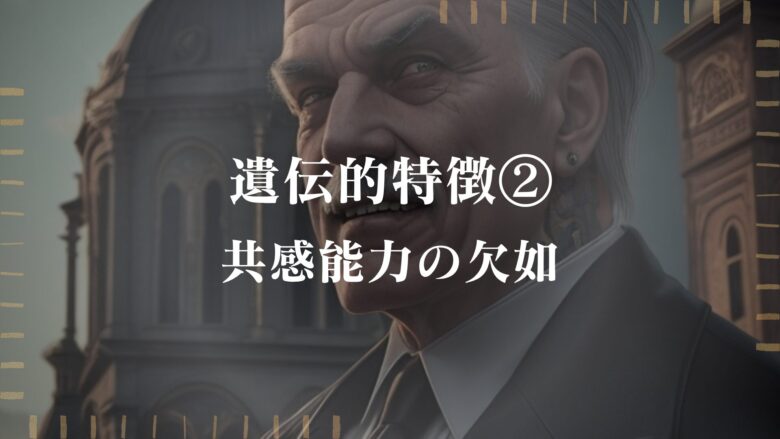
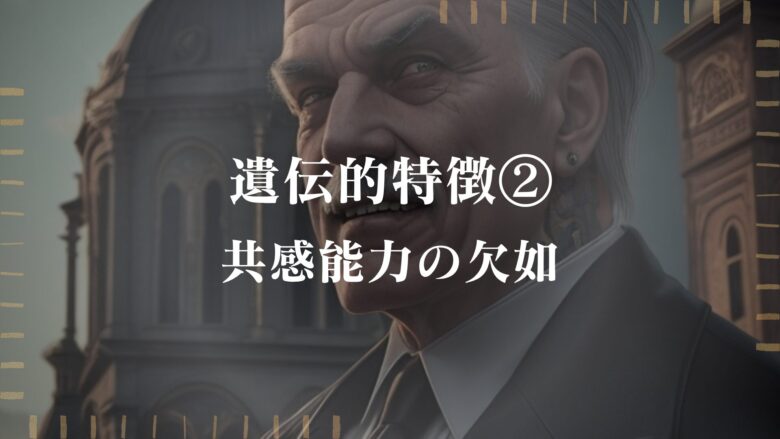
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因の2つ目は、「共感能力の欠如」です。
他者を気にしない態度は、えてして「他者の感情を理解し反応する能力(=共感)」の弱さと結びついています。実際、メタ分析を用いた研究などでは、自己中心的。反社会的傾向と共感の低さが相関することを示されていますよね。



特に一部のナルシシズム特徴は他者の視点を取る能力(認知的共感)や感情的反応(情動的共感)を阻害するとされていますね。
参考:The relationship between narcissism and empathy: A meta-analytic review
また、自己中心性といえば、良心のない性格類型として知られるサイコパシーも無視できません。そこに、目的達成のために手段を問わないマキャベリズムや他人の苦痛を快楽と感じるサディズムが加わると、自己中心性はさらに強化されるでしょう。
なお、ナルシシズム、サイコパシー、マキャベリズム、サディズムの4つの邪悪な性格類型をまとめて、ダークテトラッドと称されます。ダークテトラッドについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を見てみて下さいね。
心理的原因③:愛着形成が不全
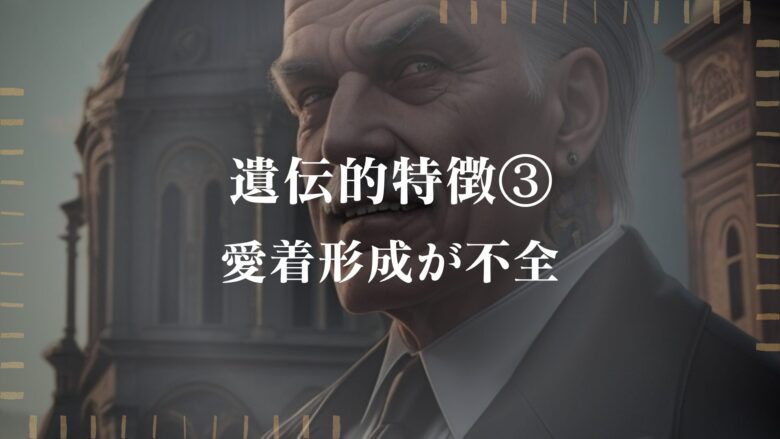
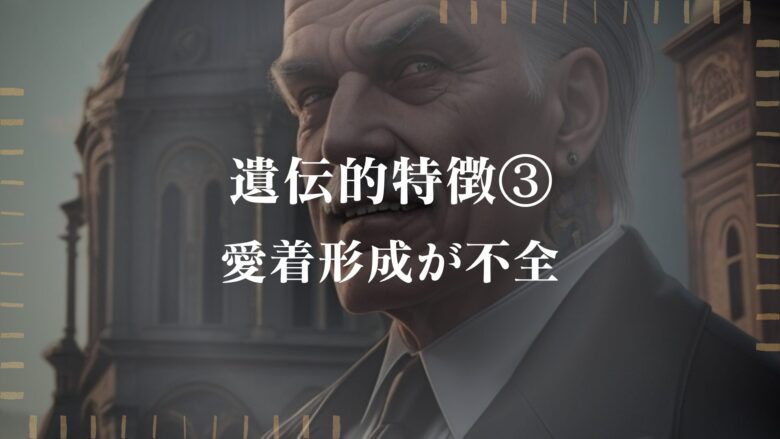
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因の3つ目は、「愛着形成が不全」です。
幼少期の養育経験で形成される愛着スタイルが不安定だと、自己中心的な対人戦略が生じやすいことが示唆されています。



やっぱ、幼少期の愛着形成って大事なのね。
例えば、愛着スタイルの不安型や回避型は他者への警戒、または他者への依存と同時に自己防衛的な自己優先行動を誘発するとされていますね。
なお一言付けくわえておくと、こうした幼少期の愛着形成が不全であっても、後天的に健全的とされる安定型に修正することは可能です。
心理的原因④:競争への過度の傾倒
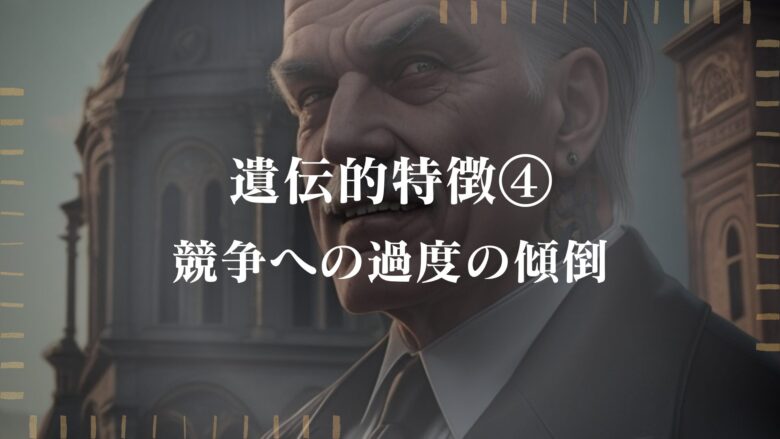
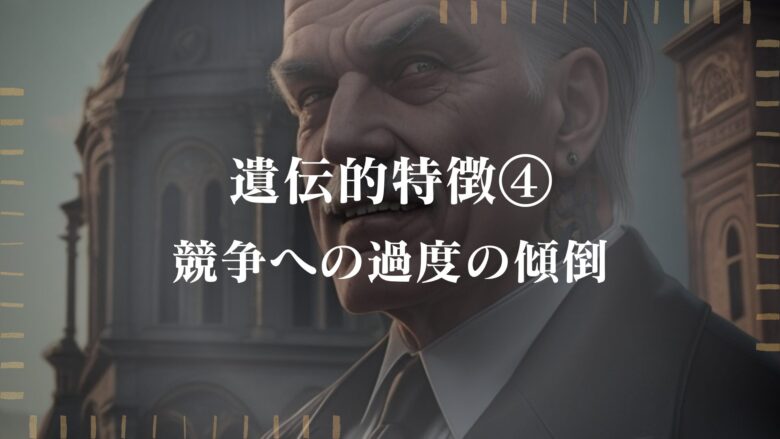
自分が良ければ他人はどうでもいい人の心理的原因の4つ目は、「競争への過度の傾倒」です。
現代社会の一部環境(高度な競争場面や個人主義的文化など)は、「勝ち残るために自己優先が必要」と学習させ、他者配慮を犠牲にして効率や成果を優先する行動を強化してしまいます。



確かになあ、、、競争は人を悪い意味で変えるよね。
実際、以下の研究では、社会的地位や競争的価値観が利己的行動を促進することが確認されていますね。
参考:Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review
競争に傾倒しすぎるて利己的行動を重視する傾向が習慣化すると、他者を軽視する姿勢が定着してしまいけねませんから、注意が必要ですね。
自分さえよければいい人のたどる2つの凄惨な末路





自分さえよければいい人って、ロクな事になりそうにないよね。



うむ、大概ろくなことにならんね。
自分がよければ他人はどうでもいいというスタンスの人は、かなりの高確率でロクな末路をたどりません。そこで、つぎは、自分さえよければいい人がたどる凄惨な末路について、見ていきたいと思います。
自分さえよければいい人のたどる凄惨な末路は、以下の通りです。
自分さえよければいい人のたどる凄惨な末路
- 末路①:社会的に孤立する
- 末路②:精神的に追い込まれる



それぞれ、詳しく見ていこう!
末路①:社会的に孤立する


自分さえよければいい人のたどる凄惨な末路の1つ目は、「社会的に孤立する」というものです。
利己的な行動は短期的には成功をもたらすことがあっても、長期的には人間関係が失われるせいで社会的に孤立してしまうことが少なくありまりません。



だよね、あきらかに利己的な人となんて関わりたくないもんね。
ちなみに、社会関係の質は健康・寿命にも、強く影響します。メタ解析による研究では、「社会的つながりの弱さは死亡リスクの上昇と関連する」と報告されており、孤立や孤独は心身のリスクを高めるそうです。
参考:Social Relationships and Mortality Risk: A Meta-analytic Review
あんまり「自分がよければ他人はどうでもいい」といったスタンスでいると、早死にするかもしれませんね。
末路③:精神的に追い込まれる
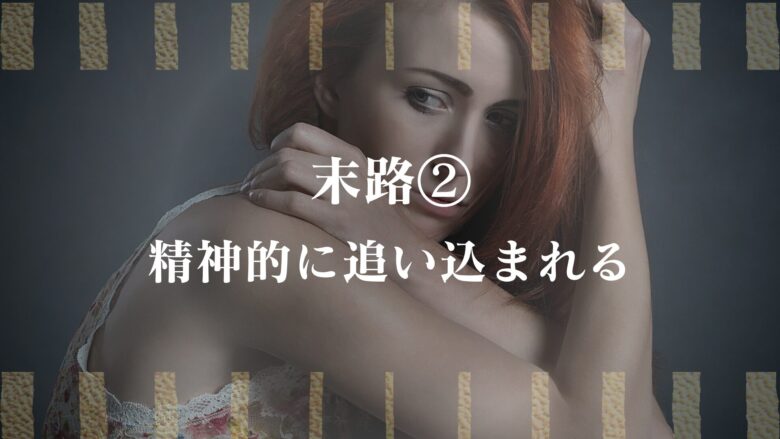
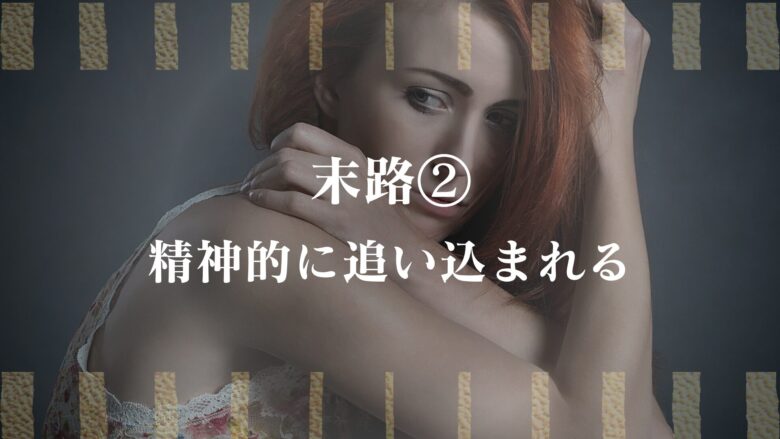
自分さえよければいい人のたどる凄惨な末路の2つ目は、「精神的に追い込まれる」というものです。
一見「自分がよければ他人はどうでもいい」といった自己中心的な姿勢は精神的に強靭に感じられますが、サイコパシーはともかく他の場合は、意外とそんな事はありません。特にナルシストに関しては、かなり弱いですね。



実際、以下の研究では「脆弱型ナルシシズムは孤独や抑うつと関連する」ことを示しており、表面上の自信が内面の不安を覆い隠す場合があると指摘されています。
多くの人にとって「自分がよければ他人はどうでもいい」といったスタンスで生き続けると、前述のように社会的に孤立したり、そうでなくても自分の心の中に強力な認知の歪みを抱え続けるために、最終的には病んでしまう可能性が高そうです。
自分が良ければ他人はどうでもいい人との一番効果的な接し方





自己中野郎には,どうやって接していったらいいん?



境界をはっきりさせることが、一番重要やな!
「自分がよければ他人はどうでもいい」という自己中人間に対しては、境界をはっきりさせる、つまり「相手の要求や操作から自分を守るために明確な線を引き、その線を一貫して守ること」が非常に重要になります。境界を引かなければ、どんどん相手の思惑どおりに搾取されてしまいます。
実際、自己中心的・操作的傾向を持つ人に対して境界設定を実施すると、相手の攻撃的行動や操作行動が減少することが報告されていますし、境界を明確に持つ人は燃え尽き症候群や心理的ストレスのリスクが有意に低いとされていますね。
参考
Narcissism and observed communication in couples
Sense and Sensitivity: A Response to the Commentary by Keller et al. (2018)
境界を引く際の詳しい実践手順は、以下の通りです。
境界を引く際の実践手順
「どんな言動を受け入れられないか」「どんな行動なら距離を置くか」を具体的に紙に書く。
例:嘘・約束破り・人格否定 → 関係を縮小する。一方的な要求が続く → 返答の頻度を減らす。
相手を責めるのではなく、「自分がどう感じるか」に焦点を当てる。
ダメな例:「あなたが間違っている!」→ ✕
良い例:「私はこの話し方をされると、距離を置きたく感じます」→ ○
これは非暴力コミュニケーション(NVC)理論(Rosenberg, 2003)に基づく方法で、攻撃を受けにくく、境界を維持しやすいとされている。
一度決めた境界は、相手の機嫌や罪悪感で揺らがせないようにする。
仮に相手からの圧力によって 境界を揺らすと、自己中心的な人は「押せば曲がる」と学習し、より強く侵入してくる。
メッセージの返信頻度を減らす、対面時間を短くする、共通プロジェクトから段階的に離れるといった事が有効である。
これはグレーロック戦略といわれ、臨床でもよく推奨されている。
参考:Should I Stay or Should I Go: Surviving A Relationship with a Narcissist
自己中心的な人は、相手の感情反応(怒り・罪悪感・同情)を利用して操作する傾向があり、この感情操作に押し負けた人は得てして搾取されがちです。
こうした感情操作に負けないためには、後述するようなマインドフルネス瞑想の習慣化によって、「感情に自動反応せず観察する能力」を強化していく必要があります。感情に流されなくなれば、利己的な人間に利用されにくくなりますね、間違いなく。



ふむ、マインドフルネス瞑想やってみるか。
また自己中心的な相手に対処していると精神的に疲弊していくので、第三者的視点を取り入れるために信頼できる友人や心理カウンセラー・コミュニティなどに相談するのがベストとなりますね。
そして、さらにさらに、精神の防御力を高めていきたいのであれば、自分の大事にしたいものを見出していくのが重要になります。自分軸の確立について、気になる方は以下の記事を参考にしてみて下さいね。
自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治す2つの方法





自己中心的な考えは、どう修正したらいいん?



ふむ、それなら以下の2つを試してみるとよいぞよ。
つぎは、自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治す方法について、見たい来たいと思います。自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治す方法は、以下の通りです。
自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治す2つの方法
- 方法①:マインドフルネス瞑想で共感力を向上させる
- 方法②:認知再構成法により自分の認知を見直す



それぞれ、詳しく見ていこう!
方法①:マインドフルネス瞑想で共感力を向上させる
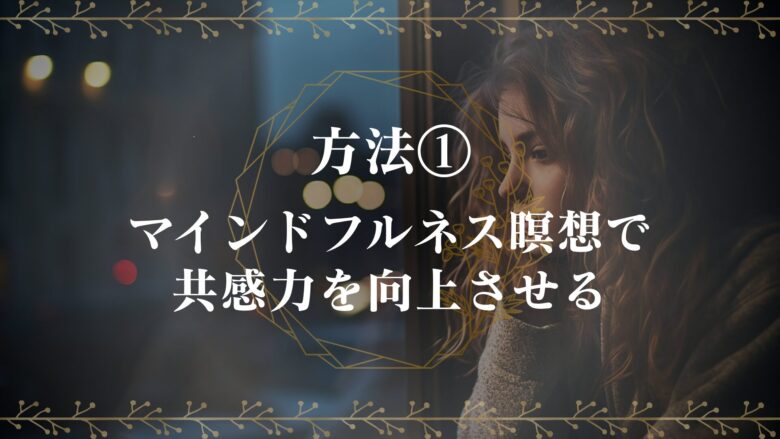
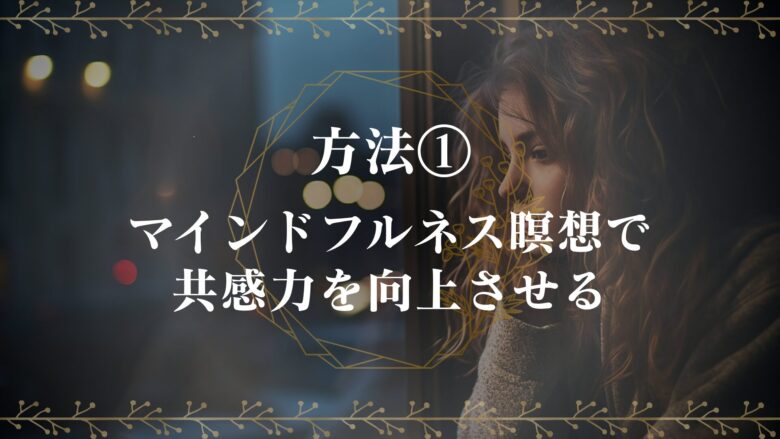
自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治す方法の1つ目は、「マインドフルネス瞑想で共感力を向上させる」です。
複数の系統的レビューやメタ解析の夜研究では、瞑想やマインドフルネスベースの介入(MBI)が「共感・思いやり・プロ社会的行動」を増やす有望な手法であることが示されています。
ただし研究間でエフェクトの大きさや持続性はばらつきがあり、実施内容(メディテーションの種類、期間、指導の質)によって結果が左右される



へえ、マインドフルネスってそんな効果あるのかあ。
マインドフルネス瞑想の詳しい実践手順の一例は、以下の通りです。
マインドフルネス瞑想の実践手順
静かな場所で、椅子や床に楽に座る(横になっても可)。スマートフォンや時計を近くに置き、5分タイマーをセット。
背筋を軽く伸ばし、肩をリラックス。目は軽く閉じるか、床の一点を見つめる。
息を鼻から吸い口から吐き、呼吸に意識を集中。吸う時に「お腹が膨らむ」、吐く時に「空気が抜ける」と感じる。思考が逸れたら、優しく呼吸に戻す(これが重要!)。
呼吸を続けながら、体の感覚(足、腹、胸など)を順に観察。緊張やざわつきがあれば、ただ「気づく」だけにとどめる。
タイマーが鳴ったら、ゆっくり目を開け、体の感覚や気持ちの変化を軽く振り返る。
自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治したいならマインドフルネス瞑想をしよう
方法②:認知再構成法により自分の認知を見直す
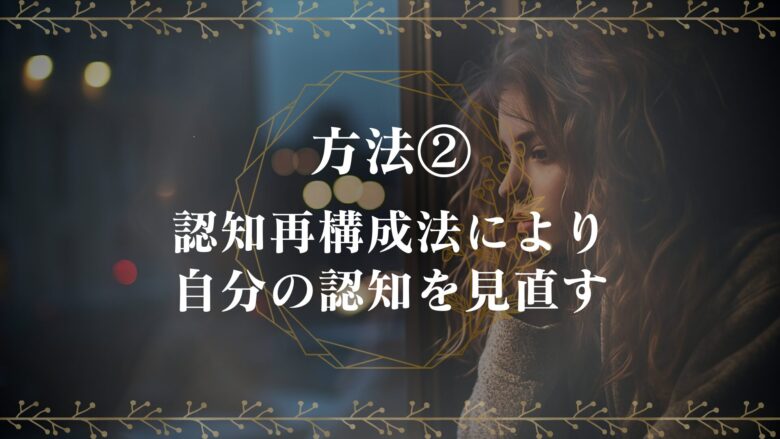
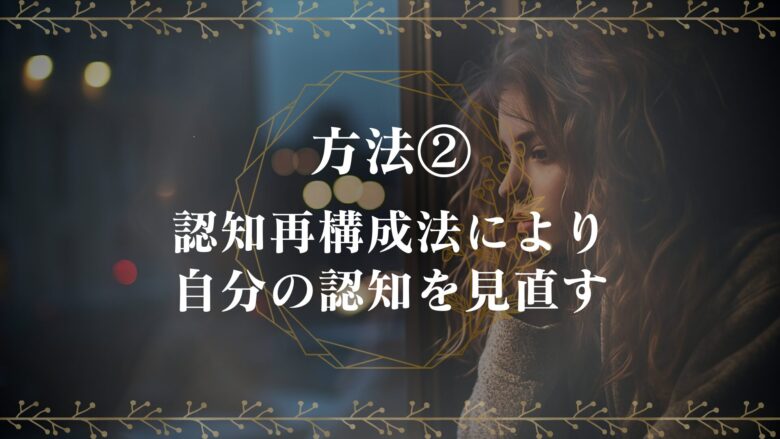
自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治す方法の2つ目は、「認知再構成法により自分の認知を見直す」です。
認知再構成は認知行動療法(CBT)の中核技法の1つであり、これは基本的に「自動思考の気づき→思考の検証→より現実的で機能的な解釈への書き換え」という流れで行われます。



ふむふむ、なるほど。
ちなみに、CBT自体は不安・抑うつなど多くの心理問題に対して有効性が示されており、認知再構成(認知的再評価)は情動調整の有効手段としてもエビデンスがあります。
参考:The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses
「自分がよければ他人はどうでもいい」という思考を変えるために、認知再構成法を適用する際の詳しい実践手順は、以下の通りです。
ノート1冊(またはスマホのメモアプリ)を用意する。毎日の思考記録を習慣化する(1日1回(問題が起きたときは随時)記録する)
例:「上司の前で自分の案が却下された」など、日時・場所・誰が関係したかを短く書く。
そのとき頭に浮かんだ最初の考えをそのまま書く(短いフレーズでOK)。
例:「どうせ俺はチームで嫌われてる」「人の気持ちなんてどうでもいい」など。
感情ラベル(例:怒り、恥、疎外感)を%で評価(0–100%)と身体反応(心拍、胃のむかつきなど)を記す。
例:孤立感 70%、胸の圧迫感など。
証拠(支持):その自動思考を支持する事実を箇条で書く(観察可能な出来事のみ)。
反証(反対の証拠):その思考に反する事実も必ず箇条で書く(過去の行動、他者の発言、第三者の視点など)。
例
支持:上司が私の案を否定した。
反証:上司はスケジュール理由で却下したと言った/以前は私の案でプロジェクト承認されたことがある。
証拠を踏まえて、元の極端な思考に対して現実的で機能的な再解釈を作成する。短く、行動につながる表現にするのがよい。
例:「今回はスケジュール上の問題で却下された。自分の案の価値はゼロではなく、説明やタイミングを改めれば通る可能性がある」など。
再構成した思考に基づいて1つ小さな行動を決める(情報収集、フィードバック依頼、謝意を示す等)。
例:「上司に『次回改善できる点を教えてください』と尋ねる(2日以内)」など。
行動後に結果を記録し、元の思考・感情がどれだけ変わったかを振り返る(感情%、得られた新しい証拠)。
このフィードバックが認知の修正を固定化する。
上記プロセスは1日〜週単位で反復すると効果的
なお、上記の方法と合わせて以下の様な問いかけを自分に行うのを習慣化すると、より一層自動思考がほぐされていき効果的ですね。
- 「その考えの根拠は何か?
- 「反対の可能性は?
- 「最悪/最良/最も現実的な結果は何か?
- この思考は行動を助けるか妨げるか?
自分が良ければ他人はどうでもいいという思考を治したいなら認知再構成法を実践しよう
自分が良ければ他人はどうでもいいという考えに対して持ちがちな疑問





まだ、気になる事があるんよね。



んじゃ、最後に疑問にこたえていこうかの。
最後に、自分が良ければ他人はどうでもいいという考えに対して持ちがちな疑問について、回答していこうと思います。
疑問①:自己中心的な人は本当に幸せになれない?
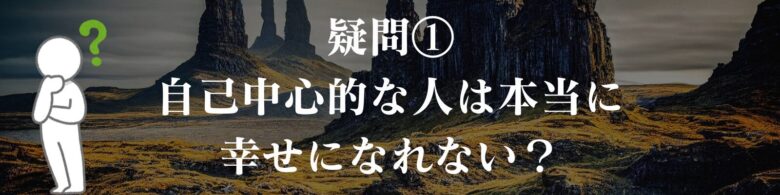
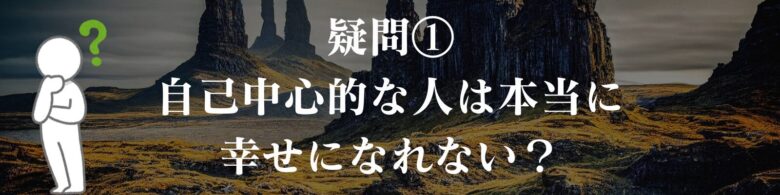
全てについて絶対はありませんが、自己中心的な人は短期的な満足を得る場合があるものの、長期的な幸福度は低い傾向にあります。
実際、以下のポジティブ心理学に関する研究では、幸福は「他者との良好な関係」「社会への貢献」に強く依存するとされています。
参考:Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being.
中には、自分のことしか考えずに徹底的に利己的に生きた方が満足いく人もいるでしょうが(サイコパス等)、それはかなりの少数派ですから、基本的にはお勧めできませんね。
疑問②:自己中心的な思考は生まれつきの性格?
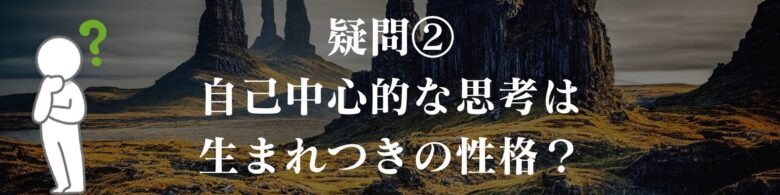
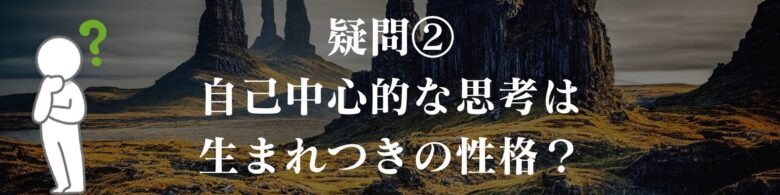
自己中心的な思考は、遺伝的要因もありますが、環境や学習に非常に大きな影響を受けて形成されます。ちなみに、バンデューラの社会的学習理論によれば、自己中心的な行動は、報酬(例: 注目や成功)を得ることで強化される場合があるとされていますね。
参考:Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
性格形成において、生来の遺伝要因はもちろん重要ですが、環境要因の影響も無視はできません。
疑問③: 自己中心的な人とどうやって付き合えばいい?
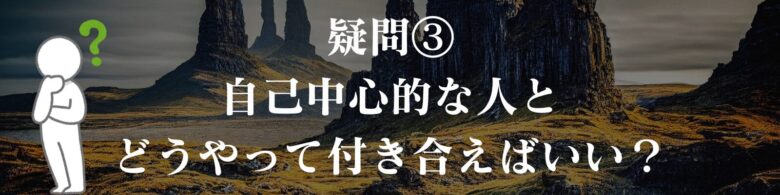
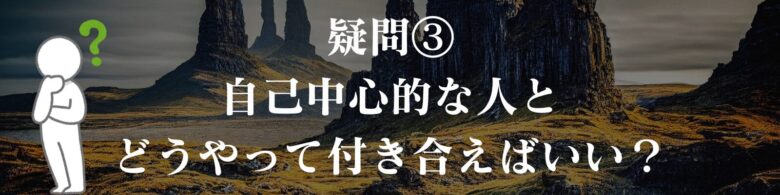
自己中心的な人との関係では、明確な境界設定が有効です。例えば、以下の研究では、自己主張(例: 「私はこう感じる」)や明確なコミュニケーションが、相手の利己的な行動を抑制し、健全な関係を維持する助けになるとされています。
参考:High self-esteem buffers negative feedback: Once more with feeling.
具体的には、相手の行動に振り回されないよう、自分のニーズを穏やかに伝え、必要に応じて距離を取ることが重要です。こうしたコミュニケーションについては、相手に配慮をしつつ自己主張するアサーションスキルを身に着ける事が大事になります。
アサーションについて気になる方は、以下の記事を見てみてくださいね。
参考:アサーショントレーニング
「自分が良ければ他人はどうでもいい」ではいい末路にならない!他者との協調もきちんと意識した方が得!


「自分が良ければ他人はどうでもいい」という思考では、短期的に得をしても最終的にはロクな結末にはならないのがほとんどです。そのため、自己利益だけでなく他者との協調もきちんと意識した行動をした方が、いろいろと得といえます。真に打算的に動きたいなら、他人のことも考えましょう。それが正解です。
そして、善良な人はこうした我利我利亡者とはなるべく距離を置くのが大事になります。搾取リスクが高いですからね。ただ、誰にでもこうした自己中な面はあるものですから、前述の方法などを使って自己中度を下げておくのが賢明でもあります。それでこそ、人といい関係を築いていけるでしょう。



常に、内省し自戒していこうぞ!
ちなみに、公式ラインでは「もっと自分を理解したい」、「人との関わりをうまく築きたい」、そんなあなたのために不定期で心理学的ヒントを発信しています。ただ今LINE登録者限定で、心の軸を取り戻すための限定記事や表ではあまり言えない実践知ベースの限定記事のパスワードをプレゼント中です。
あなたの生き方を少しずつ再構成していくヒントをお届けします。心の成長を始める第一歩として、今すぐ登録を!