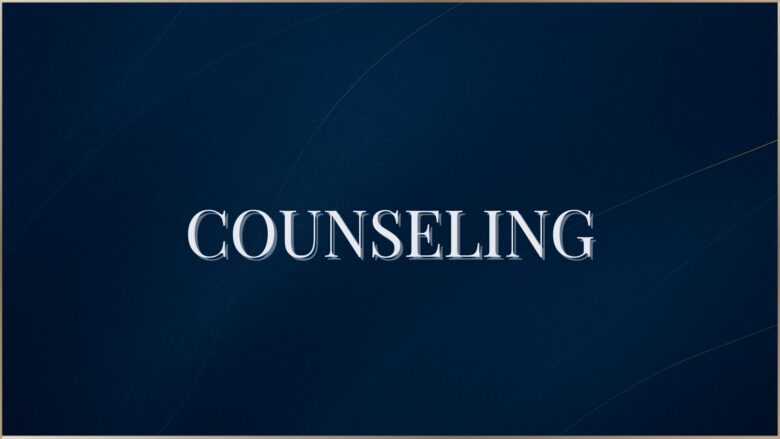おにぎり
おにぎり「わかる」が口癖 の人の心理が、気になるんよね。



「わかる」が口癖の人の心理は、主に以下の3つやね。
世の中には何を言っても「わかる」とばかり言う人がいますが、こうした人たちに「いや、本当にわかっているのか?」なんて思ってしまうこともしばしばでしょう。特に男性からしたら、この口癖には疑問しかないと思います。
そんな感じですから、わかるが口癖の人の心理について、気になりますよね?結論から言うと、わかるが口癖の人の心理は、以下の通りです。
「わかる」が口癖 の人の心理
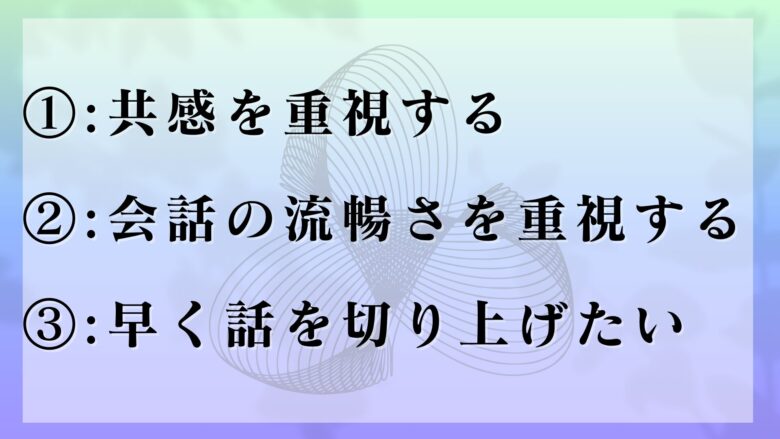
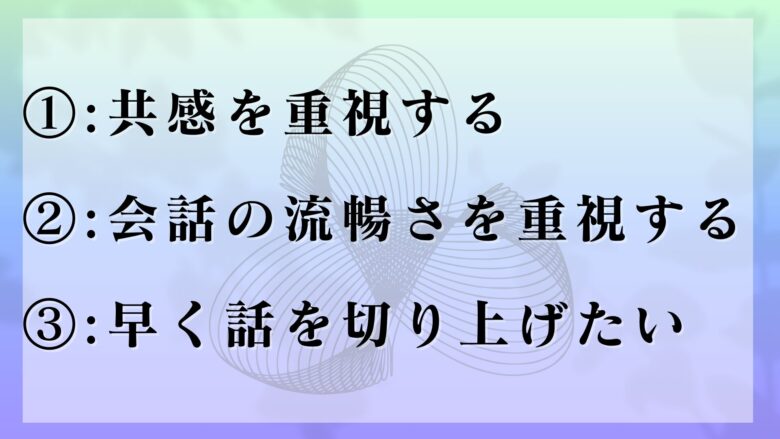



共感を重視しているのが、ほとんどやね。
「わかる」が口癖の人は、「共感を重視している」ことが多い印象です。中には、一々まともにリアクションを返すのがだるいので「わかる」といっている人もいますが、これは文脈依存なうえそこまで多数派ではないと思います。なので、「わかる」といわれても、変に勘繰る必要はないでしょう。
ちなみに、公式ラインでは「人との関わりをうまく築きたい」、「誰かの期待じゃなく自分の意志で生きたい」、そんなあなたのために不定期で心理学的ヒントを発信しています。ただ今LINE登録者限定で、心の軸を取り戻すための限定記事や表ではあまり言えない実践知ベースの限定記事のパスワードをプレゼント中。
あなたの生き方を少しずつ再構成していくヒントをお届けします。今すぐ登録して、あなたのペースで心を整えていきましょう!
「わかる」が口癖 の人の3つの心理





「わかる」が口癖 の人の心理って、どんなもんなん?



以下の3つやね。
まずは、わかるが口癖 の人の心理について、考えていきたいと思います。わかるが口癖 の人の心理については、以下の通りです。
「わかる」が口癖 の人の心理
- 心理①:共感を重視する
- 心理②:会話の流暢さを重視する
- 心理③:早く話を切り上げたい



それぞれ、詳しく見ていこう!
心理①:共感を重視する


わかるが口癖 の人の心理の1つ目は、「共感を重視する」というものです。
多くの場合、「わかる」は聞き手が、「話を受け止めている、または共感している」ことを示すための短い合図として作用します。



せやね、語彙的には共感の提示よね。
そのため、「わかる」という口癖の人は、相手に安心感を与えたい、または話を続けさせたいという親和的な意図を第一義として「わかる」と使っているのが通例です。
つまり、「わかる」という口癖を身に着けている方は、共感を大事にしたコミュニケーションをとろうとしていた結果、「わかる」が口癖になった可能性がありますね。そういえば、私も共感を重視していたら、一時期、開口一番「わかる」ばかり言うようになってしまっていましたねえ、、、。
心理②:会話の流暢さを重視する


わかるが口癖 の人の心理の2つ目は、「会話の流暢さを重視する」ということです。
会話のテンポや「場のなめらかさ」を保つために、無意識に短い相槌を多用する人がいます。実際、「わかる」は軽い共感や同意を意味する言葉ですから、言われた方としても会話が続けやすいですよね。



確かに否定とか変な返しされるよりは、ずっと続けやすいよね。
こうした場合、会話の円滑化のために「わかる」といっている場合、「わかる」といっている本人が話の内容をどのくらいわかっているかは定かではありません。いってみれば、反射的に言っているだけの可能性もありますからね。
とはいえ、適当に流す意図で「わかる」といっているとは限らないので、そこは決めつけない方がいいですね。
心理③:早く話を切り上げたい


わかるが口癖 の人の心理の3つ目は、「早く話を切り上げたい」ということです。
全体からすると、多数派とはいいがたいですが、一部「わかる」を多用して会話を区切り、深掘りを避けたり、話題を転換したりする人たちは実際にいます。大体の場合、「わかる」といっておけば、向うは共感か同意をもらったと思って、同じ話題を延々と深堀って来ない事も多いですからね。



まあ、確かにそうかもしれんね。
この心理は面倒な感情処理や対立を避けたいという回避的動機に基づいていますから、「わかる」を共感ではなく回避目的で使用していることがわかります。
ただ、誰しも「うわ、この話は面倒だぞ、、、」と思うと、「わかる」等と表面的な同意を取り繕って、当該話題におけるやり取りの終了を目論むのは自然な事です。そのため、普段は共感重視で会話する人であっても、話題によっては話題回避のために「わかる」を使うこともあるでしょう。
「わかる」という口癖の裏に隠された4つの闇
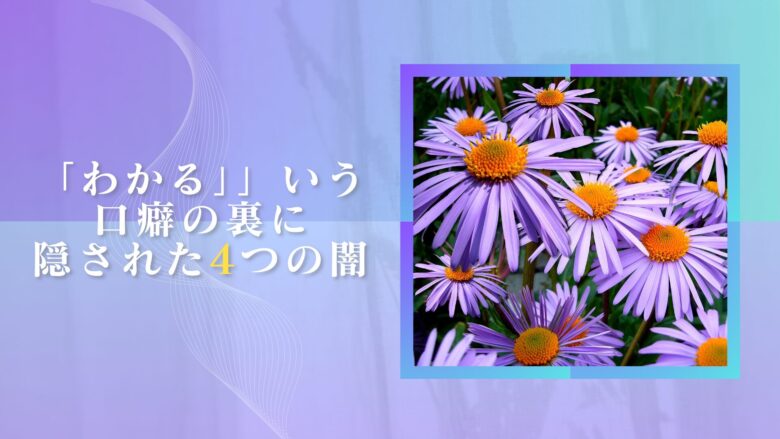
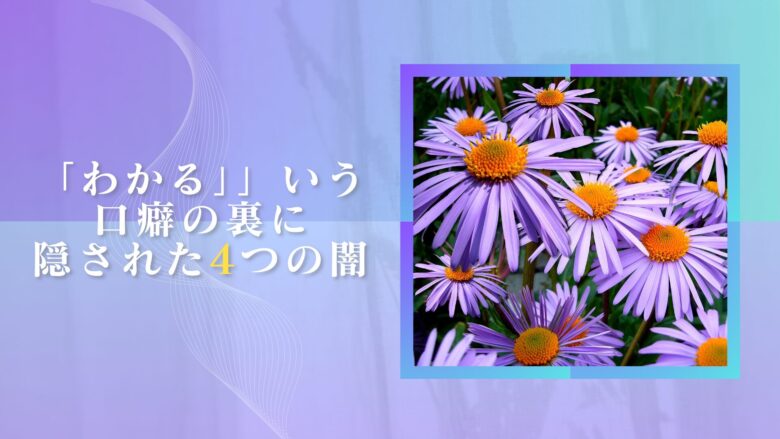



「わかる」という口癖の裏にある心理が、気になるねえ。



ふむ、では少し詳しく見ていこうかの。
つぎは、わかるという口癖の裏に隠された闇について、見ていきたいと思います。わかるという口癖の裏に隠された闇は、以下の通り。
わかるという口癖の裏に隠された闇
- 闇①:なんとか好感度を稼ぎたい
- 闇②:相手に気を遣うのがだるい
- 闇③:人の話を聞くより自分の話をしたい
- 闇④:責任をとりたくない



それぞれ、詳しく見ていこう!
闇①:なんとか好感度を稼ぎたい
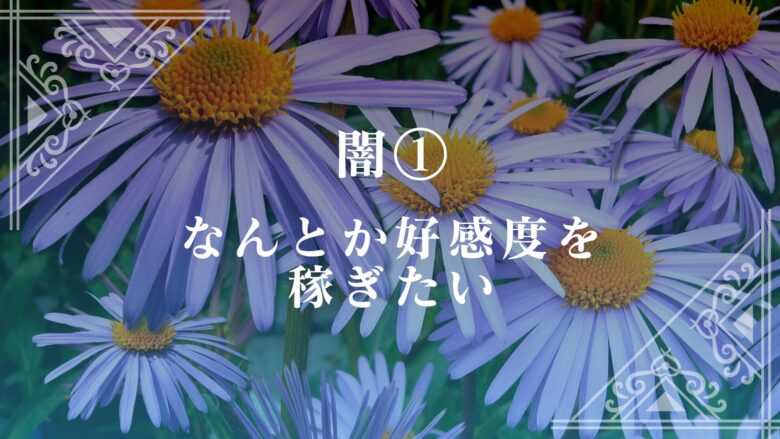
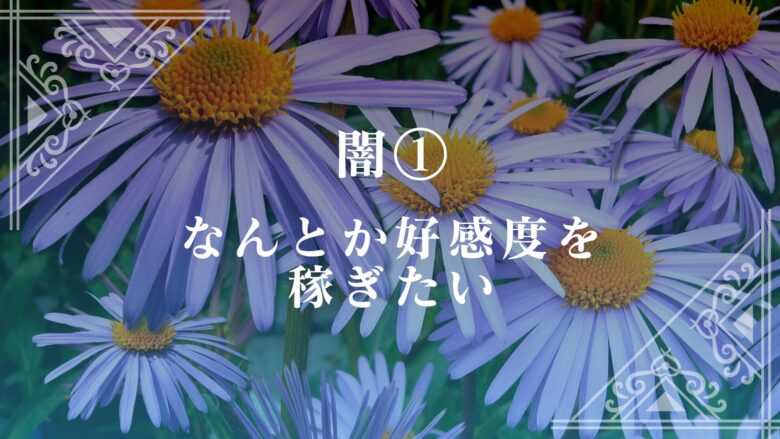
「わかる」という口癖の裏に隠された闇の1つ目は、「なんとか好感度を稼ぎたい」というものです。
「わかる」という口癖の裏には、「何とか相手に迎合して何とか好感度を稼ごう」といった意図が隠されていることもあるでしょう。



んー、ありえるなあ、これ。
ようは、言葉だけで同情を示し、実際の理解や行動が伴わないという「見せかけの共感」ですよね。このような「わかる」の使用方法はSNSや職場でも指摘される問題であり、受け手は次第に不信感を抱くこともしばしばです。
なお、「わかる」をこのような意図で使う人は、承認欲求もそうですが他者から嫌われることに対して非常に強い恐怖をもっていることが多い印象ですね。端的に言うと、八方美人といった感じです。
闇②:相手に気を遣うのがだるい
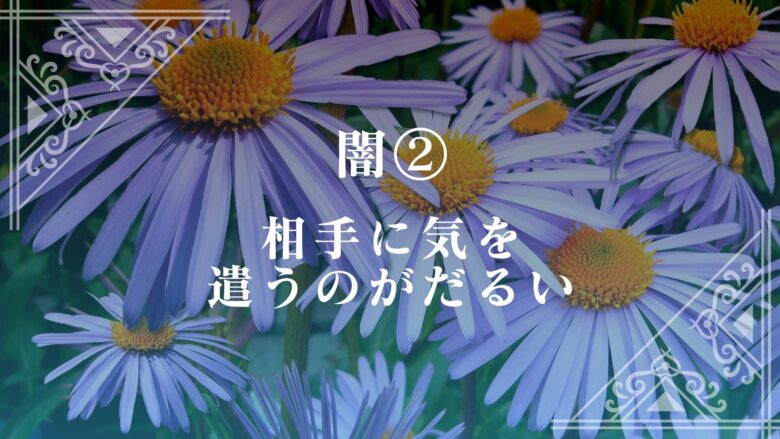
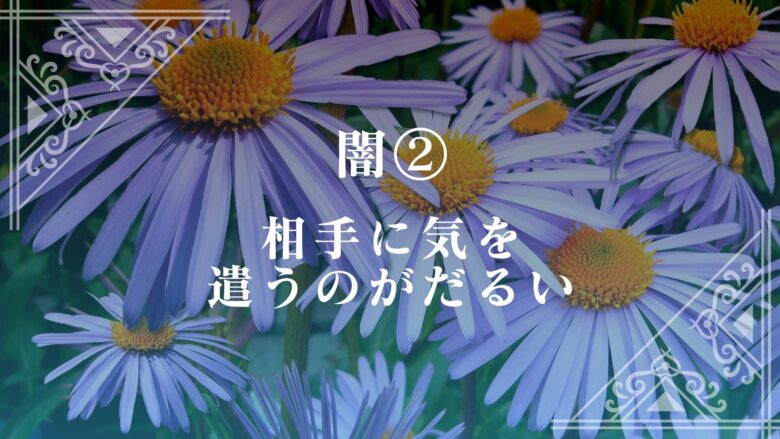
「わかる」という口癖の裏に隠された闇の2つ目は、「なんとか好感度を稼ぎたい」というものです。
「わかる」が口癖の人の中には、本当は相手の感情に向き合うのがしんどいために、短い「わかる」で済ませたいという意図が含まれていることがあります。



たしかに、こうした意図で言う人もいるよね。
特に、自分の得意でない話題やその日のメンタルの調子が悪く心理的負荷に耐えられない時などは、こうした意図で「わかる」を使いがちになる人が多いでしょう。実際、私にもこれは心当たりがありますしね、、、よくないんですが。
実際、うした意図で「わかる」を多用されると、受け取り側は自分の感情を軽んじられている様に感じて、ストレスになってしまいますからねえ。まあ、嫌われてもいいor距離をとりたい相手に対し手であれば、最適解なんでしょうが。
参考:Perceived Emotion Invalidation Predicts Daily Affect and Stressors
闇③:人の話を聞くより自分の話をしたい
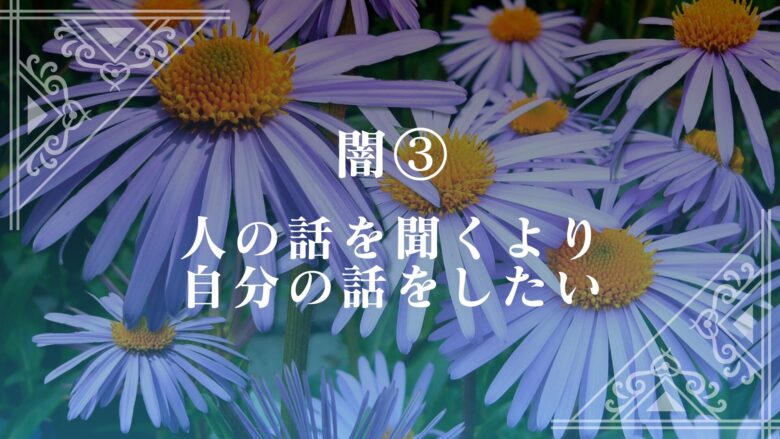
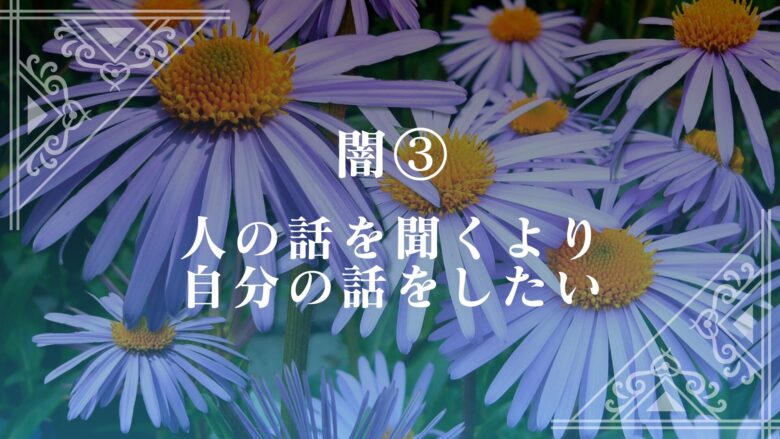
「わかる」という口癖の裏に隠された闇の3つ目は、「人の話を聞くより自分の話をしたい」というものです。
「わかる」が口癖になっている人の中には、「人の話を聞くよりも自分の話をしたいので、さっさと相手の話を切り上げたい」と考えている人がいたりします。



ああ、、いるかもしれんわ、こういう人。
実際、こうした意図で「わかる」を多用している人は知り合いにもいまして、大概その人はこちらの話に対して「わかる」といった後に、「てかさ」と即座に続けて自分の話題に持っていこうとするのが常です。別にこれが悪いとは言いませんが、、、人によっては「いつも自分の話ばかりしたがるな」と感じストレスでしょう。
やはり、人は自分の話を聞いてもらうことに快感を感じる生き物ですから、いつもいつも自分の話をスルーされるような相手と接するのはきついです。
闇④:責任をとりたくない


「わかる」という口癖の裏に隠された闇の4つ目は、「責任をとりたくない」というものです。
「わかる」が口癖になっている人の中には、自分の発言に対して責任を持ちたくないから、相手に対して「わかる」というのが口癖になっている人がいたりします。



相手に対して責任を持ちたくないからねえ、なるほど。
実際、相手の提示した話題に対して持論を展開したり、「いや、~」等と否定を使用するとなると、発言したからにはフォローやそれなりに納得のいく説明をしないといけない雰囲気が出てきてしまいますからね。
こうした事を考えると、「いちいち自分が発言の責任をかぶるのはダルいから適当に軽い同意や共感を示しておくか、、」と考える人がいても、おかしくはないでしょう。
「わかる」という口癖を直したいなら取るべき対策6ステップ
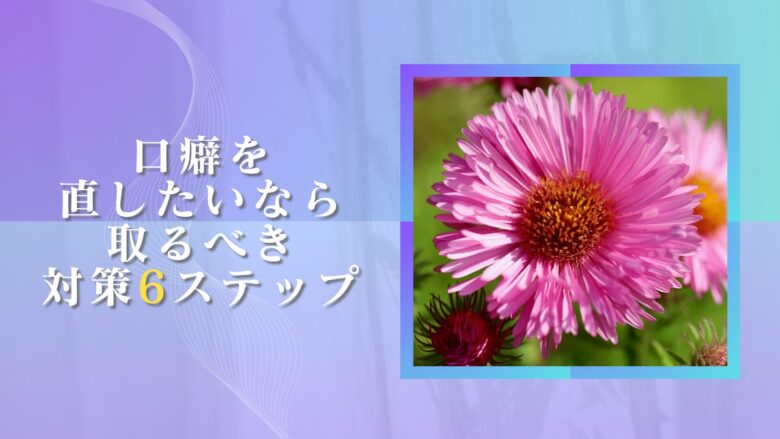
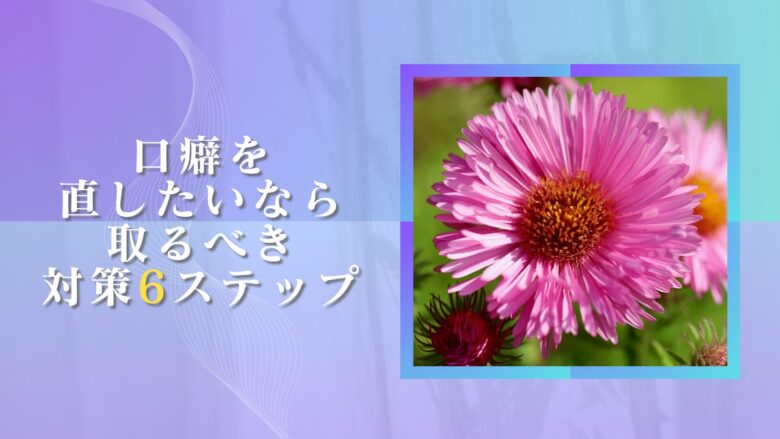



「わかる」といいすぎだから、ちょっと直したいわ。



ふむ、なら、以下の対策をためしてみるとええで。
前述のように多くの場合、「わかる」問う口癖は共感ベースで人と接する中で身についたものであるため、決してとがめられるようなものではありません。ただ、あまりにも多用しすぎると、不信感を狩ってしまう場合があるのも事実です。
そこで、ここでは、わかるという口癖を直すor使用頻度を減らしたいのであれば、取るべき対策について見ていきたいと思います。わかるという口癖を直したいなら取るべき対策は、以下の6ステップです。
わかるという口癖を直したいなら取るべき対策6ステップ
まずは、会話を録音して「わかる」の出現頻度を数えていくことから始める。事実を数値化すると改善の起点になる。実際、己モニタリングはフィラー低減で実証的に有効とされる。
参考:Using Awareness Training to Decrease Nervous Habits in Public Speaking
「わかる」と言いそうになった瞬間の合図(内的サイン)をまず知り、事前に代替反応(深呼吸や顎に手を当てる、軽く頷くだけ等)を決めて習慣化していく。
参考:Using awareness training to decrease nervous habits during public speaking
フィラー(会話の間をつなぐ言葉のこと)の代わりに短い沈黙(1呼吸)を入れる訓練をしていく。沈黙は不安定さではなく落ち着きや余裕として受け取られやすく、パブリックスピーキングの実務でも推奨されている。
参考:Learn how to remove filler words from formal speeches to present with confidence.
週に数回、短い会話や練習を録音して、会話の中で「わかる」をつかっている回数をチェックする。数値の推移を見ればモチベーション維持、自分で気づきにくい癖を客観化が促進される。
不安や焦りが原因で反射的に「わかる」が出ると感じる場合、短時間の呼吸法やマインドフルネスで衝動を抑える練習をする。事実、スピーチ不安の軽減にマインドフルネスが寄与するエビデンスがある。
なお、マインドフルネス瞑想について、詳しく知りたい方は以下の記事を参照。
話すスピードを意識的に落として、句読点ごとに呼吸を入れる練習をしていく。ゆっくり話すことで「わかる」をはさむ隙間が減る。このような訓練は、流暢性訓練をいいフィラーの減少に対して効果的である。
参考:Speech Disfluencies in Consecutive Interpreting by Student Interpreters: The Role of Language Proficiency, Working Memory, and Anxiety
なお上記の方法以外にも、信頼できる第三者(家族や同僚)に定期的にフィードバックをもらうのも有効でしょう。
そして、口癖が重度かつそれが対人の心象を著しく損なっていると感じる場合は、言語聴覚士など専門家の支援を仰ぐのがおすすめですね。実際、専門的介入は臨床レベルでも利用されています。
わかるが口癖の人の心理に関するFAQ
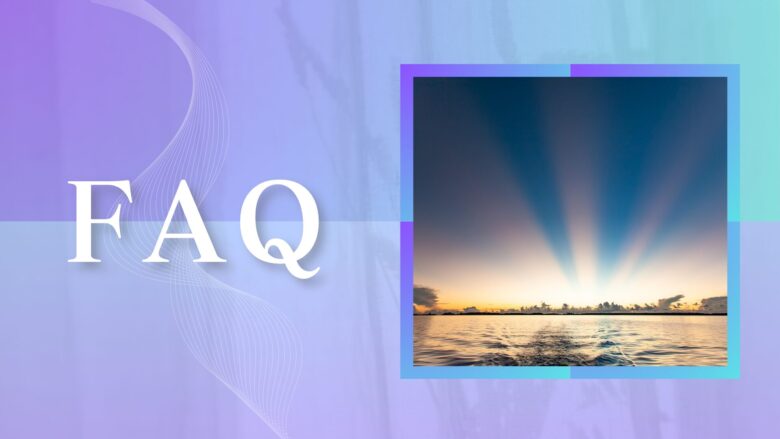
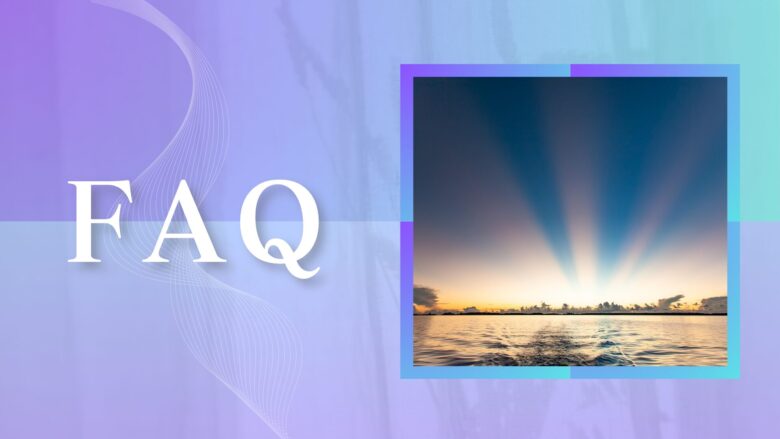



まだ気になる事が、あるんよねえ。



ふむ、最後に疑問について答えていこうかのお。
最後に、わかるが口癖の人の心理に関する疑問について、回答していこうかと思います。
FAQ①:「わかる」を言う人は本当に理解や共感している?
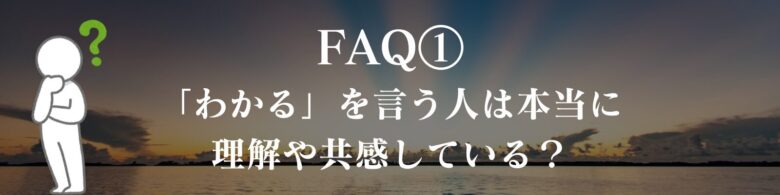
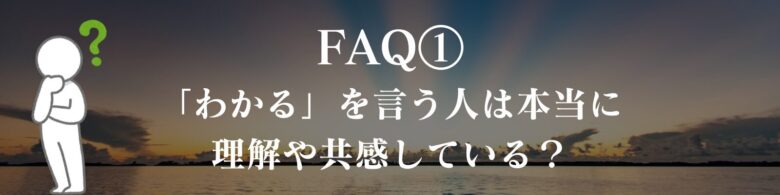
「わかる」を言う人が本当に理解や共感しているかは、場合によります。多くは「聞いてますよ・関与してますよ」という意思表示を示すために、おこなってます。
ただ、短い「わかる」という言葉だけで具体的内容や感情まで理解しているとは限らないので、話の深さや非言語(視線・うなずき)・続く言葉で判断する必要がありますね。
FAQ②:「わかる」が口癖の人は薄っぺらい人?
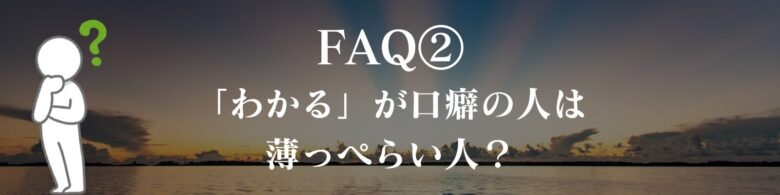
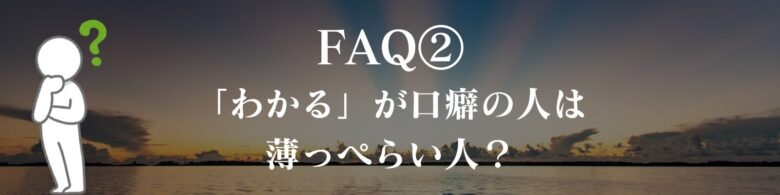
前述のように、「わかる」が口癖の人がその口癖を身に着けた背景には色々な配慮がある可能性があるので、薄っぺらい人であるとは限りません。
ただ、「わかる」という口癖をもっぱら責任回避や会話の主導権を握るための手段として身に着けた人に関しては、相手への配慮ベースで身に着けた人と比較すると人間性の点で未熟である事も少なくないと思います。
FAQ③:「わかる」が本物か偽物かどう見分ける?
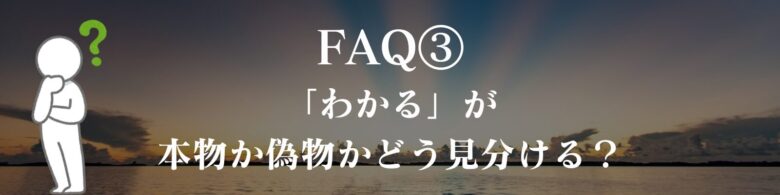
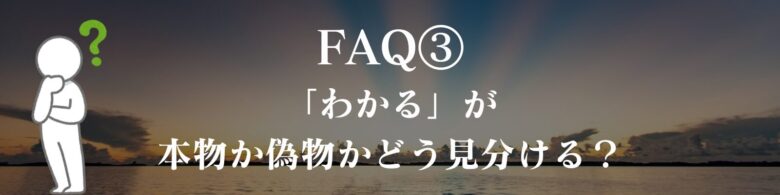
ある人の放った「わかる」が本物か偽物かを見極めたい場合、以下の点に着目するといいでしょう。
「わかる」が本物か偽物かどう見分けるポイント
- 具体性:続けて「どの点が?」と説明できるか。
- 非言語:目線・表情・うなずきが一致しているか。
- 行動:言葉の後にフォローや行動があるか。
- 会話の結果:話し手が安心して深掘りできるか。
「わかる」が口癖の人の心理は共感重視の表れ!「わかる」という口癖は別に無理にやめなくてOK!
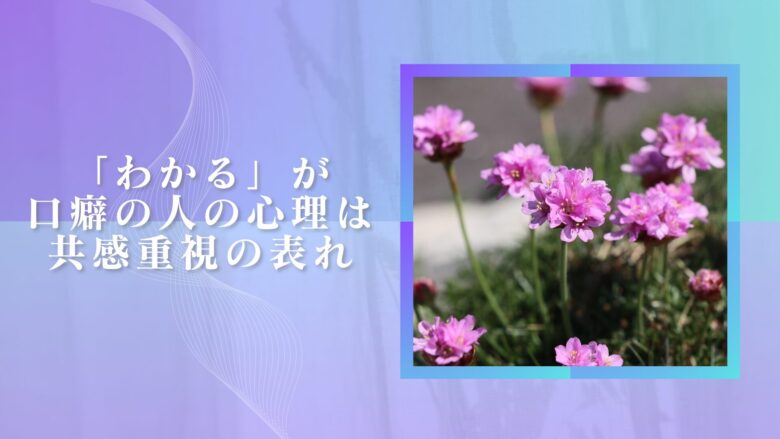
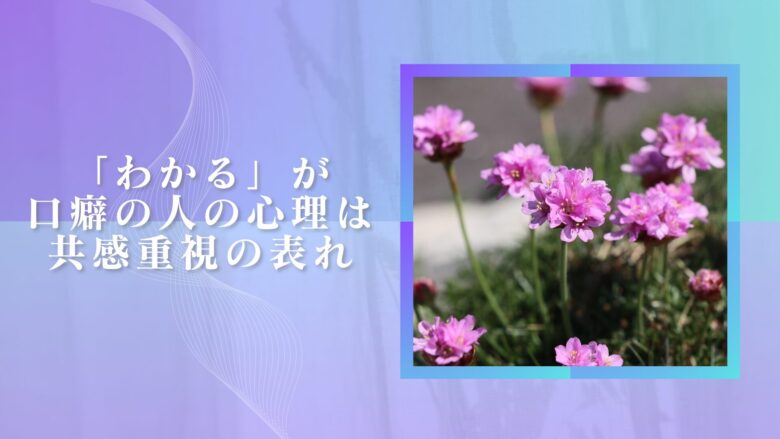
「わかる」が口癖の人は共感重視で会話をしていることが、ほとんとです。一部、「いちいち真面目に話を受け取って返すのがだるいから「わかる」といっておけばいいや」という人もいますが、正直、そこまで多くはないでしょう。それに、誰にでもそういったことは時々あるでしょうし、あまり問題にしなくていいかと思います。
ただ、あなたが「私はあまりにも「わかる」といいすぎているな、ちょっと減らした方がいいな」と思う場合に関しては、前述の6ステップを実践し「わかる」を適切な頻度に調節したらいいと思います。もっとも、普通はそこまで問題にしなくていいと思いますけどね。



まあ、あまり気にしなくてええで。
ちなみに、公式ラインでは「もっと自分を理解したい」、「人との関わりをうまく築きたい」、そんなあなたのために不定期で心理学的ヒントを発信しています。ただ今LINE登録者限定で、心の軸を取り戻すための限定記事や表ではあまり言えない実践知ベースの限定記事のパスワードをプレゼント中です。
あなたの生き方を少しずつ再構成していくヒントをお届けします。心の成長を始める第一歩として、今すぐ登録を!