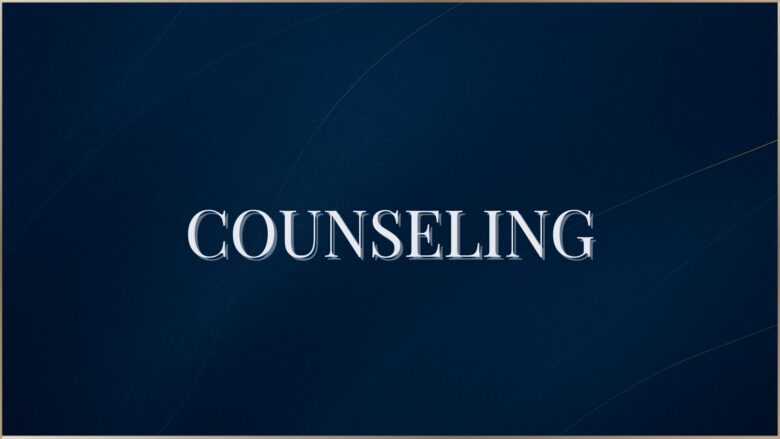おにぎり
おにぎりよく笑う人はよく泣いた人って、本当なん?



いや、必ずしも本当とは言えんね。
ネット上では、「よく笑う人はよく泣いた人だ」という話が、しばしばなされます。確かに、あまりに明るい人には、何か裏や隠された闇があるのではないかと思ってしまうのが人情というものですから、こうした話がなされるのもわかる気はするものです。
そんな感じですから、よく笑う人はよく泣いた人とは、本当なのか気になりますよね?結論から言うと、必ずしもよく笑う人はよく泣いた人という言葉は、本当とはいえません。その理由については、以下の通りです。
「よく笑う人はよく泣いた人」が必ずしも本当でない理由
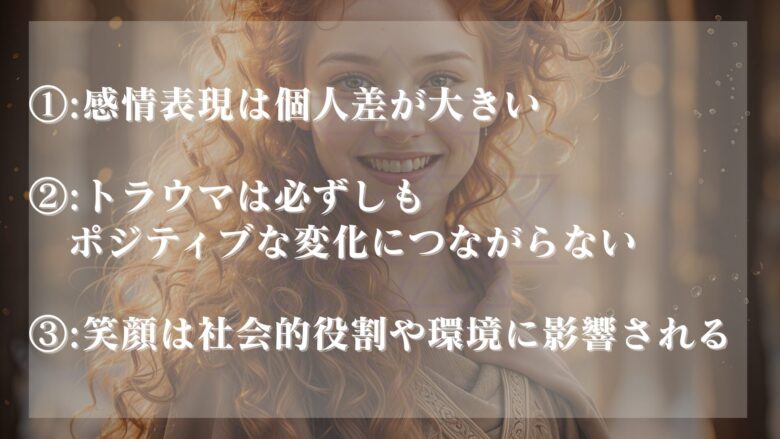
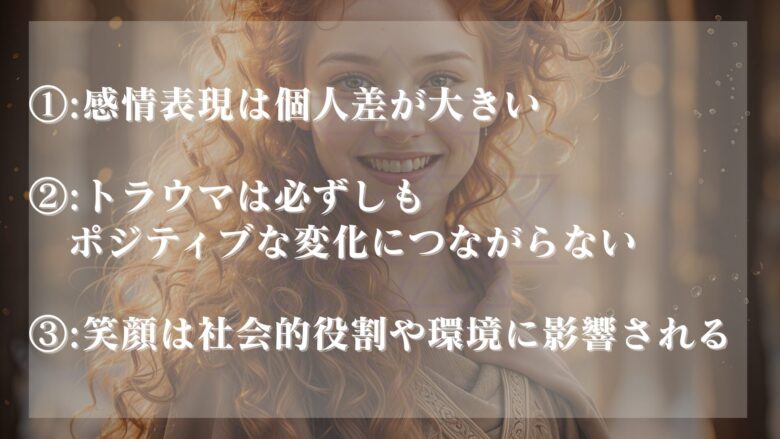



そもそも、感情表現は個人差が大きいからねえ。
よく笑う人はよく泣いた人であるとは必ずしも本当とは、言えません。なにせ、元から外向性が非常に高く感情表現が豊かな人もいるからです。こうした人は、もともと底抜けに明るいがために、よく笑っていたりすることも珍しくありません。このようによく笑う人は、人からの印象という点では最強です。
もし後天的に彼らのようによく笑うようになりたいのであれば、まずはメンタルの安定を徹底するのが先決です。不安が多いと、とても笑う気になんてなりませんから。そのため、日々のメンタルケアは必須です。とはいえ、自力で効果的なメンタルケア対策を日々きちんと行うのは、なかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!
\月間1,600円(税込) /
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
「よく笑う人はよく泣いた人」が必ずしも本当でない3つの理由





「よく笑う人はよく泣いた人」って、本当なん?



いや、必ずしもそうではないねん。
冒頭でもふれましたが、「よく笑う人はよく泣いた人」は、必ずしも本当でなはありません。「よく笑う人はよく泣いた人」が必ずしも本当でない理由は、以下の通りです。
よく笑う人はよく泣いた人が必ずしも本当でない理由
- 理由①:感情表現は個人差が大きい
- 理由②:トラウマは必ずしもポジティブな変化につながらない
- 理由③:笑顔は社会的役割や環境に影響される



それぞれ、詳しく見ていこう!
理由①:感情表現は個人差が大きい


「よく笑う人はよく泣いた人」が必ずしも本当でない理由として、まず「感情表現は個人差が大きい」というものがあげられます。
人々が感情をどのように表現するかは、性格や文化的背景に大きく左右されるものです。事実、心理学のビッグファイブ性格特性に関する研究によると、外向性の高い人はポジティブな感情を頻繁に表現しますが、これは過去の辛い経験とは直接関係しません。



確かに、外向性の高い人ほど、笑っている気がするね。
例えば、楽観的な性格の人は苦労が少なくても笑顔が多く、逆に内向的な人は苦労を経験しても感情を表に出さない場合があります。
そうしたことから考えると、「よく笑う」ことが「よく泣いた」経験の結果とは限らないという話になるでしょう。
理由②:トラウマは必ずしもポジティブな変化につながらない
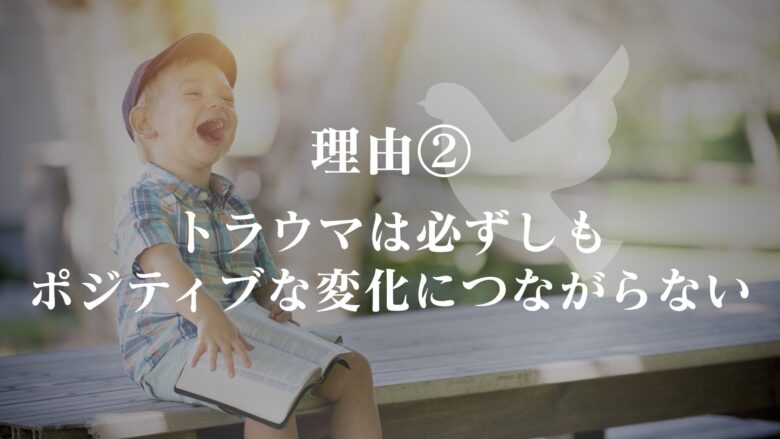
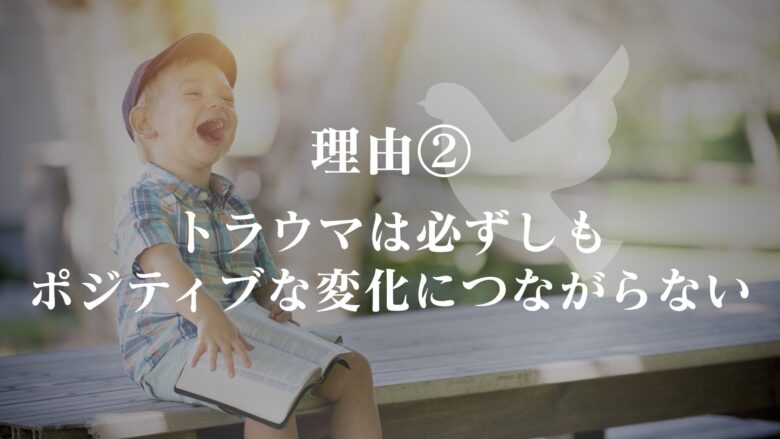
「よく笑う人はよく泣いた人」が必ずしも本当でない理由として、「トラウマは必ずしもポジティブな変化につながらない」というものもあげられます。
心的外傷後成長に関する研究では、辛い経験が成長やポジティブな変化につながる場合があるとされていますが、これは全員に当てはまるわけではありません。
参考:Target Article: “Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations and Empirical Evidence”.



そうねえ、、確かに中々きついか、、。
実際の所、深刻なトラウマは、PTSD(心的外傷後ストレス障害)のように精神状態を悪化させ、笑顔を取り戻すのを難しくすることがあります。
したがって、過去に泣いた経験が必ずしも現在よく笑うという状態につながるとは限らないのです。人は得てして、過去の逆境を乗り越えて成長し、、、という物語が好きなので過去の経験を美談にしがちですが、現実はそう簡単ではないということですね。
理由③:笑顔は社会的役割や環境に影響される
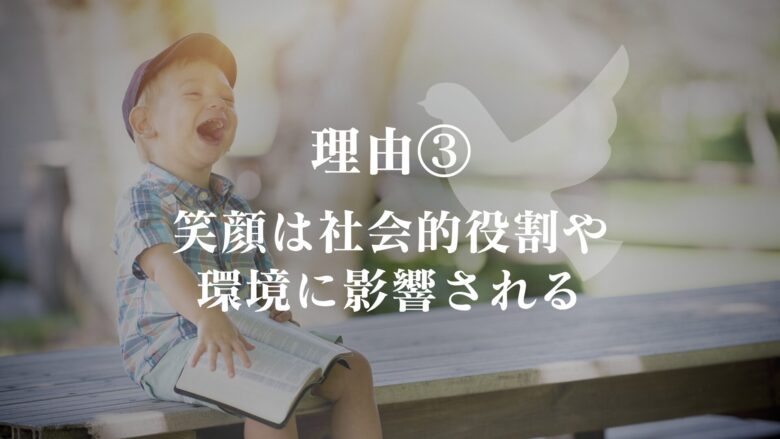
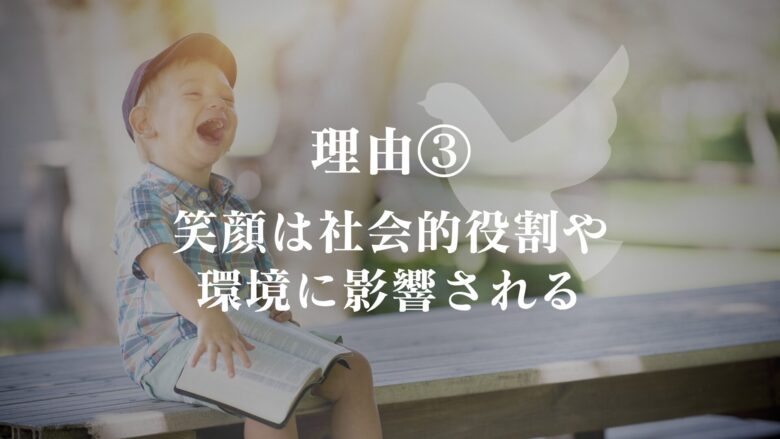
「よく笑う人はよく泣いた人」が必ずしも本当でない理由として、「笑顔は社会的役割や環境に影響される」というものもあげられます。
笑顔は内面的な幸福や過去の経験を必ずしも反映せず、社会的期待や環境に応じた「表面的な感情表現」である場合もよくあるものです。



つまり、、作り笑いとか?
たとえば、感情労働の研究では、サービス業従事者などが仕事上笑顔を強制されるケースが示されています。この結果は直感的にも、心当たりがある方は非常に多い事でしょう。
このような笑顔は、過去の泣いた経験とは無関係に生じるため、よく笑うこととよく泣いたことの間に特段の因果関係は成立しないでしょう。
さらに言えば、過去に泣いた経験があろうがなかろうが、接客業で作り笑いが板につきすぎて、プライベートでも作り笑顔が当たり前になっている人だって結構いると思います。
「よく笑う人はよく泣いた人」という言葉の本当の起源は?
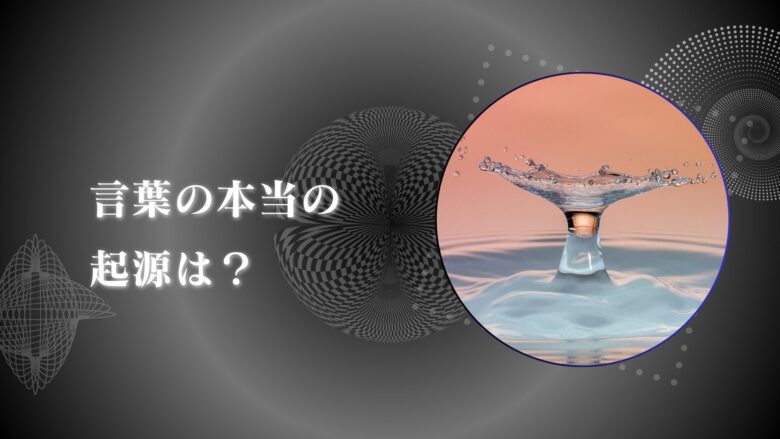
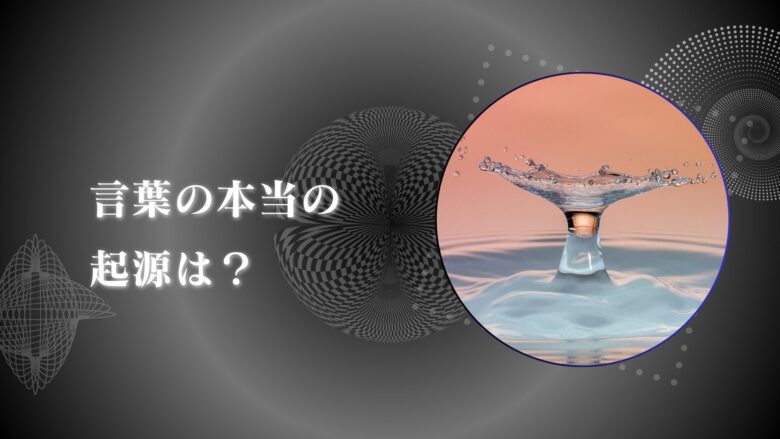



「よく笑う人はよく泣いた人」って、誰が言い始めたん?



確かなことは、わかっていないんよね。
まず、結論から言ってしまうと、「よく笑う人はよく泣いた人」という言葉の本当の起源については、よくわかっていません。「よく笑う人はよく泣いた人」という言葉は、ポエムの形式で2000年代後半〜2010年代前半にSNS・ブログで拡散されました。
流行当時は、引用元不明のまま名言や偉人の言葉として拡散されることが多く、しばしばアメリカの詩人の言葉、海外の格言などと紹介されることがありましたが、英語圏で同じ構文の言葉は文学的には確認されていないといいます。
「よく笑う人はよく泣いた人」は日本発祥の言葉である可能性が高め
ちなみに、「よく笑う人はよく泣いた人」の使用例については、現状確認できるものだとネット上では、以下の2018年に投稿されたアメーバブログの記事が最古のものといえそうですね。
そして、エックス上では、2016年に投稿された以下のポストが最古の使用例となっています。
よく泣いた人がよく笑う人になる3つの方法








つぎは、よく泣いた人がよく笑う人になる方法について、見ていきたいと思います。 よく泣いた人がよく笑う人になる方法は、以下の通りです。
よく泣いた人がよく笑う人になる3つの方法
- 方法①:マインドフルネスで感情を整理する
- 方法②:逆境耐性をあげる
- 方法③:自分の大事にしたいものに則って生きる



それぞれ、詳しく見ていこう!
方法①:マインドフルネスで感情を整理する


よく泣いた人がよく笑う人になる方法の1つ目は、「マインドフルネスによる感情整理」です。
マインドフルネス瞑想は、過去の辛い経験や感情を受け入れ、現在の感情を穏やかに保つ効果があります。実際、以下の研究では、マインドフルネスがストレス軽減やポジティブ感情の増加に寄与することが示されていますね。



ふむ、んで、どんな手順で実践するん?
なお、マインドフルネス瞑想の実践手順は、以下の通りです。
マインドフルネス瞑想の実践手順
静かな場所で、椅子や床に楽に座る(横になっても可)。スマートフォンや時計を近くに置き、5分タイマーをセット。
背筋を軽く伸ばし、肩をリラックス。目は軽く閉じるか、床の一点を見つめる。
息を鼻から吸い口から吐き、呼吸に意識を集中。吸う時に「お腹が膨らむ」、吐く時に「空気が抜ける」と感じる。思考が逸れたら、優しく呼吸に戻す(これが重要!)。
呼吸を続けながら、体の感覚(足、腹、胸など)を順に観察。緊張やざわつきがあれば、ただ「気づく」だけにとどめる。
タイマーが鳴ったら、ゆっくり目を開け、体の感覚や気持ちの変化を軽く振り返る。
よく泣いた人がよく笑う人になりたいならマインドフルネスで感情を整理しよう
方法②:逆境耐性をあげる


よく泣いた人がよく笑う人になる方法の2つ目は、「逆境耐性をあげること」です。過去の泣いた経験を受容し糧にしていくためには、逆境耐性(レジリエンス)を高めていくことが不可欠といえます。
逆境耐性(レジリエンス)は、ストレスや逆境を乗り越える能力を指します。レジリエンス研究では、自己効力感や問題解決スキルの向上が、逆境後のポジティブな感情を促進するとされています
例えば、中々実践は難しい時もあるでしょうが、失敗や辛い経験を「学びの機会」ととらえ直し、小さな成功体験を積むことで、笑顔で前向きに生きる力が養われるでしょう。週に1回、過去の困難から学んだ教訓を書き出し、それを活かした行動計画を立てることがおすすめです。



ふむ、、、そうねえ、まあやってみようか。
なお、レジリエンスを高めるためには、セルフコンパッション(自分への思いやり)も非常に効果的です。セルフコンパッションについて、詳しく知りたい方は以下の記事を見てみて下さいね。
よく泣いた人がよく笑う人になりたいなら逆境耐性をあげよう
方法③:自分の大事にしたいものに則って生きる


よく泣いた人がよく笑う人になる方法の3つ目は、「自分の大事にしたいものに則って生きること」です。
「自分の大事にしたいもの」に基づいた人生・生活は、幸福感や自己肯定感を高め、笑顔になれる心の余裕を形成していきます。実際、内在的動機(自分の価値観や興味に基づく行動)がメンタルヘルスを向上させることが示されていますね。



自分の大事にしたいものに基づいて生きるのが大事なのね。
例えば、「家族との時間」や「創造的な活動」を大切にする人は、それらを優先する生活を設計することで、過去の辛い経験を乗り越え、笑顔を取り戻しやすくなるでしょう。
自分の大事にしたいものを見つけたい方は、以下の記事を見てみて下さい。
よく泣いた人がよく笑う人になりたいなら自分の大事にしたいものに則って生きよう
「よく笑う人はよく泣いた人」が本当か気になる時にありがちな疑問





まだ、気になる事があるんよね。



んじゃ、最後に疑問にこたえていこうかの。
最後に、「よく笑う人はよく泣いた人」が本当か、気になる時にありがちな疑問について回答していこうかと思います。
疑問①:笑顔が多い人は本当に幸せ?
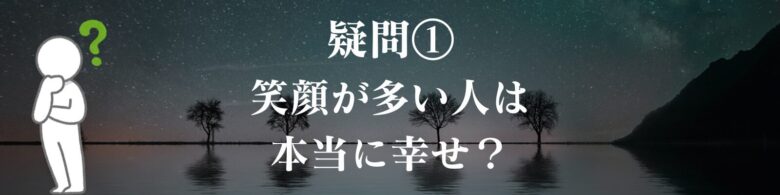
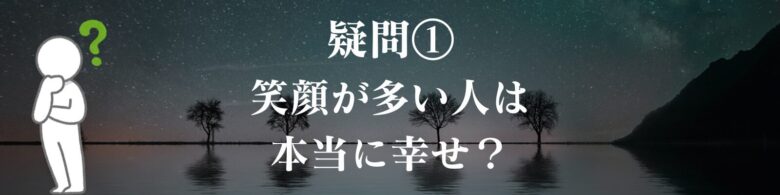
笑顔は幸せを表す場合もありますが、必ずしも内心の幸福を反映しません。実際、以下の研究では、意識的に笑顔を作る「ポジティブ感情の再評価」が幸福感を高める可能性がある一方で、強制的笑顔はストレスを増やすこともあるとされています。
参考:The emerging field of emotion regulation: An integrative review.
自分に無理のない範囲で笑顔を増やし、内面の幸福感を育むことが大切です。
疑問②:笑顔が増えると人間関係は本当に良くなる?
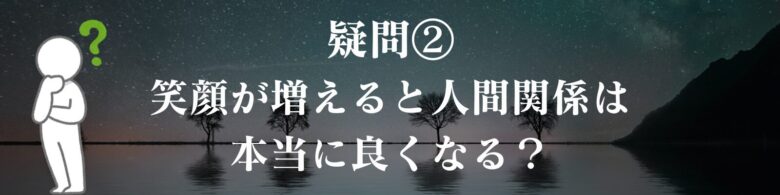
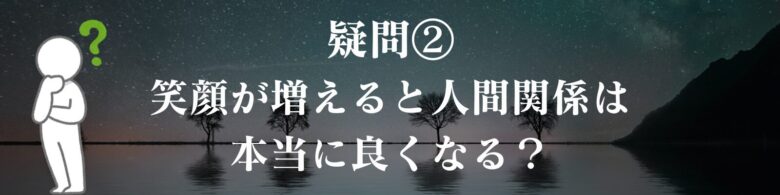
笑顔にH相手に安心感や親しみを与え、信頼関係を築きやする効果があることは間違いありません。事実、社会的信号の研究では、笑顔が他者のポジティブな反応を引き出し、対人関係を改善する効果があるとされています。
ただ、過度に無理した笑顔は不自然に見え、逆効果になる場合もあるため、自然体でいることが重要ですね。
よく笑う人はよく泣いた人が必ずしも本当とはいえない!ただ泣いた経験を活かしてよく笑った方が人生良くなるのはガチ!


「よく笑う人はよく泣いた人」は、必ずしも本当ではありません。というのも、もともと底抜けに明るいような人は、そもそも不安にとらわれずよく笑うものだからです。ただ、泣いた経験を活かして、よく笑うようになったた方が人生良くなるのは本当でしょう。
いつも辛気臭そうな顔をしていたら、自分も他人も気分が悪くなってしまいますからね。ただ、過去に何回も泣くようなつらい経験をした人ほど、よく笑うためには日々安定した精神状態になるための努力が不可欠ではあるでしょう。過去のつらい経験に流されないためにも、日々のメンタルケアは重要です。



過去につらい事がある人ほど、入念にケアした方がええで。
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、人間関係と人生を豊かにしていくための下地を整えていきましょう!
\月間1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\!\