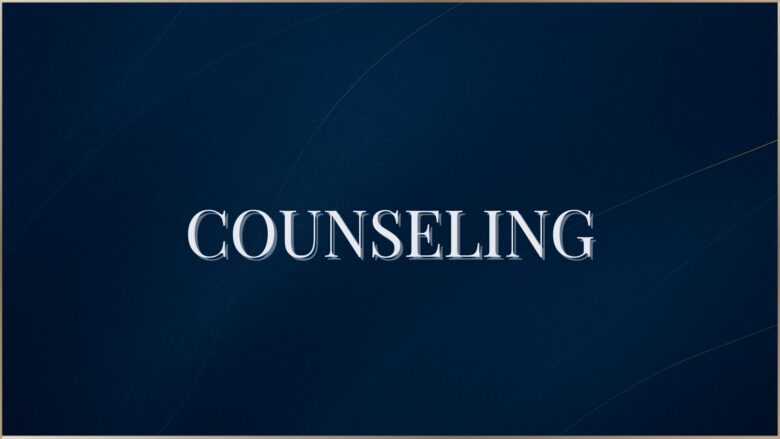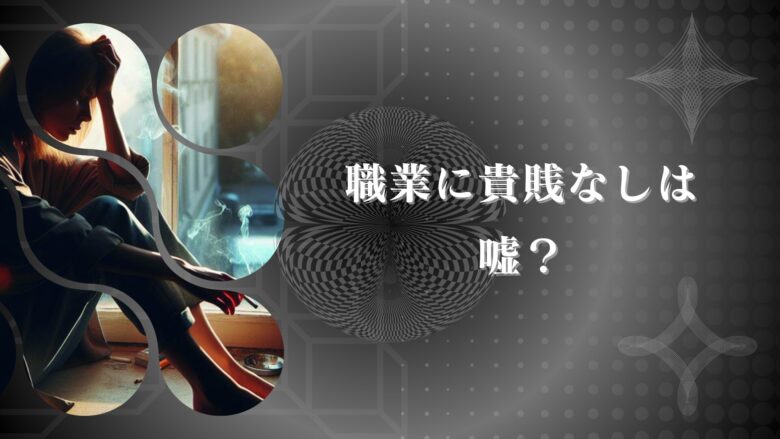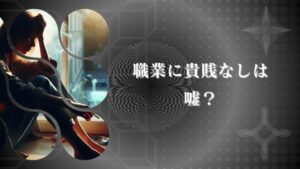おにぎり
おにぎり職業に貴賎なしは、嘘なん?



いや、嘘ではないで!
「職業に貴賎なし」ということわざがありますが現状の社会情勢などから考えて、このことわざがひどく嘘くさいきれいごとにしか思えない方も増えているようです。実際、私も一時期、「職業に貴賤なしとか、そんなわけあるか!」と思っていましたから、わかる気がします。
ですから、「職業に貴賎なし」は嘘なのか、気になりますよね?結論から言うと、「職業に貴賎なし」は嘘ではありません。「職業に貴賤なし」が嘘ではない理由は、以下の通りです。
職業に貴賤なしは嘘ではない3つの理由
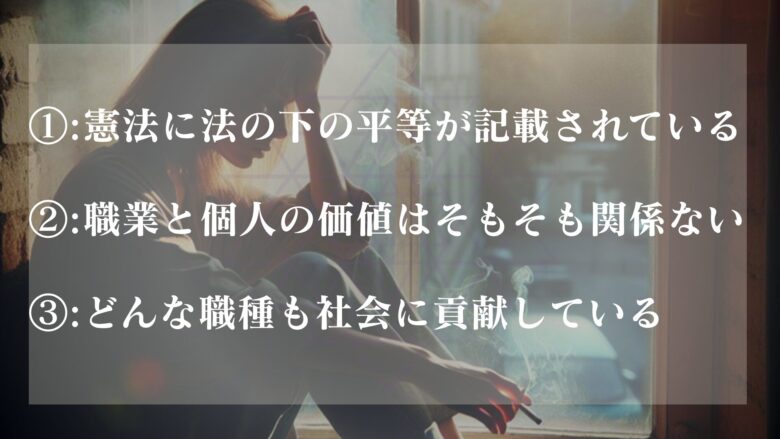
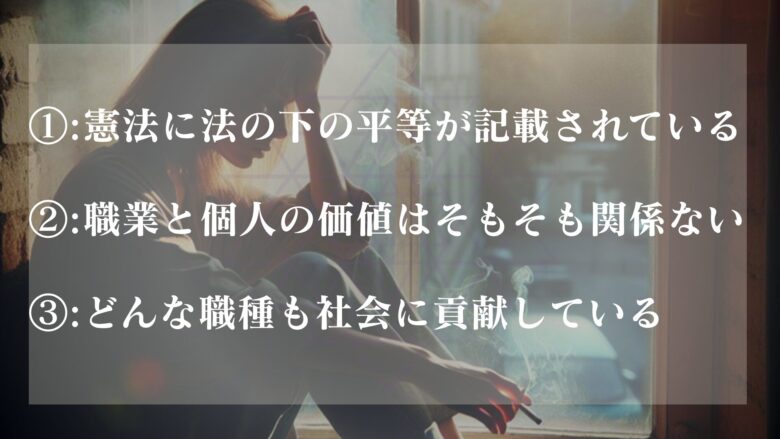



特に、職業は人の都合でできたものにすぎないって視点が大事!
「職業に貴賤なし」という言葉は一見きれいごとで嘘のように聞こえますが、そもそも職業は人為的に作られたものにすぎずそれ自体に意味などありません。そもそも職業自体に価値などないので、職業に貴賤などありようがないです。ただ精神的に不安定だと、自分の職業を卑下したくなる方もいるでしょう。
職業に貴賤なしという言葉が、ただのきれいごとに聞こえるのなら、日々のメンタルケアをしっかりする必要があります。それでこそ、自分の人生の主導権を確立し、満足くして生きていけるというものです。とはいえ、自力で日々のメンタルケアを効率的に行うのは、なかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
職業に貴賤なしが嘘かを3つの視点から徹底検証
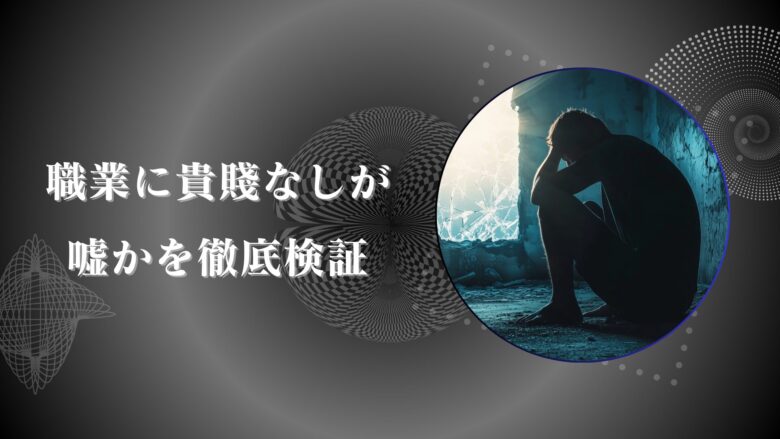
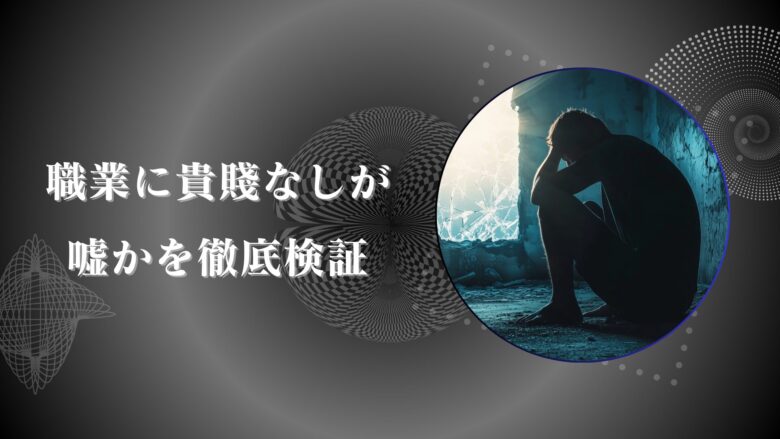



職業に貴賤なしって嘘、な気がするんよね。



んじゃ、以下の3つの視点から検証してみよう!
まずは、職業に貴賤なしが嘘かを、検証していきたいと思います。職業に貴賤なしが嘘かを検証する視点は、以下の通りです。
職業に貴賤なしが嘘かを検証する視点
- 視点①:社会制度
- 視点②:人間心理
- 視点③:社会経済



それぞれ、詳しく見ていこう!
視点①:社会制度
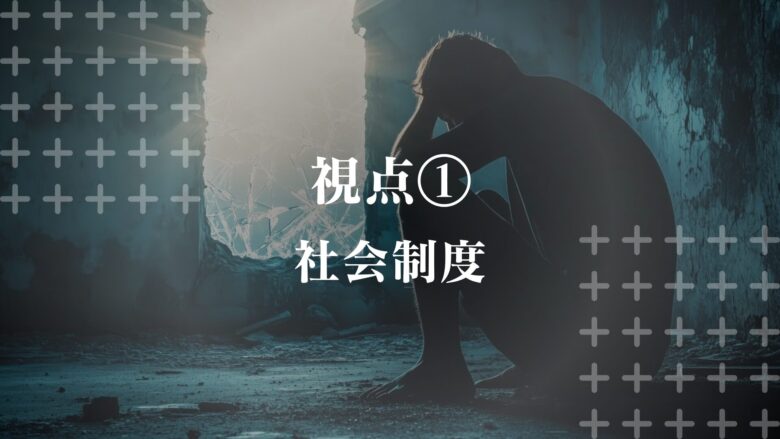
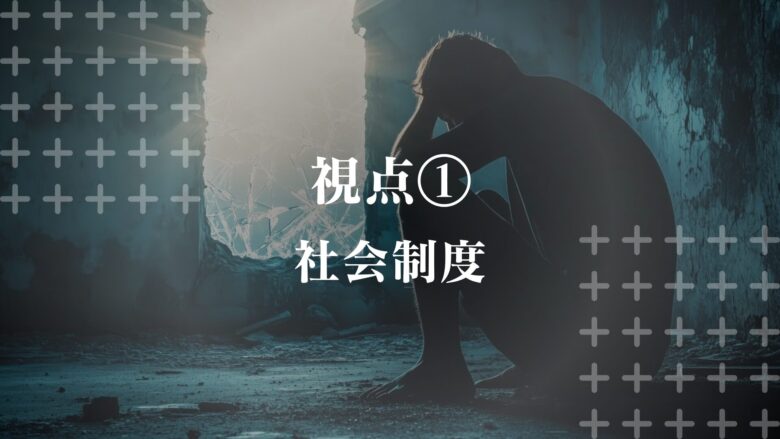
まずは、職業に貴賤なしが嘘かどうかを社会制度の視点から、検証していきたいと思います。
憲法では職業に貴賤がない旨が明確に記述されており、現実の社会制度もその趣旨に沿って設計されているのが現状です。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
引用:法令検索・日本国憲法



だね、法の下の平等やもんね。
そのため、社会制度の視点から見ると、「職業に貴賤なし」は全く嘘ではありません。
視点②:人間心理
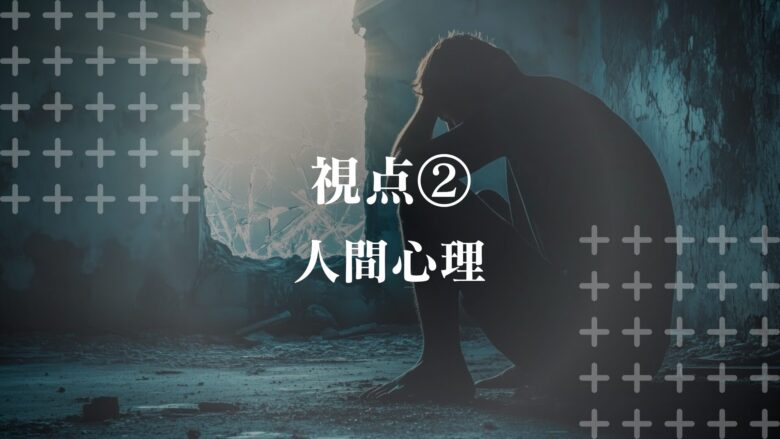
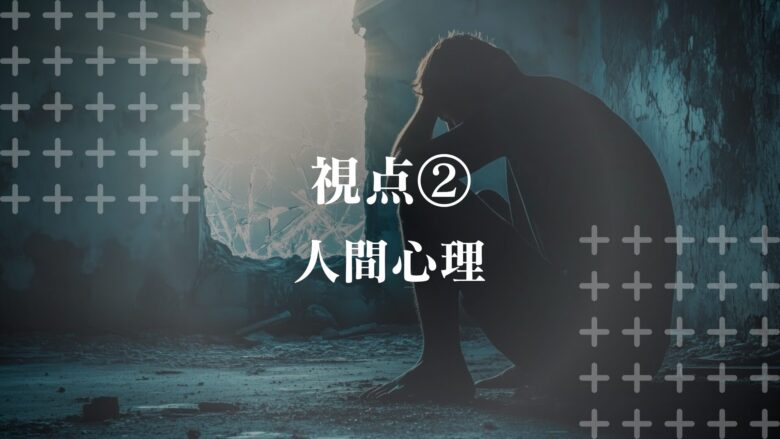
つぎに、職業に貴賤なしが嘘かどうかを人間心理の視点から、検証していきましょう。
まず社会心理学的視点から考えると、人は他者と比較して自己評価を行う傾向があり、職業は地位や成功の指標として機能します。具体的に言うと、高収入や高地位の職業(医師、経営者など)は社会的承認を得やすい一方で、逆に低賃金や肉体労働の職業は軽視されがちです。
実際、日本には現状、「ホワイトカラー=高価値、ブルーカラー=低価値」といった無意識のステレオタイプが根付いているといわれています。
実際、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)の調査シリーズによれば、職業の社会的評価に関する意識が継続的に分析されており、2023年の高校生対象調査では約60%の人が特定の職業(清掃業、運送業など)が低く見られていると感じていることが示されていますよね。



たしかに、職業に関する偏見はあるよなあ、、。
こうしたことから考えると、人間心理の視点から見ると、「職業に貴賤なし」は嘘とまでは言えないものの、きれいごとと感じやすいのは間違いないでしょう。
とはいえ、後述するように、職業などそもそも人間が勝手に作り出したものにすぎないため、職業と個人の価値はそもそも関係ないんですけどね。
視点③:社会経済
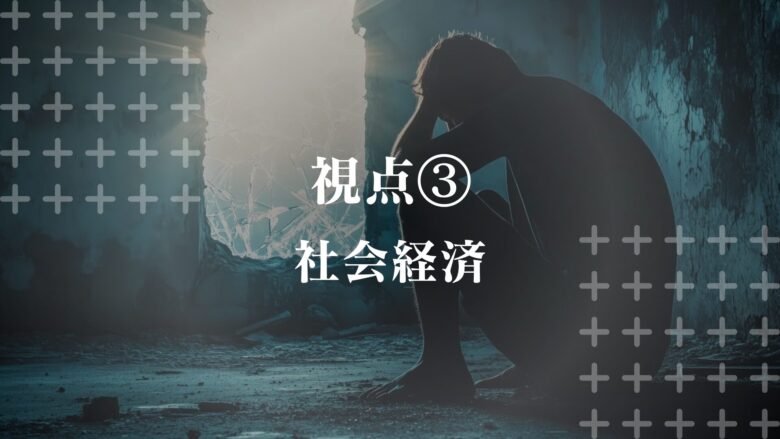
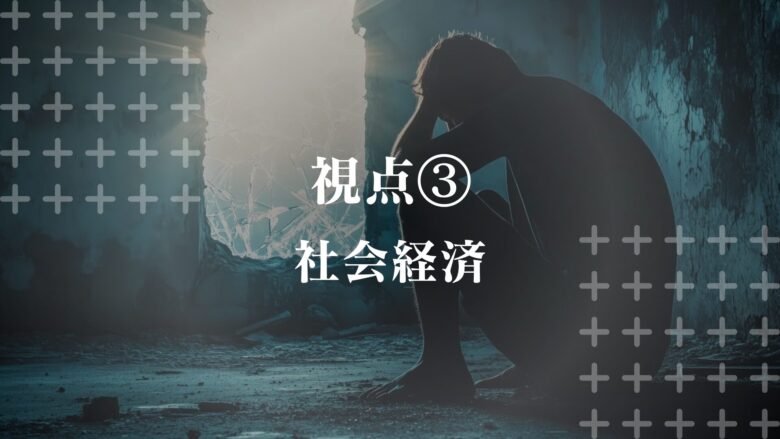
最後に、職業に貴賤なしが嘘かどうかを社会経済の視点から、検証していきましょう。
経済的視点から考えると、職業間には収入において非常に大きな格差が存在しています。例えば、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」(2024年)によれば、医師や弁護士といった専門職の平均年収は約1,200万円であるのに対し、介護職や清掃員は約300万円と、4倍近い開きがありますね。



そんなに開きがあるんか、、、。
こうした賃金格差は、人々の職業に対する偏見を強化するため、なかなか理想的な平等を実現するのは難しそうです。
とはいえ、どの職業であっても、社会経済全体に大なり小なり貢献しているので、その点においては貴賤など存在しないといってもいいと思います。
結論:職業に貴賤なしは嘘ではない!
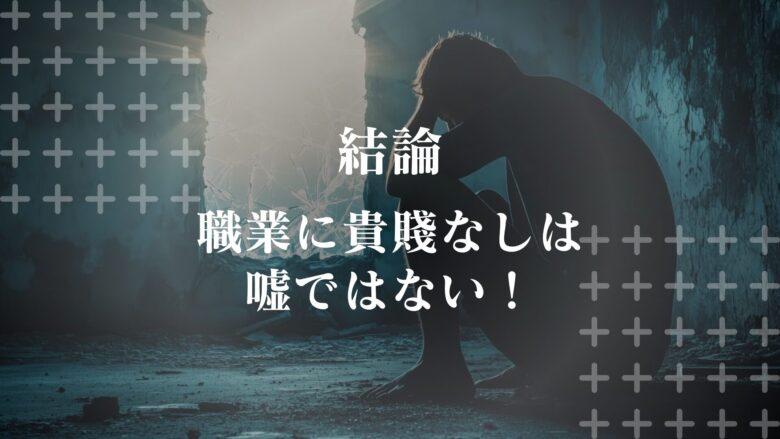
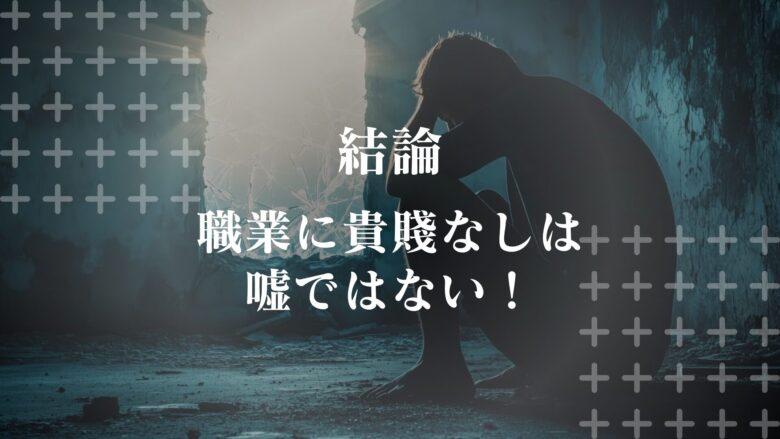
上記の3つの視点(社会制度、人間心理、経済的現実)から検証した結果、「職業に貴賎なし」は現実の格差により嘘と感じられやすいものの、本質的には本当であると結論できます。
ここで、「職業に貴賤なし」といえる理由を総括すると、以下の様になりますね。
「職業に貴賤なし」が嘘ではない理由
- 憲法に法の下の平等が記載されている
- 職業と個人の価値はそもそも関係ない
- どんな職種も社会に貢献している
現状の社会を見ると、確かに社会には賃金の安い職種や専門性の低い職種、肉体労働に対する偏見は存在しており、理想的な平等が難しい状況ではあります。



ブルーカラー蔑視は、まだまだあるよなあ、、、。
しかし、だからといって、本質的には「職業に貴賤なし」というのは嘘ではありません。
職業に貴賤なしが嘘であった方が都合がいい2つの理由





職業に貴賤があった方が都合が人もいる気がする、、。



そうなんよね、実は貴賤があると都合がいい側面もある!
先ほどふれたように、「職業に貴賤なし」は嘘はありません。しかし、社会全体でみると、職業に貴賤があった方が都合がいい側面もあります。
そこで、ここでは「職業に貴賤なし」が嘘であった方が都合がいい理由について、見ていきたいと思います。「職業に貴賤なし」が嘘であった方が都合がいい理由については、以下の通りです。
職業に貴賤なしが嘘であった方が都合がいい理由
- 理由①:治安悪化等に対する抑止力になる
- 理由②:社会不安等のはけ口になる



それぞれ、詳しく見ていこう!
理由①:治安悪化等に対する抑止力になる
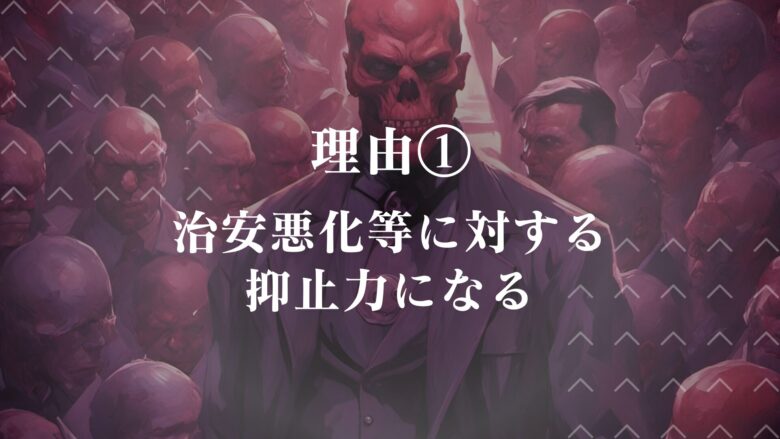
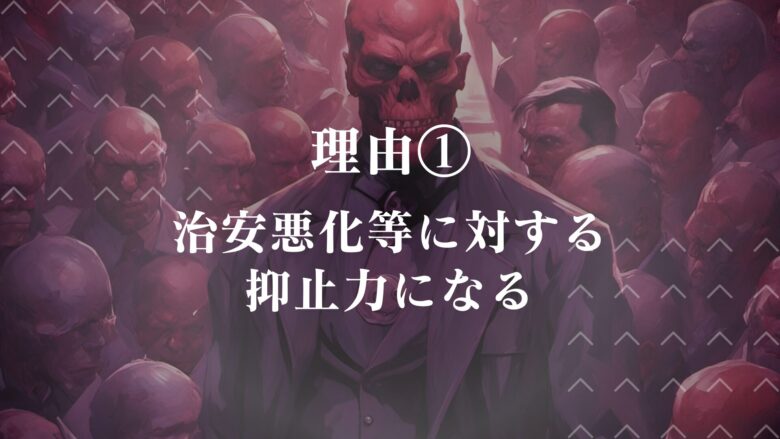
職業に貴賤なしが嘘であった方が都合がいい理由として、まず「治安悪化等に対する抑止力になること」があげられます。
人によっては意外かもしれませんが、職業に貴賎があると信じることには、社会の階層構造を維持し、治安悪化を抑える機能があるという意見がありますね。



んー、感情的にはすごく解せないなあ。
事実、以下のメタ分析による研究によれば、社会階層が明確な場合、労働者の役割受容が高まり社会的安定性が向上すると報告されていますね(反対に貴賤意識がないと、ストライキなどの抗議行動が増えるという)。
参考:The educational journey of a Latina feminist community psychologist
また、いわゆるホストやキャバクラといった夜職に対するヘイトも、そうした職業に憧れて就業する人が増えると、社会秩序が乱れたり国全体としての生産力が落ちるので、存在してくれた方が都合がいいと考える人がいるといえるでしょう。
ちなみに、最近のホスト規制などをみていると、国が夜職があまりにはぶりよさそうにして、衆人の耳目を引いている様子に危機感を感じている感じがします。国民に夜職にあまりいいイメージを持たれると、国は都合が悪いわけです。
理由②:社会不安等のはけ口になる
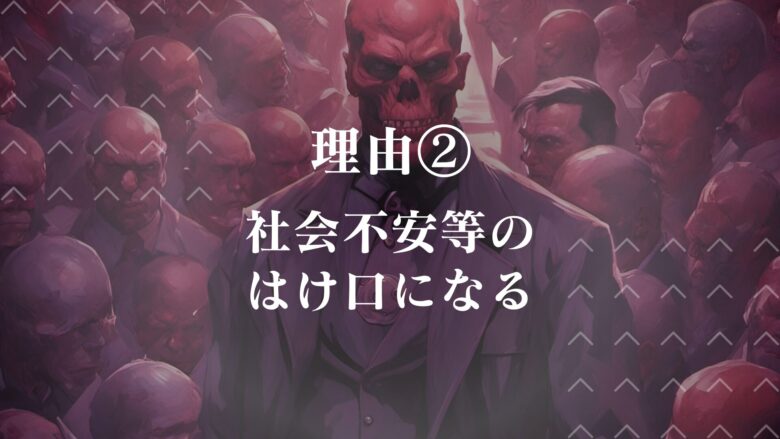
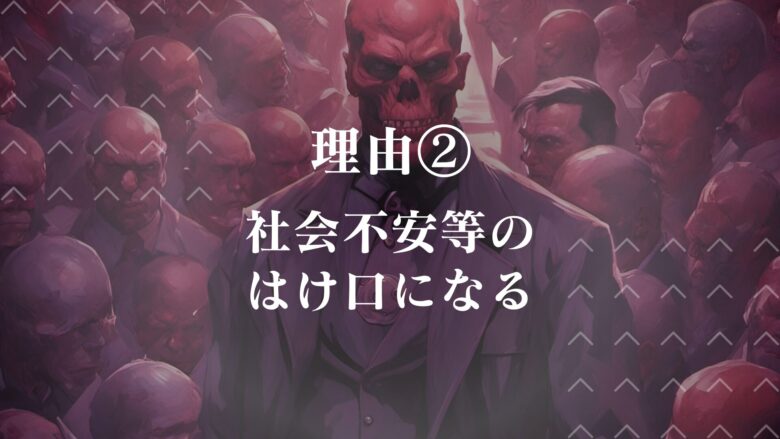
職業に貴賤なしが嘘であった方が都合がいい理由として、「社会不安等のはけ口になること」もあげられます。
職業格差を「貴賎」として受け入れることは、社会不安のはけ口としての役割も果たします。事実、心理学の「スケープゴート理論」によれば、人々はストレスや不満を弱い立場(例: 低地位の職業)に投影することでメンタルバランスを保つ傾向があるといえますからね。



浅ましいけど、、、こういった心理あるよなあ、、。
また、以下のメタ分析による研究では、低地位職業への偏見が社会的ストレスの緩衝材として機能し、支配層への反発を軽減すると報告されています。
要は、自分よりも下の人間たちをいじめる事で、「自分たちはまだマシだ」とか「コイツらがこのざまだから社会が良くならんのだ」などと留飲を下げることができるので、政治などへの怒りが向きにくくなるというわけですね。実に、浅ましい構造ではありますが、理屈としては納得がいくでしょう。



江戸時代のえた非人を思い出すね、、。
最近問題になっている日本の「底辺職」といった表現が、こうした心理的メカニズムを反映している可能性は高いでしょう。
職業に貴賤なしが嘘としか思えない時に取るべき対策
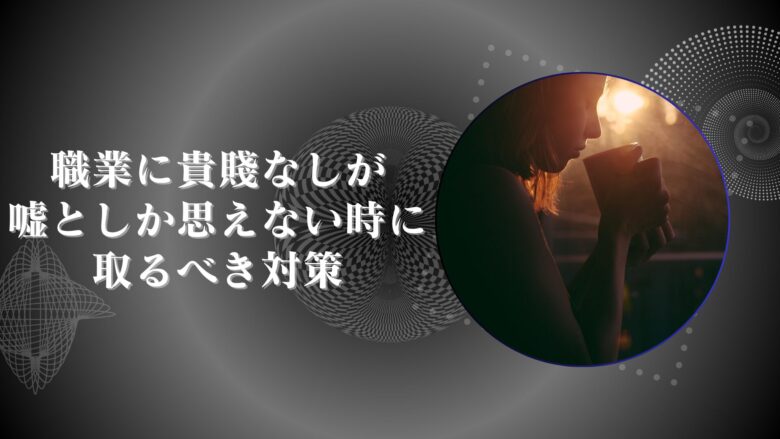
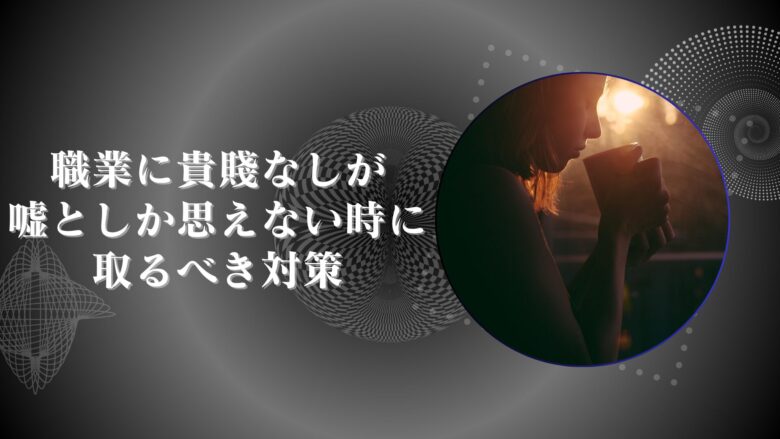



どうにも、自分の職業が卑しい気するわ、、、。



そんな時は、以下の対策をするのがおすすめ!
つぎは、「職業に貴賤なし」が嘘としか思えない時に取るべき対策について、見ていきたいと思います。「職業に貴賤なし」が嘘としか思えない時に取るべき対策は、以下の通りです。
職業に貴賤なしが嘘としか思えない時に取るべき対策
- 対策①:自分軸を確立する
- 対策②:自分と職業を分離する
- 対策③:他業種に移る



それぞれ、詳しく見ていこう!
対策①:自分軸を確立する
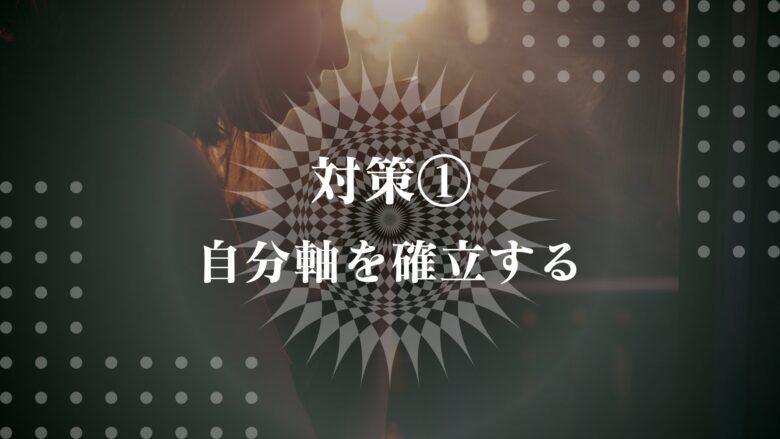
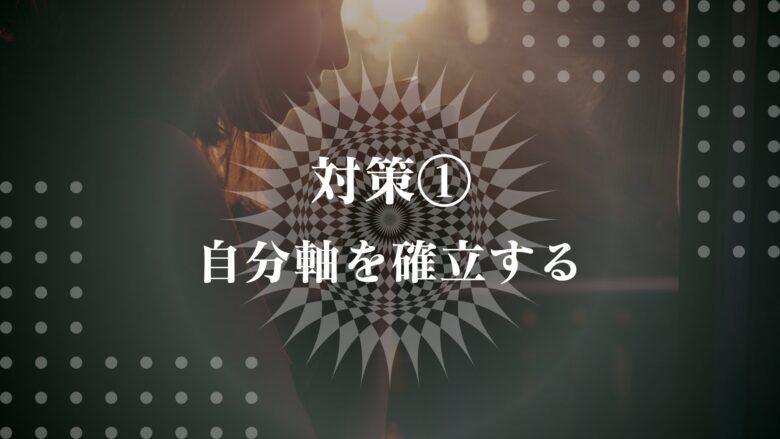
職業に貴賤なしが嘘としか思えない時に取るべき対策の1つ目は、「自分軸の確立」です。
自分軸を確立することができれば、自分がどんな職業についているかにとらわれることなく生きていけます。早い話が、職業を純粋に手段として活用することができるようになり、職業が自分のアイデンティティに与える影響を最小化することができるという感じです。



確かに、軸が定まっていれば、影響されなくなりそう。
自分軸を確立したい方は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。手間はかかりますが、参考になるはずです。
対策②:自分と職業を分離する
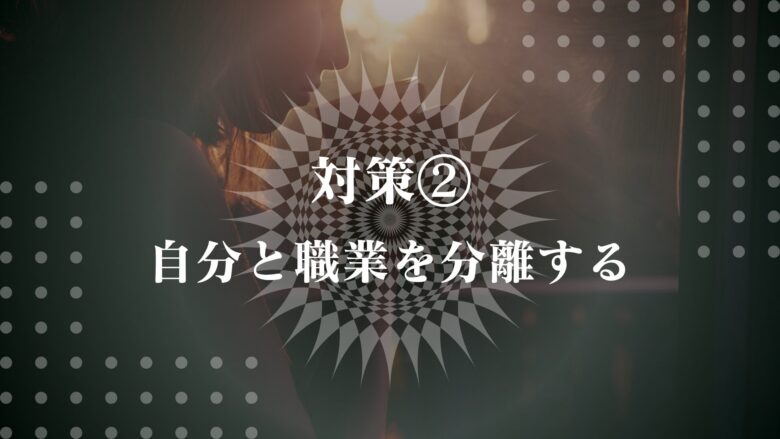
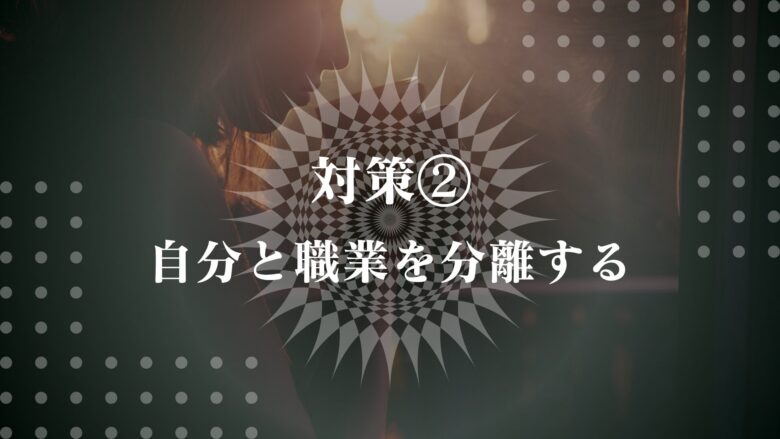
職業に貴賤なしが嘘としか思えない時に取るべき対策の2つ目は、「自分と職業の分離」です。
先ほど少しふれましたが、職業と自分の価値は、全くといっていいほど関係がありません。しかし、自分の従事する職業の世間的評価と自分の価値を混同する人は、かなりいるものです。



それはどうだよ、気になるって。
職業などというものは、所詮人間が自分たちの都合で作り出したものにすぎないので、そんなものに価値があると思う必要は全くないです。もっと言ってしまうなら、職業などは「単に自分の食い扶持を稼ぐための手段にすぎない」とも言えます。
そのため、普段から意識して自分の職業を自己アイデンティティと同一視しないよう意識していきましょう。
対策③:他業種に移る
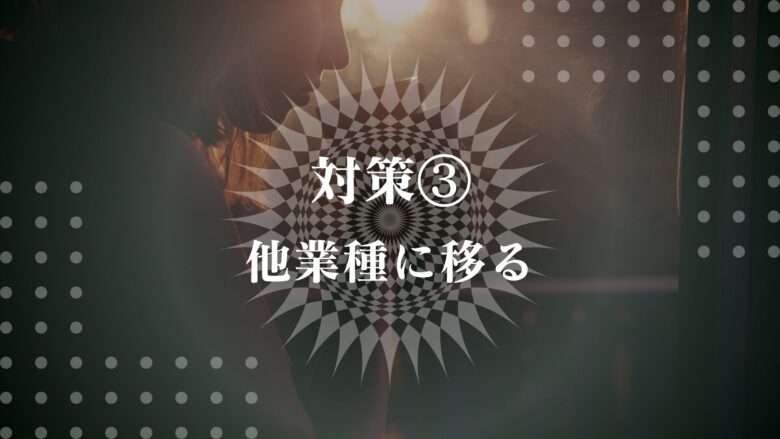
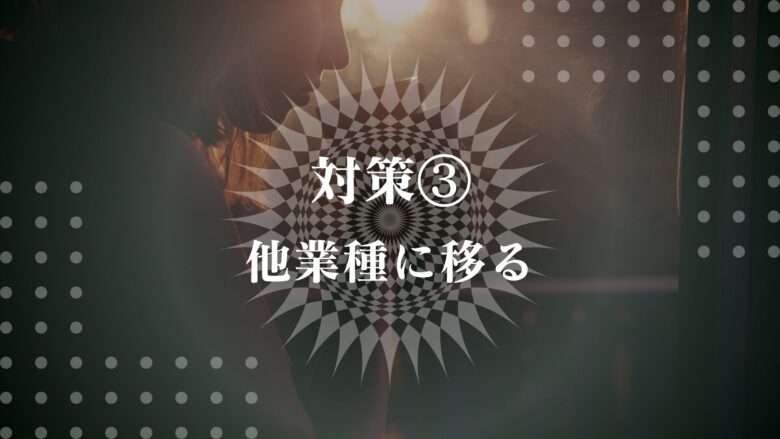
職業に貴賤なしが嘘としか思えない時に取るべき対策の3つ目は、「他業種への転職」です。
前述のような、職業と自分のアイデンティティを分離が難しい場合、他の業種へ意を決して転職するのがいいでしょう。例えば、介護職が嫌で仕方なくなったので、事務職に転職する、といった感じですかね。



ふむふむ。
あとは、自分の手に負える範囲で資格を取得するのもいいかもしれません。個人的におすすめな資格は宅地建物取引主任者と簿記2級ですね。
この2つの資格は、努力の割に得られるメリットが大きい印象です。
職業に貴賤なしが嘘と思う時に気になりがちな疑問





まだ、気になることがあるんよねえ。



んじゃ、最後に疑問にこたえていこう!
最後に、職業に貴賤なしが嘘と思う時に気になりがちな疑問に対して、答えていきたいと思います。
疑問①:「職業に貴賎なし」という言葉は誰が言い始めた?
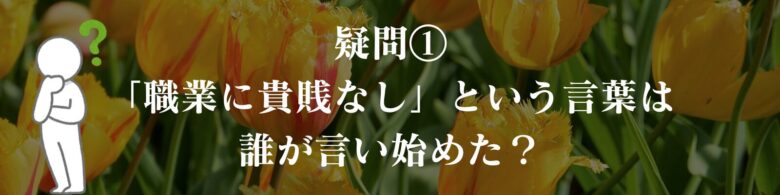
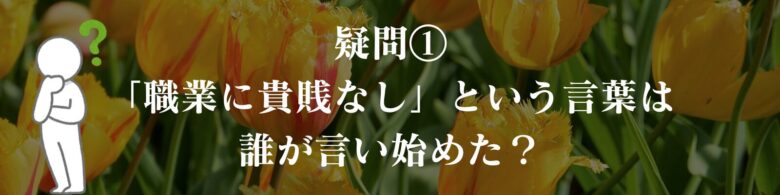
「職業に貴賤なし」は、江戸時代の石田梅岩の著作である『都鄙問答』からの言葉であり、「職業内での地位の高低によって人間の価値は決まらない」といった意味合いであったそうです。
そのため、もともとは現在のような「職業そのものに貴賤はない」といったような用法では、なかったとされます。
疑問②:職業差別は日本特有の問題か?
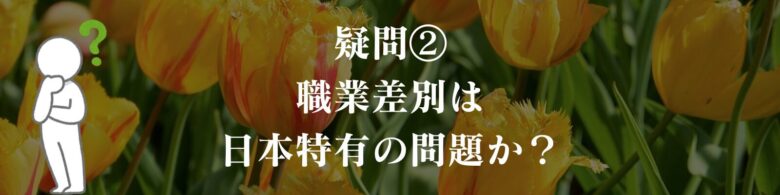
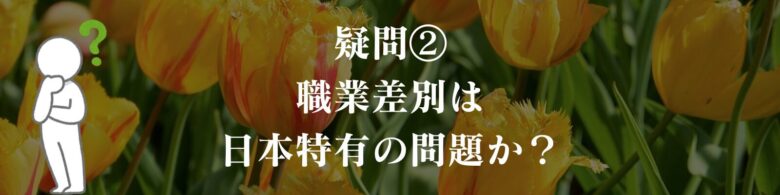
職業差別は、日本だけに限らない世界的な問題です。事実、ILO(国際労働機関)の「Global Wage Report 2024-25」(2024年)によれば、世界的に低賃金労働者(例: 清掃員、サービス業)は差別や低評価に直面しやすく、日本も例外ではないといいます。
参考:Global Wage Report 2024-25: Is wage inequality decreasing globally?
職業に貴賤なしは嘘ではない!職業と自分の価値を分離してこそ後悔なく生きれる!


職業に貴賤なしという言葉は、決して嘘ではありません。確かに、一般に賃金や評価が低い職業というものが存在するのは事実ですが、そもそも職業というものは人為的に作られたものにすぎず、本来はそんなものに価値などありません。それに、あなたはあなたでありあ、あなたの価値と職業の価値は無関係です。
なので、他人があなたのついている職種をした見たとしても、そんな事はあなたの価値を毀損することにはなりません。ただ精神的に参っていると、他人からのそうした声が気になるのは事実です。他者からの評価に影響されないためにも、日ごろからきちんとメンタルケアを行っていくのが快適に生きる上で重要です。



精神的自立には、安定したメンタルが不可欠なのや!
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、他人からの評価に惑わされずに生きるための下地を整えていきましょう!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\