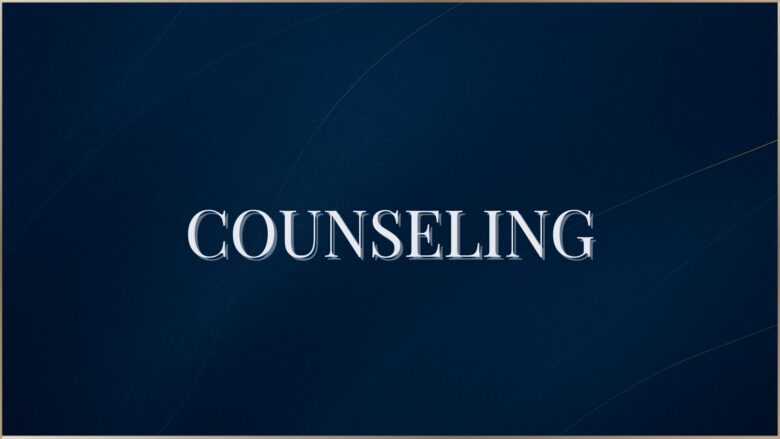おにぎり
おにぎり他人の不幸は蜜の味は、当たり前なん?



個人差あるけど、他人の不幸は蜜の味は当たり前やね。
他人の不幸は蜜の味ということわざがありますが、最近ではSNSを見ていると、このことわざの通りな行動をしているような人達がたくさん目につきます。人によっては、「何て浅ましく醜いやつらだ、、」とあきれるかもしれません。こんな人たちは例外的な存在だと、思いたくなるというものです。
そんな感じですから、他人の不幸は蜜の味と感じるのは、人であれば当たり前のことなのかどうか気になりますよね?結論から言うと、残念ながら、人の不幸は蜜の味と感じるのは個人差はあれど、人間に共通する性質です。なお、以下の特徴を持つ人は、特にこの心理に陥りやすい傾向にあります。’
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴
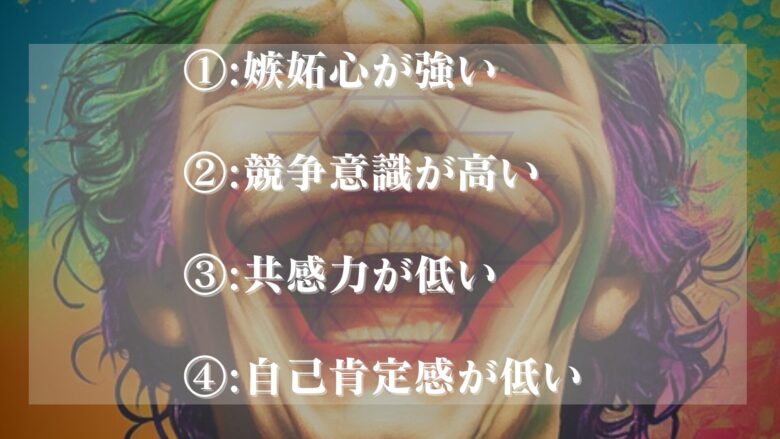
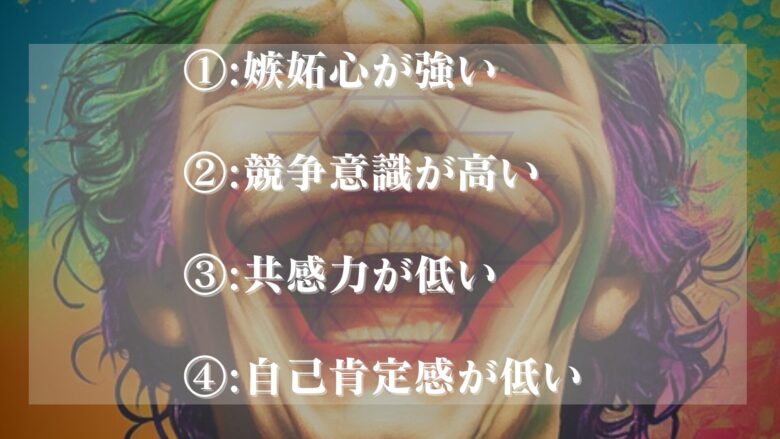



特に、低い自己肯定感と嫉妬が、発生リスクの高い特徴や!
不幸は蜜の味と感じるのは、程度の差こそあれ人類に共通する心理傾向ですが、共感力を鍛えたり自分軸を確立したりすれば発生リスクを抑えられます。ただ、再前提としてメンタルを安定させることは、絶対条件です。メンタルが不安定では、無意味に感情の制御ができずに他人に敵意や嫉妬を抱きやすくなってしまいます。
そのため、他人の不幸は蜜の味と感じるようにならないために、日々しっかりとしたメンタルケアを行うことが重要です。ただ、自力で日々のメンタルケアを効率的に行うのは、なかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
他人の不幸は蜜の味は個人差はあるが当たり前
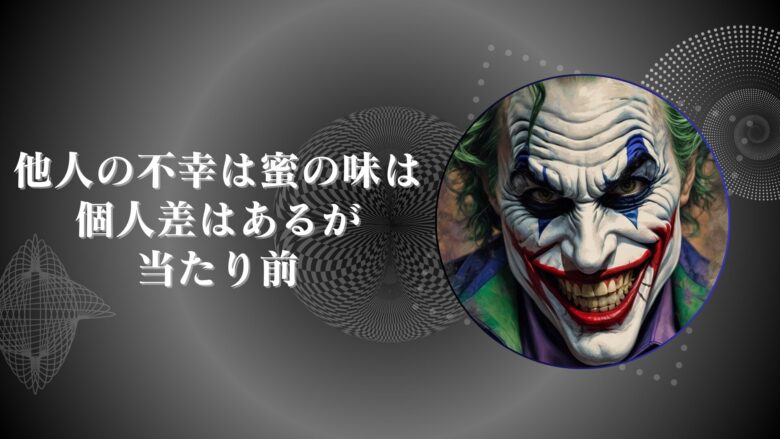
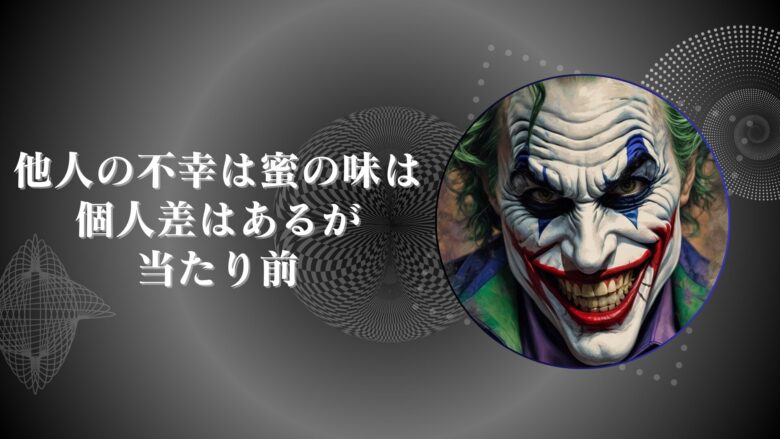



他人の不幸は蜜の味は、当たり前なん?



残念ながら、当たり前なんよね。
「他人の不幸は蜜の味」ということわざは、「他人の不幸や失敗を見て喜んだり、面白がったりする心理状態のこと」を意味しますが、これはすべての人間に普遍的な心理現象です。なお、心理学では、この現象は「シャーデンフロイデ(ドイツ語)」と呼ばれていますね。
ちなみに、以下のfMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いた研究では、シャーデンフロイデを感じるとき、脳の報酬系(例:線条体)が活性化することが示されています。これはシャーデンフロイデが人間にとって、一般的な心理現象であることを裏付ける脳科学的な側面からの証拠といえるでしょう。
参考:When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain: Neural Correlates of Envy and Schadenfreude
ただ、この心理現象の発現に関しては、かなり個人差があるのも事実です。詳しくは後述しますが、共感力や自己肯定感の高い人シャーデンフロイデが抑制されるといわれています。
参考:ERP Effects of Malicious Envy on Schadenfreude in Gain and Loss Frames
また、この心理現象の発生には文化的な要因も影響しているとされており、集団主義的な文化(日本など)では、個人主義的な文化に比べ、他人への共感がシャーデンフロイデを抑える傾向にあるそうです。
ただ現代では、SNSの普及により他人の不幸(例: 炎上、失敗投稿)が可視化されやすくなったことで、日本でもシャーデンフロイデが表面化しやすくなってきているのが現状です。実際、炎上騒動のどさくさに紛れて、他人の不幸で溜飲を下げようとする人間として品性のない行動をする人を、たくさんみかけますからね。



ああ、わかる。いっぱいいるよね。
後述するように、他人の不幸は蜜の味、つまりシャーデンフロイデはおもに嫉妬から生じる心理現象ですが、自身の正義感や道徳観から逸脱した人物の苦しむさまに対してもよく発生するものです。実際、あなたも犯罪者や過去に嫌なことをした人物がダメージを受けているのを見て、「ざまあ!」と思った事があるでしょう。
なお、進化心理学では、この心理現象は集団内で規範違反者を罰する感情が生存に有利だったとから、現在も残っていると考えられていますね。規範違反者の失敗を喜ぶこの心理現象が、集団のルールを強化し協力的な社会を維持する役割を果たした可能性があるというわけです。
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の4つの特徴
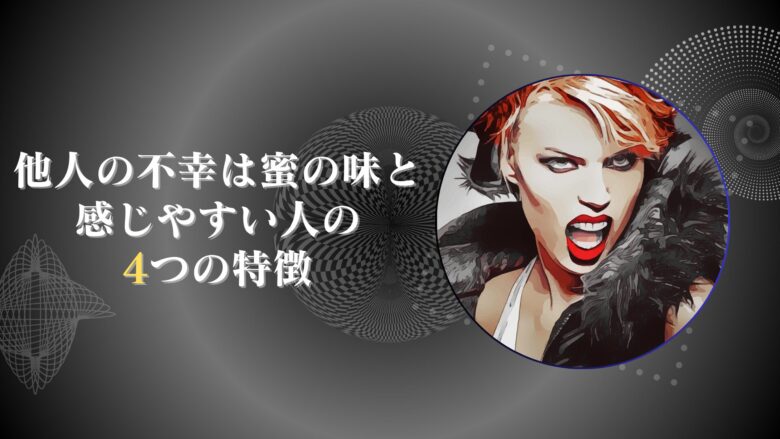
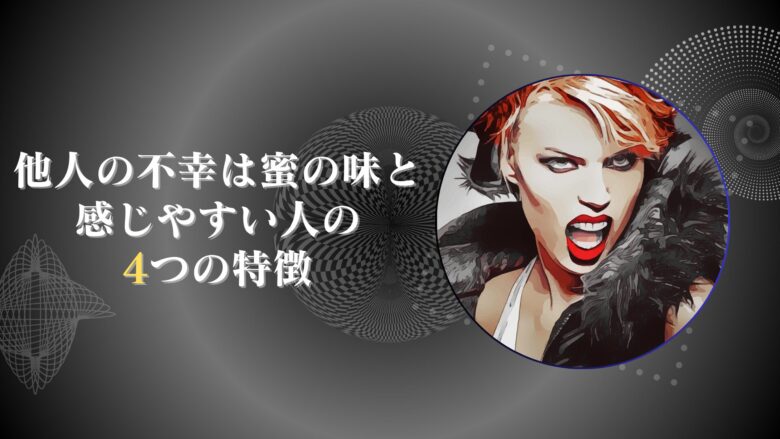



他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴は?



特徴は、以下の4つやね。
つぎは、他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴について、見ていきたいと思います。他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴は、以下の通りです。
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴
- 特徴①:嫉妬心が強い
- 特徴②:競争意識が高い
- 特徴③:共感力が低い
- 特徴④:自己肯定感が低い



それぞれ、詳しく見ていこう!
特徴①:嫉妬心が強い
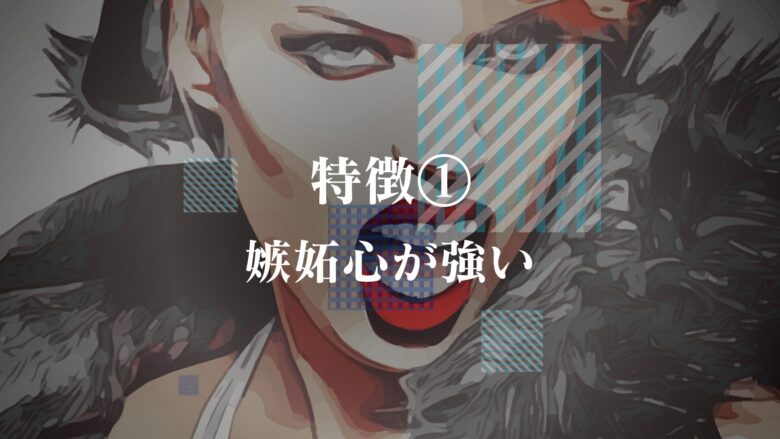
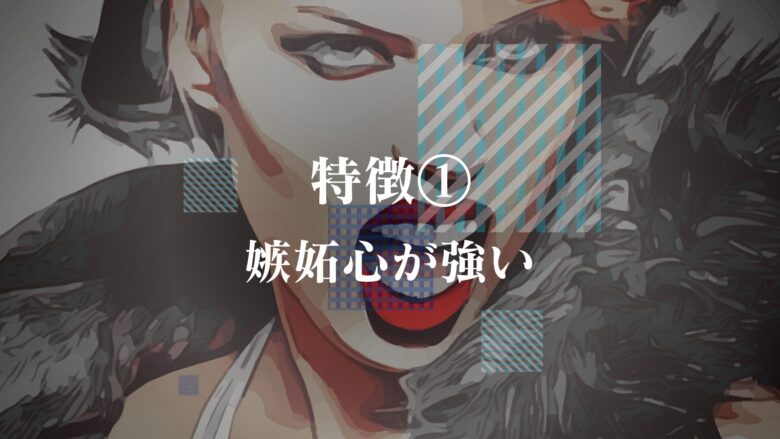
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴としては、まず「嫉妬心が強いこと」があげられます。
嫉妬は、シャーデンフロイデの主要なトリガーとなる感情です。ちなみに、以下の研究では他人に嫉妬している場合、その嫉妬対象たる人の失敗が「正義の回復」と感じられ、喜びを引き起こすことが確認されています。
参考:The Roles of Disliking, Deservingness, and Envy in Predicting Schadenfreude
特に、SNSで他人の成功(例: 豪華な生活の投稿)を見た後、その人の失敗を知ると強いシャーデンフロイデが生じやすいとも言われていますね。おそらく、これは心当たりがある方もいるのではないでしょうか?



んー、心当たりありすぎてつらい!
ただ、嫉妬心は適切に活用すれば、自己成長の起爆剤となるので全面的に否定するような感情ではなかったりします。嫉妬心の自己成長への適用などについて、詳しく知りたい方は以下の記事を見てみてくださいね。
参考:嫉妬 付き合い方
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人ほど嫉妬心が強い
特徴②:競争意識が高い
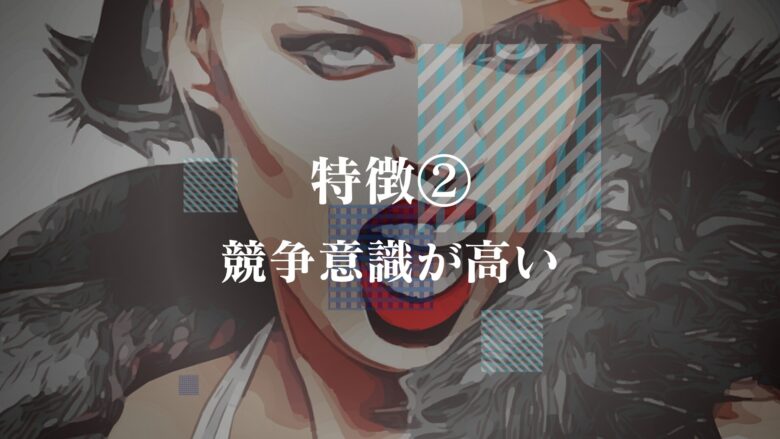
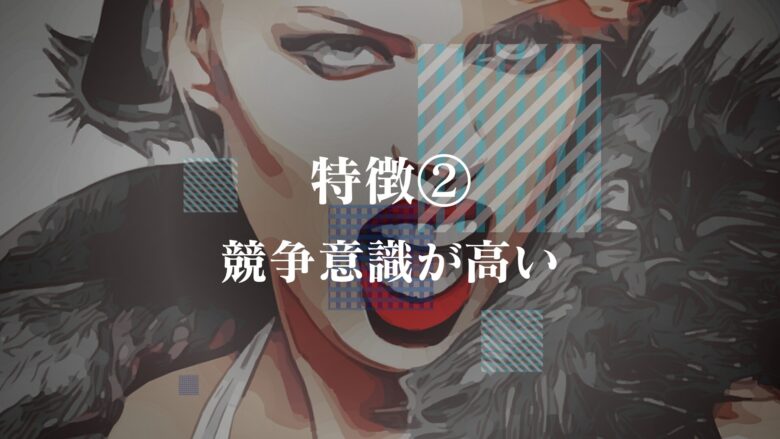
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴として、「競争意識が高いこと」もあげられます。
競争環境に身を置く人は、他人を「ライバル」と見なし、その失敗を喜ぶ傾向があることが確認されています。例えば、以下のの研究では、スポーツファンや職場での競争者が相手チームや同僚の失敗に喜びを感じる脳活動が確認されていたりしますね。
参考:Us versus them: Social identity shapes neural responses to intergroup competition and harm.



、、、これも心当たりあるぞ、、。
これは進化的視点からは、資源や地位の競争が背景にあると考えられます。つまり、ライバルが失敗する事で、自分がそのライバルが成功していれば獲得するはずだった資源等が獲得できるチャンスが巡ってくるので、ライバルの失敗で快感を得てそれをトリガーにして資源獲得を目指す、、というわけです。
性格が悪いと理性的には感じてしまう仕組みではありますが、生存するための本能ととらえるのであれば、利にはかなっていますよね、よくもわるくも。
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人ほど嫉妬心が強い
特徴③:共感力が低い
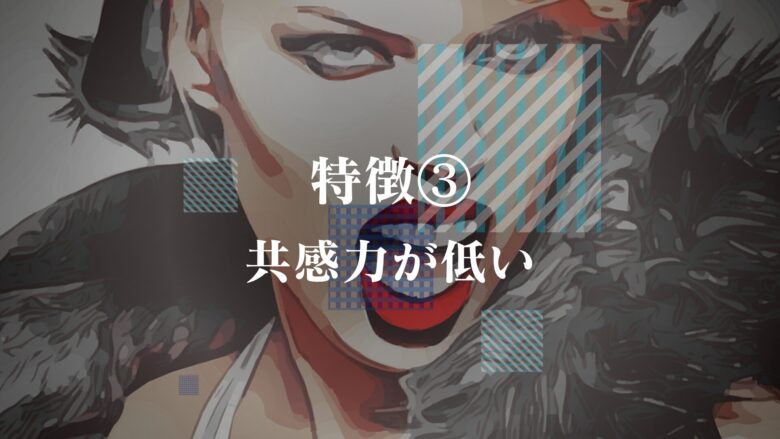
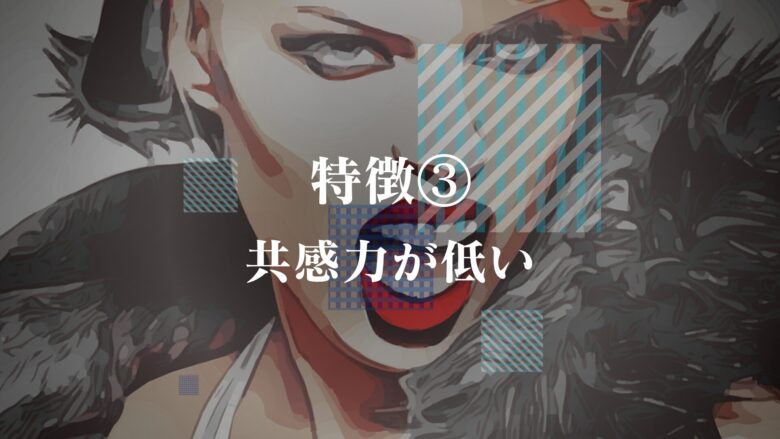
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴として、「共感力が低いこと」もあげられます。
共感力が低い人は、他人の苦しみに感情的に共感できず、シャーデンフロイデを感じやすくなる傾向にあるといされています。事実、以下の研究では、共感に関わる前頭前皮質の活動が低い人は、他人の不幸に対する喜びを抑制しにくいことが示されていますね。
参考:Impaired empathy following ventromedial prefrontal brain damage.



共感が低いと、他人の不幸は蜜の味になりやすい、、なぜ?
なぜ共感が低いとシャーデンフロイデが発生しやすいかについては、共感が倫理的判断を強化する役割を果たすからと考えられているようです。
実際、程度の差はあるでしょうが、どんな悪人に対しても一定数同情の念を、抱いてしまう人はいますよね。そういった現実の事例を考えると、共感力の高さとシャーデンフロイデの起こりやすさの関係性について、ある程度納得がいくかと思います。
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人ほど競争意識が高い
特徴④:自己肯定感が低い
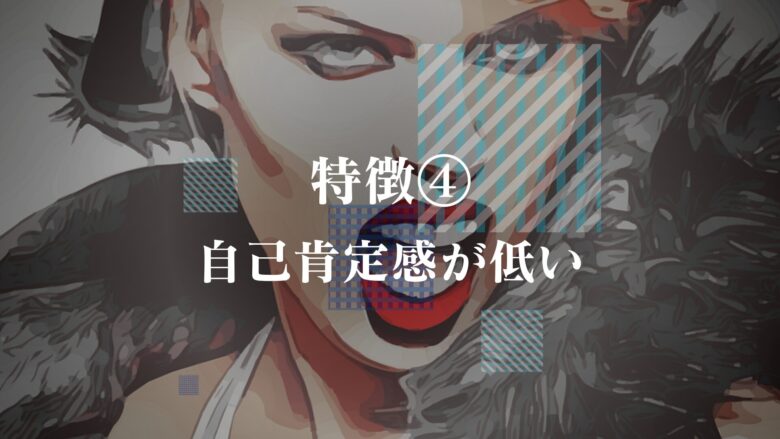
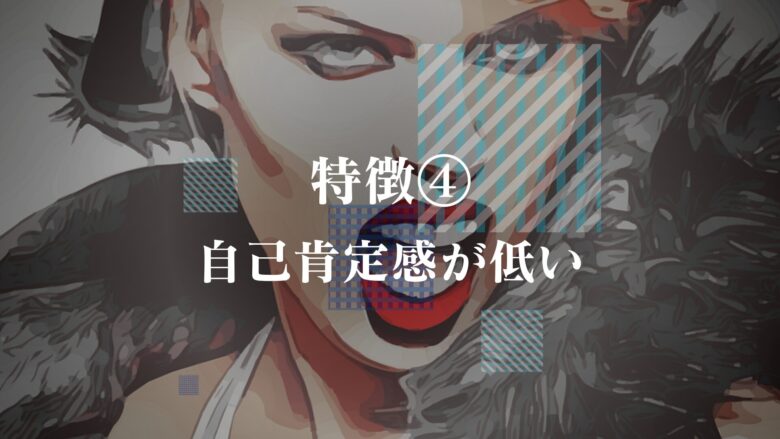
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人の特徴として、「自己肯定感が低いこと」もあげられます。
自己肯定感が低い人は、他人の失敗を通じて一時的に自己の価値を感じようとする傾向にあるといわれます。つまり、他人の失敗をみて「自分の置かれている状況の方がまだまし」等と感じる事で、優越感を感じようとしているといえるわけです。



んー、わかるなあ、この心理醜いよなあ。
なお、以下のの研究では、低い自己肯定感がシャーデンフロイデの強度を高める、特に競争相手の失敗に対して強い喜びを感じると報告されていたりします。
正直、「自分より下の人間を見て仮初の優越感を感じる」という心理とかなり似通った現象とえますね。客観的に見ると、醜い事はなはだしいですが、自分の心を外圧から守るためのある種の防衛機制だと思えば納得もいくというものでしょう。
他人の不幸は蜜の味と感じやすい人ほど嫉妬心が強い
他人の不幸は蜜の味と感じないための3つの備え





他人の不幸は蜜の味と感じないためには、どうしたらええん?



それなら、以下の3つの備えをしておくのがおすすめや!
前述のように、他人の不幸は蜜の味と感じるのは、人間の本能に根差した心理です。そのため、人間であれば誰もがみなこの忌々しい心理を発現するリスクを、抱えて生きているという事になります。とはいえ、他人の不幸は蜜の味といった心理に陥ることを防止するための対策もきちんとあるので大丈夫です。
ということで、つぎは、他人の不幸は蜜の味と感じないための備えについて、見ていきたいと思います。他人の不幸は蜜の味と感じないための備えは、以下の通りです。
他人の不幸は蜜の味と感じないための3つの備え
- 備え①:自分軸を確立する
- 備え②:感謝の習慣を育む
- 備え③:共感力を鍛える



それぞれ、詳しく見ていこう!
備え①:自分軸を確立する
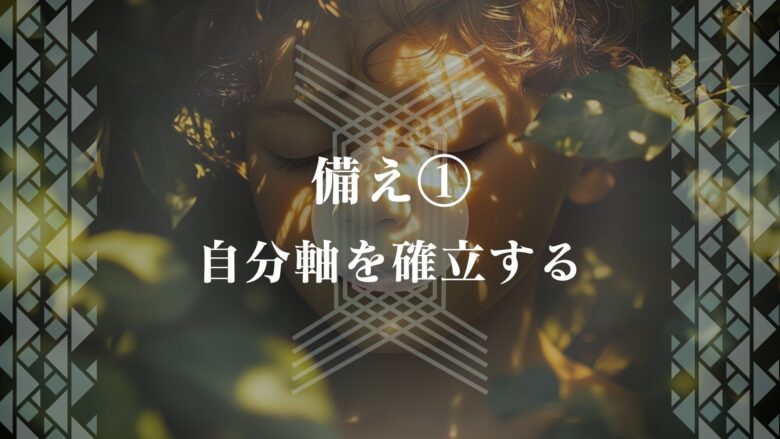
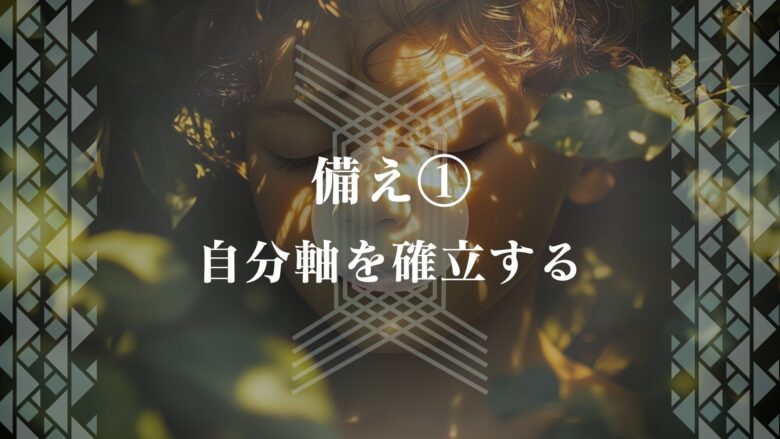
他人の不幸は蜜の味と感じないための備えの1つ目は、「自分軸を確立すること」です。
先ほどふれたように、自己肯定感の低さはシャーデンフロイデの元凶の1つですから、自己肯定感をあげてしまえば、自然とシャーデンフロイデが発生しにくくなるといえます。そこで、個人的に一番おすすめしたいのが、自分軸の確立、つまり「自分の大事にしたいものを見つけそれに沿って生きる生き方をすること」です。



自分軸が確立されれば、いい意味で他人に関心なくなりそうだね。
自分軸が確立されれば、他人がどういった行動をしているかやどう評価されているかに惑わされず、自分の人生に集中できるようになります。そうすれば、いい意味で他人には無関心になれるので、他人の不幸は蜜の味だと感じるような事態は激減すること請け合いです。
自分軸を確立したい方は、以下の記事を見てみてくださいね。手間はかかりますが、得るものはきっと多いはずです!
備え②:感謝の習慣を育む
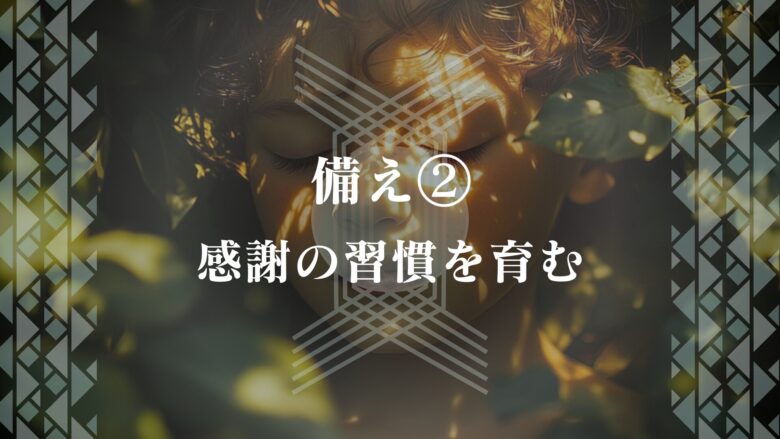
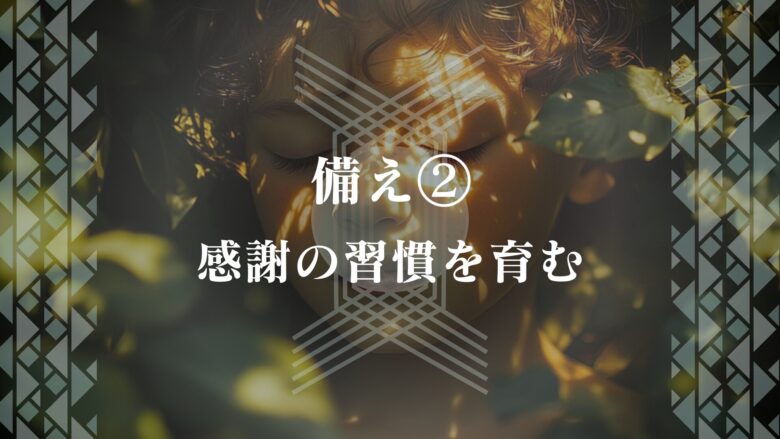
他人の不幸は蜜の味と感じないための備えの2つ目は、「感謝の習慣を育むこと」です。
感謝の実践は、他人との比較や嫉妬を減らしポジティブな感情を増強しますし、間接的に自己肯定感の向上にも役立ちます。先ほどふれたように、嫉妬や低い自己肯定感は、シャーデンフロイデの元凶でしたから、他人の不幸は蜜の味と感じる事を防止するために感謝の実践は有効といえるでしょう。



ふむ、感謝の実践、、具体的にはどうするん?
感謝の実践方法としては、具体的には、感謝日記をつけるのがおすすめです。実際、以下の研究では、感謝日記を書くことで自己肯定感が向上し、他人への敵意が減少することが示されていますね。
感謝日記をつける際は、以下の事に気を付けて実践しましょう。
- 毎日、感謝できる3つのことを書き出す(例: 家族の支え、仕事の成功)
- 他人の成功を「自分も刺激を受けた」と再解釈し、ポジティブな視点を持つ
- SNSで他人の投稿を見たとき、嫉妬を感じたら「その人の努力を認める」コメントを意識的に残す
備え③:共感力を鍛える
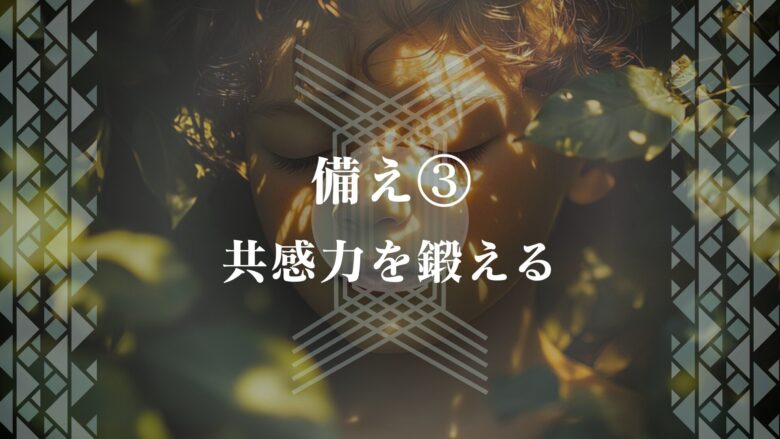
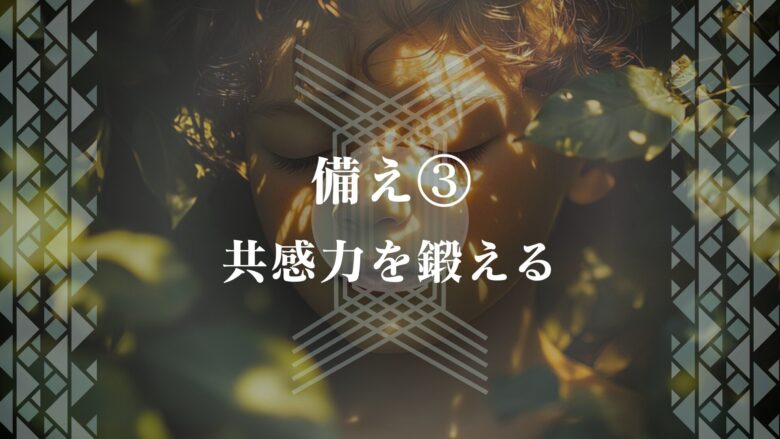
他人の不幸は蜜の味と感じないための備えの3つ目は、「共感力を鍛えること」です。
前述のように、共感力を高めることが、他人の不幸は蜜の味と感じる事への抑止力となります。ただ、人によっては「共感力は生まれつきで、強化などできないのでは?」と思うかもしれません。しかし、そこは大丈夫です。



んで、共感力を上げる具体的な方法は何なん?
以下の研究では、共感はトレーニングで強化可能で、特に視点取得(他人の立場に立つ)練習が共感力の強化に有効とされています
なお、共感力強化の具体的な方法は、以下の通りです。できる事から、少しづつ取り組んでみるといいでしょう。
共感力強化の具体的な方法
- 他人の失敗を見たとき、「その人がどんな気持ちか」を想像する(例: 「失敗したときの悔しさは自分も経験したことがある」)。
- 積極的にリスニングスキルを磨き、相手の話を否定せず理解する姿勢を持つ。
- ボランティア活動や対話の機会を増やし、他人の感情に触れる経験を積む。
他人の不幸は蜜の味に関するFAQ





他人の不幸は蜜の味に関して、まだ気になる事があるんよ。



んじゃ、最後に疑問にこたえていこうかの!
最後に、他人の不幸は蜜の味に関連する疑問について、回答していきたいと思います。
FAQ①:シャーデンフロイデを感じるのは異常?
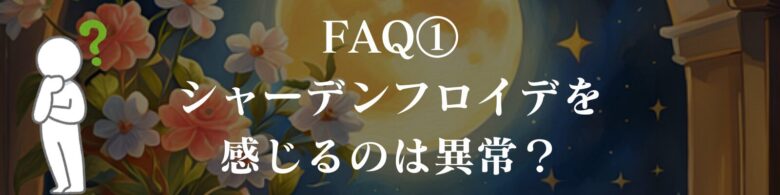
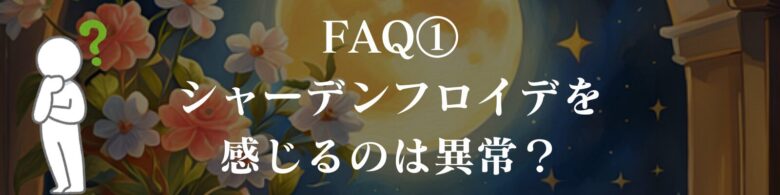
シャーデンフロイデは人間の自然な感情なので、異常ではありません。なお、進化心理学では、生存や地位競争の中で生じた適応的反応と考えられています。
FAQ②:SNSで他人の不幸を喜ぶ人が多いのはなぜ?
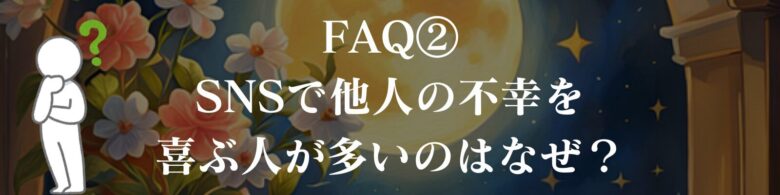
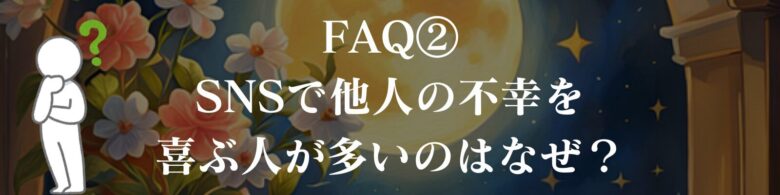
SNSは他人の成功や失敗を非常にわかりやすく可視化するため、比較や嫉妬を増幅する装置と化しています。
事実、以下の研究では、SNSの利用が社会比較を強化し、シャーデンフロイデを誘発しやすいことが示されていますね。
FAQ③:シャーデンフロイデを完全に無くすことは可能?
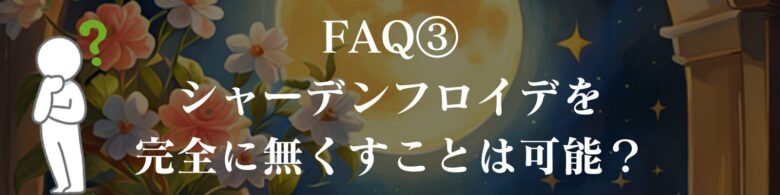
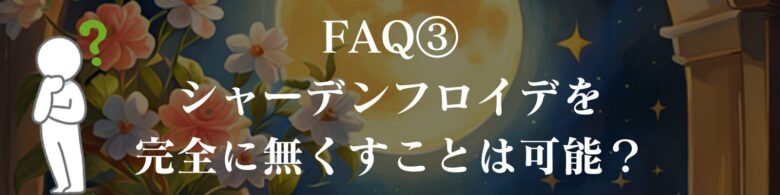
シャーデンフロイデを完全になくすことは、まず不可能です。ただ、先ほどふれたような備えを行うことで、かなりその発生頻度を減らすことは可能でしょう。
ちなみに、以下の研究によれば、、利他行動(例: 寄付、助け合い)が脳の報酬系を活性化し、シャーデンフロイデを抑制するといわれていますね。
参考:Neural responses to taxation and voluntary giving reveal motives for charitable donations
日常的に他人への親切を実践することも有効なので、他人に努めて親切にする習慣を日常に取り入れてみるのもおすすめです。
他人の不幸は蜜の味と感じるのは本能!しかし努力でシャーデンフロイデは防止できる!


他人の不幸は蜜の味と感じるのは、もはや本能です。しかし、その発生リスクと程度にはかなり個人差がありますし、きちんと対策をすればその発生を防止する事も十分可能といえます。特に、自分軸の確立は、他人への嫉妬を制御するために非常に効果的でしょう。
ただ、自分軸の確立にしても共感性の向上にしても、安定したメンタルがあることが大前提といえます。メンタルが不安定では、他人に対して無駄に敵意や嫉妬心を感じやすくなってしまいますからね。他人の不幸は蜜の味、、と思わないようにするためには、日々のメンタルケアの徹底が欠かせないのです。



日々のメンタル管理は、きちんとしようぞ!
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)から利用で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、ファッションを存分に楽しむための下地を整えていきましょう!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\