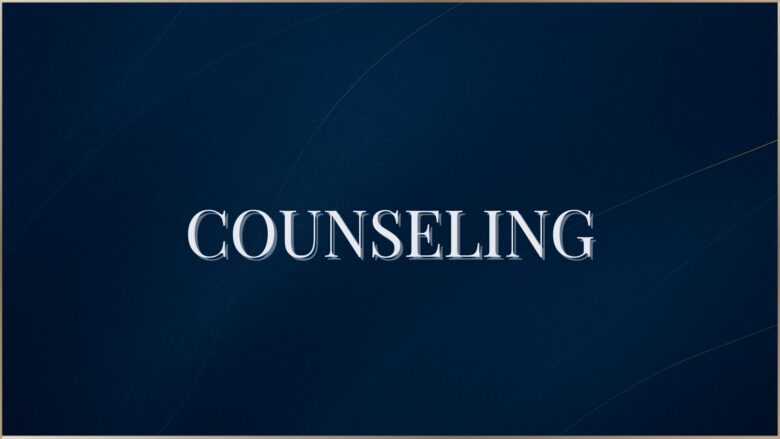おにぎり
おにぎりものと大切にする人の心理について、気になるんよ。



ものを大切にする人の心理は、おもに以下の3つやね。
ものを大切にする人は一般的に、人格者であるとされる風潮があります。とはいえ、彼らの性格や心理の実態は他者からうかがい知ることができません。それに、中にはものを大切にしているくせに、あまり人を大事にしていないように見える人もいるものです。
そんな感じですから、ものを大切にする人の心理について、気になりますよね?結論から言うと、ものを大切にする人の心理としては、おもに以下の3つがあげられます。
もの大切にする人の心理
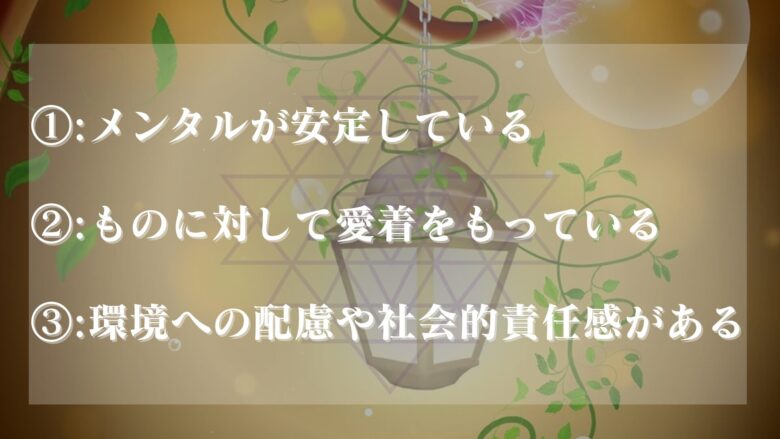
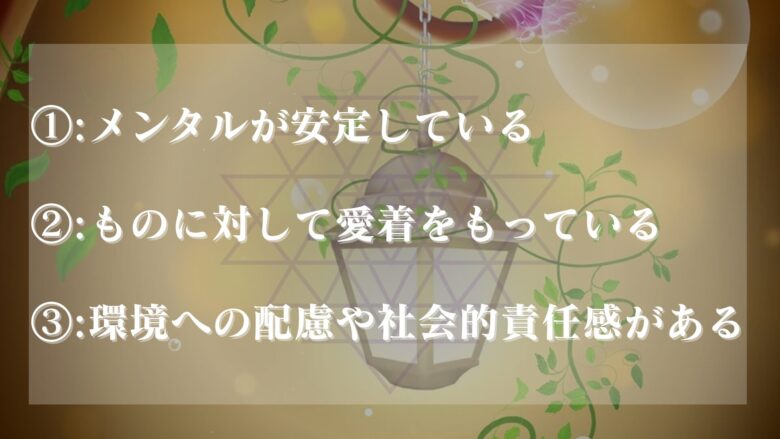



ものに対して愛着を持っている人が、一番多い印象あるね。
ものを大切にする人は、全体的にメンタルが安定しておりかつ、ものに愛着を持っている傾向があるように感じます。ただ、ものを大切にするのと執着するのは紙一重な部分もあり、その点には注意が必要です。ものを大切にするのはいい事ですが、ものに執着するのは人生において有害といえます。
そのため、ものを大切にするようになりたい方は、日々のメンタルケアにもきちんと気を配った方が良いでしょう。日々のこまめなメンタルケアが、ものへの執着を防止してくれます。とはいえ、自力で日々のメンタルケアを効率的に行うのはなかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyを利用してみてくださいね!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
ものを大切にする人の3つの心理





ものを大切にする人の心理について、教えて!



あいよ!ものを大切にする人の心理は、以下の3つや!
まずは、ものを大切にする人の心理について、見ていきたいと思います。ものを大切にする人の心理は、以下の通りです。
ものを大切にする人の心理
- 心理①:メンタルが安定している
- 心理②:ものに対して愛着をもっている
- 心理③:環境への配慮や社会的責任感がある



それぞれ、詳しく見ていこう!
心理①:メンタルが安定している


ものを大切にする人の心理としては、まず「メンタルが安定していること」があげられるでしょう。
もの大切にする傾向は、心理学の文脈においては所有物を管理することで、コントロール感を得ようとする傾向ととらえることが可能です。



まあ、、うん、ちょっとこじつけっぽけど分かった。
精神的な安定のためには、自己効力感やコントロール感が重要とされているため、ものを大切にしようとする人の精神状態は比較的安定している可能性があります。
ちなみに、以下の研究では物を丁寧に扱い整理整頓することで、環境に対するコントロール感が高まり、不安が軽減されることが示唆されていますね。
参考:For better or worse? Coregulation of couples’ cortisol levels and mood states.
ものを大切にする人はメンタルが安定している
心理②:ものに対して愛着をもっている


ものを大切にする人の心理としては、「ものに対して愛着をもっていること」もあげられるでしょう。
物を大切にする人は、ものに対して愛着をいだいている傾向があり、心理学の愛着理論を応用すれば、ものは単なる道具ではなく記憶やアイデンティティの一部として機能しているといえます。



なるほど、ものがアイデンティティの一部になるんか。
例えば、祖父母から受け継いだ時計や長年使った鞄にはストーリーや感情が宿り、所有者にとって自分らしさを象徴する存在になるでしょう。実際、以下の研究では、ものに対する愛着が自己表現や安心感に寄与することが示されています。
なお、日本には八百万の神、つまり森羅万象あらゆるものに神が宿るとされるアニミズム的な信仰が古来よりあるので、日本人の場合、ものへの愛着形成はこの信仰の影響を大きく受けていそうですね。
ものを大切にする人はものに対して愛着をもっている
心理③:環境への配慮や社会的責任感がある
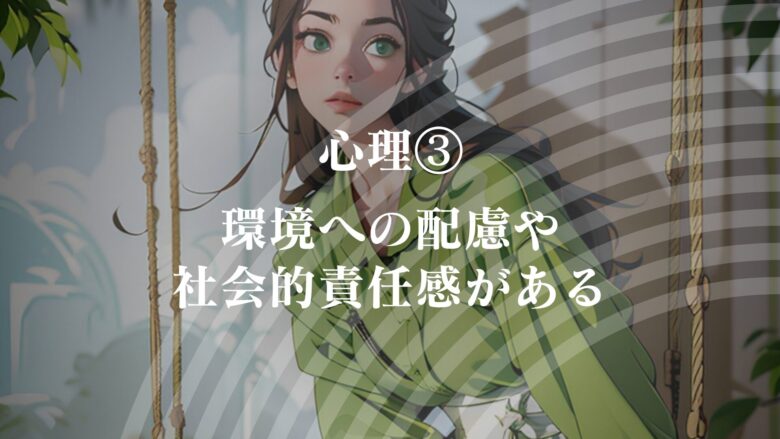
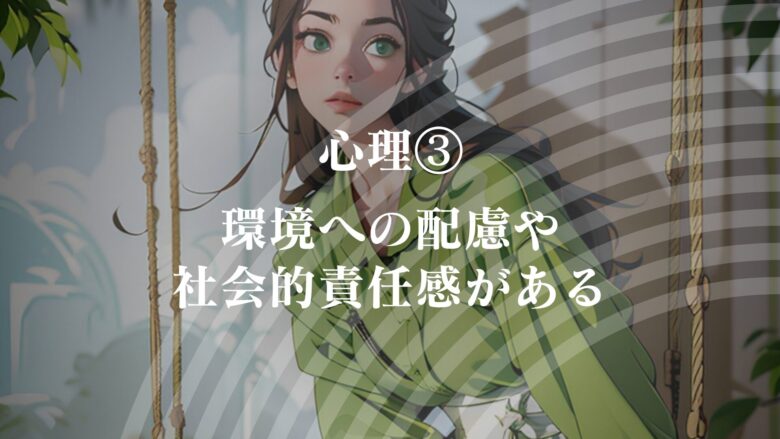
ものを大切にする人の心理としては、「環境への配慮や社会的責任感があること」もあげられるでしょう。
ものを大切にする行動は、環境意識や社会的責任感にもとづいておこなわれている場合もよくあります。いってみれば、これは利他心の延長のような思想に基づいた行動といえるかもしれません。



たしかに、最近サステナビリティとかよく話題になるよね。
ちなみに、こうしたプロソーシャル行動(他人や社会のための行動)は自己効力感や幸福感を高めるとされているので、メンタルヘルス上有益といえますね。
物を長く使うことは、廃棄物を減らし、環境負荷を下げる行為であり、特に若い世代ではサステナビリティへの関心からこの行動が見られます。日本では「もったいない」精神がこの心理を後押しし、物を大切にすることが社会への貢献と結びついています。
ものを大切にする人は環境への配慮や社会的責任感がある
ものを大切にする人が人も大切にするとは限らない2つの理由
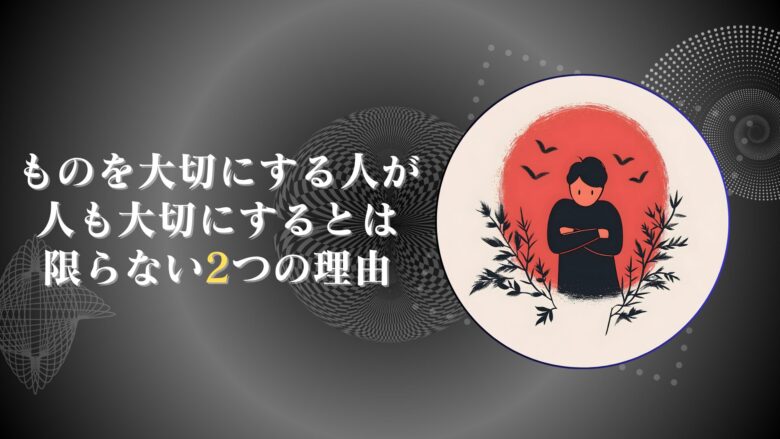
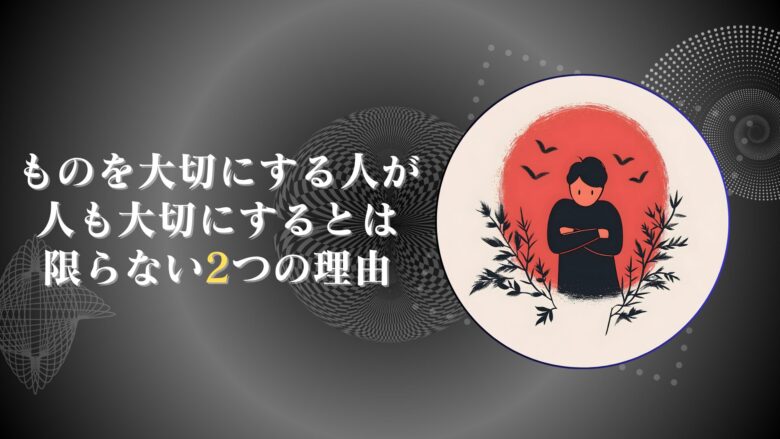



ものを大切にする人は、人も大切にするん?



必ずしも、そうではないんだよねえ。
一般に、「ものを大切にする人は人も大切にする」といわれていますが、これは必ずしも正しくありません。その理由は、以下の通りです。
ものを大切にする人が人も大切にするとは限らない2つの理由
- 理由①:ものへの愛着が対人関係の優先度を下げることもある
- 理由②:人もものもえり好みしていることがある



それぞれ、詳しく見ていこう!
理由①:ものへの愛着が対人関係の優先度を下げることもある
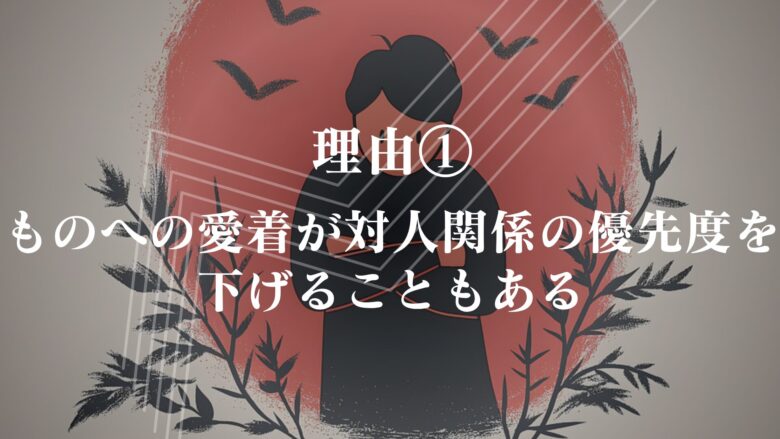
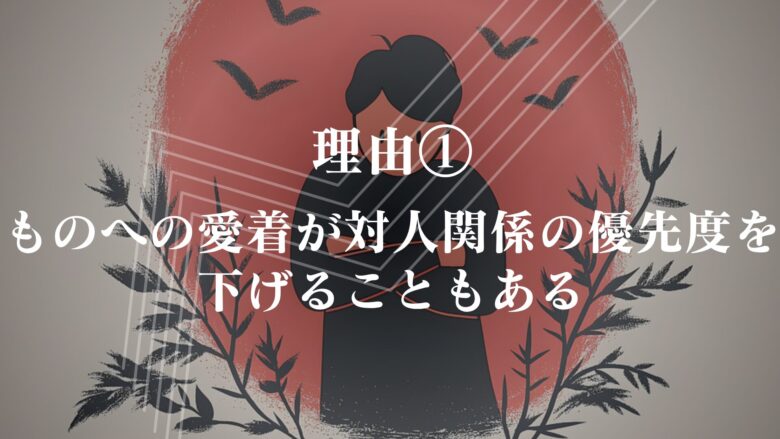
ものを大切にする人が人も大切にするとは限らない理由としては、まず「ものへの愛着が対人関係の優先度を下げることもある」というものがあげられます。
ものを大切にする人の中には、ものへの愛着が強いあまり、対人関係よりもものとの関わりに時間やエネルギーを割く人もままいるものです。



なるほど、もの優先になってしまうって感じか。
ちなみに、このような現象は心理学の資源配分理論によって、説明できるでしょう。この理論によれば、人は限られた心理的リソース(時間、注意力など)をどこに注ぐかを選択するとされています。
参考:Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress.
つまり、ものへの強い愛着は、対人関係へのリソース配分を減らし、他人への共感や関心が薄れる可能性があるということです。
例えば、コレクターが自分の収集品に没頭する一方で、家族との時間を後回しにする、、、といったケースがこれに該当するといえます。
理由②:人もものもえり好みしていることがある
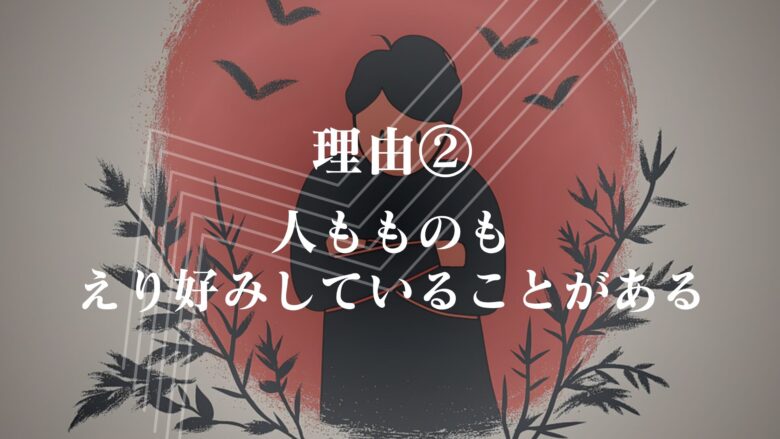
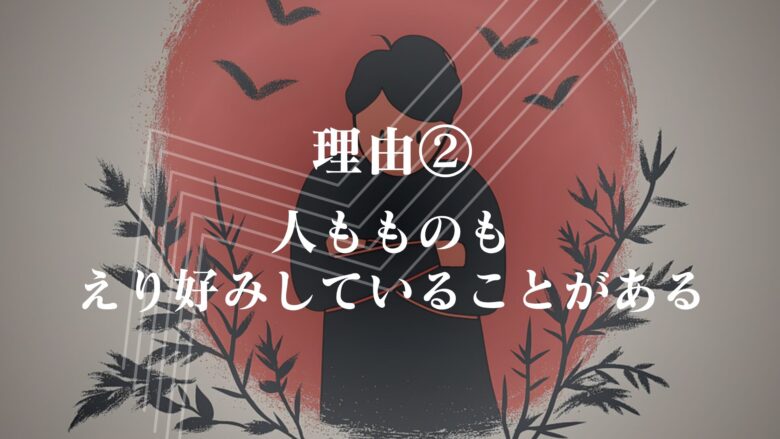
ものを大切にする人が人も大切にするとは限らない理由としては、「人もものもえり好みしていることがある」というものもあげられます。
誰にでも好き嫌いはあるので、「~は大切にしたいけど~は嫌いだから大切にはしない」等といった選別を行うのが割と普通です(特に女性に多い印象)。



まあ、好き嫌いがあるから仕方ないところもあるよね。
実際、人はすべての物に均等に愛着を持つわけではなく、特定の物に対して選択的に愛着を形成するとされています(選択的愛着)
上掲の研究によれば、ものへの愛着は、そのものが個人のアイデンティティ、記憶、または価値観をどれだけ反映しているかに依存していることが示唆されています。
つまり、当人の価値観に合わないものは、心理的に「自分と無関係」とみなされ、愛着の対象から外れるため、粗末に扱われやすいということです。例えば、 家族から受け継いだアクセサリーは大切にするが、100円ショップで買った使い捨ての食器は気軽に捨てる、、といった感じですね。
ものを大切にすることにより得られるメリット





ものを大切にすることで、得られるメリットには何があるん?



主にメリットは、3つあるね。
つぎは、ものを大切にすることにより得られるメリットについて、ふれていきたいと思います。ものを大切にすることにより得られるメリットは、以下の通りです。
ものを大切にすることにより得られるメリット
- メリット①:メンタルヘルスの向上
- メリット②:経済的節約
- メリット③:人間関係の深化



それぞれ、詳しく見ていこう!
メリット①:メンタルヘルスの向上


ものを大切にすることにより得られるメリットの1つ目は、「メンタルヘルスの向上」です。
ものを大切にする行動は、前述のようにコントロール感や自己効力感を高めることで、ストレスを軽減します。



ふむふむ。
事実、環境心理学の研究では、整理整頓された環境が不安や抑うつの軽減に寄与するとされていますね。
参考:Interactions of top-down and bottom-up mechanisms in human visual cortex
ものを丁寧に扱う習慣は日常生活の秩序を向上させることによって、精神的な安定がもたらされるといえます。
メリット②:経済的節約


ものを大切にすることにより得られるメリットの2つ目は、「経済的節約」です。
当たり前ですが、ものを長く使うことは、経済的メリットにも直結します。実際、消費行動に関する研究では、修理や再利用を重視するライフスタイルが家計の節約につながるとされていますね。
参考:Analysis of high intensity activity in Premier League soccer



やっぱり、今のご時世、節約は大事よな。
ちなみに、個人的にお気に入りの茶わんなどが割れてしまった場合に、金つぎをして利用し続けるのはいい方法だと思います。
なお、何をもって「ものを大切にする」と定義するかは人によるので何とも言えないところがありますが、少なくとも個人的には「ボロボロになってもずっと使い続ける」のはあまりものを大切にしてることに該当しないのかなと思ったりしますね。
メリット③:人間関係の深化


ものを大切にすることにより得られるメリットの3つ目は、「人間関係の深化」です。
ものを大切にする行動は、共感や感謝の意識を育み、間接的に人間関係を強化することにつながります。これはまさに「ものを大切にする人は人も大切にする」という俗説を、補強する内容といえるでしょう。



たしかに、そうね。
ちなみに、ポジティブ心理学の研究では、感謝の習慣が対人関係の満足度を高めるとされています。ですので、贈りものに対して、それをくれた人への感謝の気持ちをもって丁寧に扱う習慣をつける事は、当該送り主との関係を良好にすることつながるといえるでしょう。
ものを大切にする習慣を身につけるための3つの注意点





ものを大切にする習慣を身に着ける上で、気を付けることは?



以下の3つには、気を付けよう!
つぎは、ものを大切にする習慣を身につけるための注意点について、ふれていきたいと思います。ものを大切にする習慣を身につけるための注意点については、以下の通りです。
ものを大切にする習慣を身につけるための注意点
- 注意点①:小さな行動から始める
- 注意点②:ものに執着しない
- 注意点③:周囲と価値観を共有する



それぞれ、詳しく見ていこう!
注意点①:小さな行動から始める
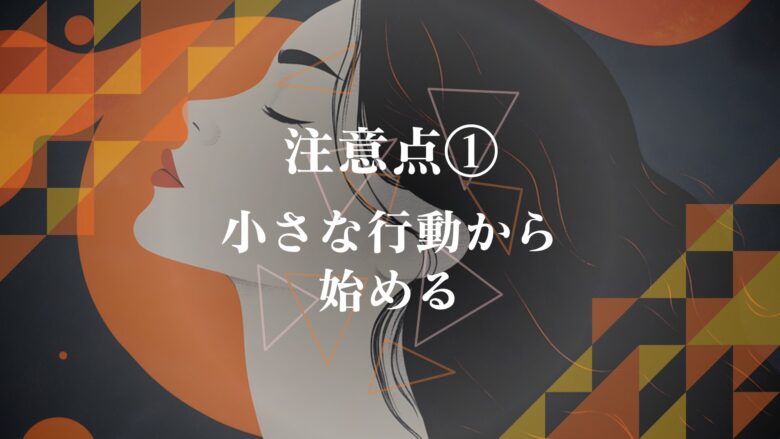
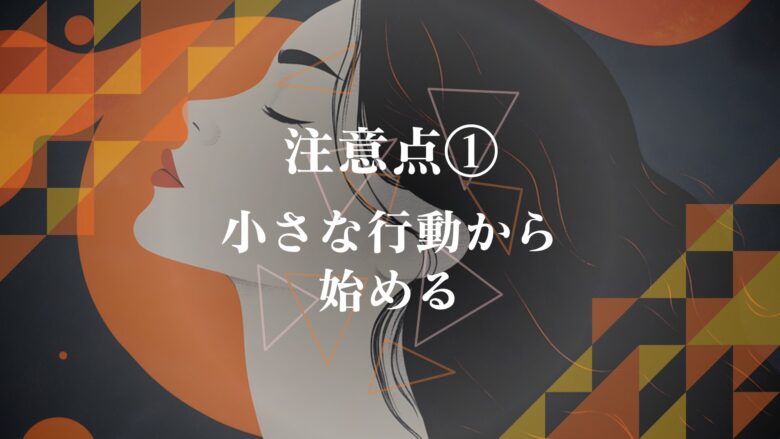
ものを大切にする習慣を身につけるため注意点の1つ目は、「小さな行動から始める」ということです。
ものを大切にするようになりたいと思っても、いきなり大きく行動を大きくかえるのはおすすめしません。もし、そんな自分史上の大改革のような事をしようとしても、十中八九途中でできなくなってすぐにやめてしまいます。



、、、なんか、身に覚えがありすぎる、、、。
ものを大切にするようになりたいのであれば、毎日少しづつ小さな行動を積みかさねるようにしたいものです。事実、行動変容の研究では、小さな成功体験が習慣形成に有効であるとされていますしね。
参考:(Lally et al., 2009)。
例えば、ものを大切にするといっても、以下の様に簡単な事から始めればオッケーです。
- 扉を静かにしめるようにする
- 靴のかかと部分をつぶしてはかない
- 皮靴を磨く
- コップを勢いよく置かない
- パソコンの画面を定期的に拭いてきれいにする
- 部屋を定期的に掃除・整理整頓する(うつ病リスクも減るので超大事)
上記の内、掃除・整理整頓に関しては本当に大事ですから、きちんとしたいものです。部屋の掃除やものを整理整頓することは、部屋やものを大切にする事と同義ですし、うつ病リスクとの関連が指摘されていますからね。
参考
Life at Home in the Twenty-First Century: 32 Families Open Their Doors
No place like home: home tours correlate with daily patterns of mood and cortisol
注意点②:ものに執着しない
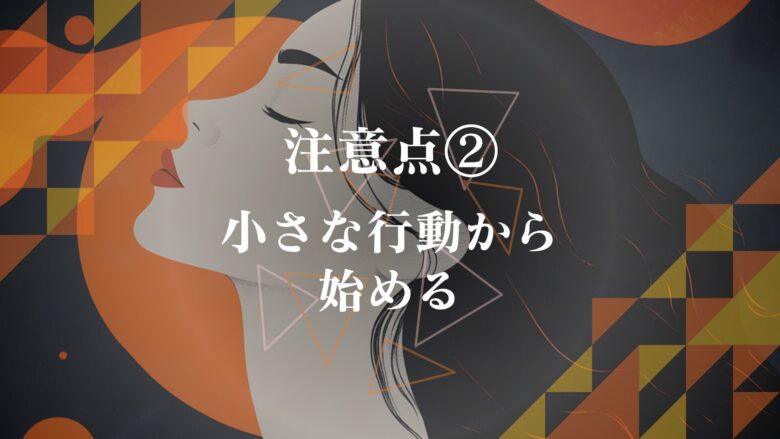
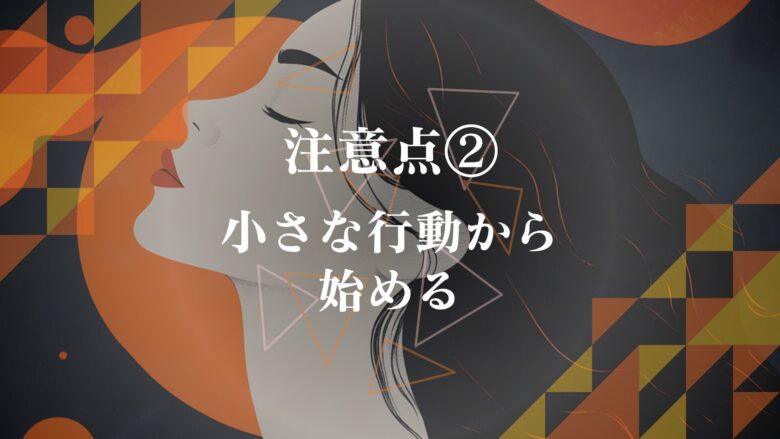
ものを大切にする習慣を身につけるため注意点の2つ目は、「ものに執着しない」ということです。
ものを大切にすることはいい事ですが、「ものに執着する」ことは避けなければいけません。心理学的観点から見た場合、ものを大切にする事と、ものに執着する事の違いは下表のようにまとめられます。
ものと大切にすることと、ものに執着することの違い
| 項目 | ものを大切にする | ものに執着する |
|---|---|---|
| 心理的状態 | 安定・感謝・思慮深さ | 不安・恐れ・依存 |
| 主な動機 | 感謝・思い出・尊重 | 失うことへの恐怖・自己の一部化 |
| 手放すことへの態度 | 状況によっては手放せる | 手放すことが極めて苦痛・拒否 |
| アイデンティティとの関係 | ものに意味を見出すが、自分とは区別している | ものが自己の延長・一体化している |
| 行動パターン | 丁寧に扱い、使い切る、整頓 | 使わなくても溜め込む、過剰に保存 |
| 心理学的背景 | 感謝・マインドフルネスなど | 強迫性傾向・愛着不安・依存性パーソナリティなど |



ふむ、似ているようで全然違うんだね。
なお、ものを大切にしているか、それともものに執着しているかは以下の質問に回答してみる事で、ある程度判断できるでしょう。
- 「なくなったら寂しいが、ありがとうと言って手放せる」→ 大切にしている
- 「捨てようとすると胸が締め付けられる、罪悪感が強い」→ 執着している可能性が高め
「補足」ものを大切にするの定義について
「ものを大切にする」と一言にいっても、いろんな立場がある。
一般に、人が「ものを大切にする」という時、以下の5つの立場のいずれかをとっていることが多い。
- 実践的・行動的立場:物を長く使う・維持する行為
- 心理的・感情的立場:物への愛着や意味づけ
- 倫理的・社会的立場:環境や社会への責任感
- 文化的・伝統的立場:文化や歴史的価値観に基づく行為
- 哲学的・存在論的立場:物と人間の関係性の再定義(ものを通じて自己や世界とのつながりを深める)
注意点③:周囲と価値観を共有する
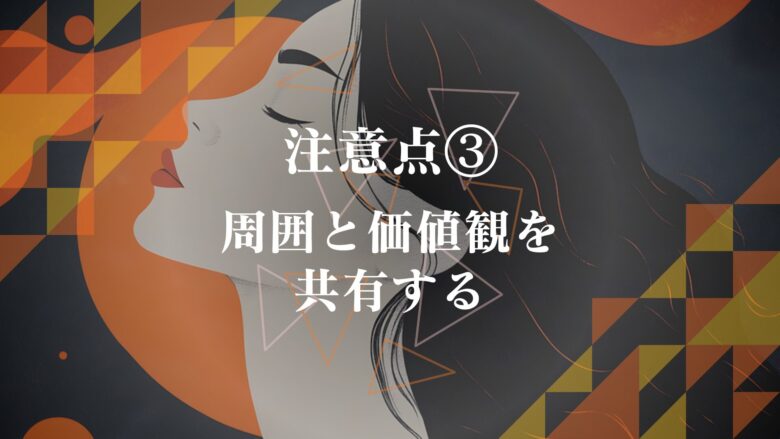
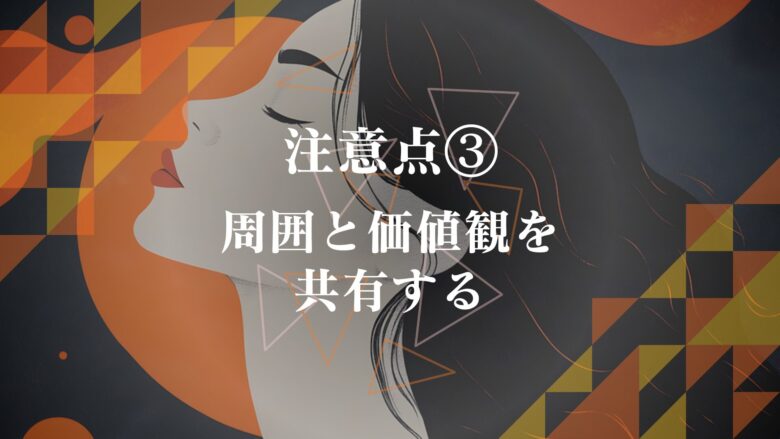
ものを大切にする習慣を身につけるため注意点の3つ目は、「周囲と価値観を共有する」ということです。
これまでから打って変わって、ものを大切にする習慣を身に着けようとしても、自分だけではどうもうまくいかない、、という方も多いでしょう。そんな時は、ものを大切にする価値観を持つ人と関係をもったり、家族や友人と共有する事で習慣化するのがおすすめです。



なるほど、環境の力を借りて習慣を身に着けようって事か。
人は、社会的動物ですから、良くも悪くも環境を変える事で性格や習慣もその環境に影響を受けて変容してきます。事実、社会心理学の研究では、集団での行動が個人の習慣形成を促進するとされていますね。
例えば、修理ワークショップに参加したり、環境意識の高いコミュニティに所属することで、価値観を共有し、習慣を維持しやすくなるでしょう。
ものを大切にすることに関するFAQ





ものを大切にする事について、まだ気になる事があるんよ。



んじゃ、最後に回答していこうかね。
最後に、ものを大切にすることに関する疑問について、回答していきたいと思います。
FAQ①:ものを大切にしすぎるとストレスになる?


物を大切にしすぎることでストレスを感じる場合は、確かにあります。具体的にいうと、例えば、物を捨てられないことによって整理がうまくいかなくなるといったストレスがこれに該当するでしょう。対処法としては、ものに優先順位をつけ、自分の手に負える範囲内でものを所有するようにするのがおすすめです。
FAQ②:ものを大切にする習慣は子供にどう教えたらいい?
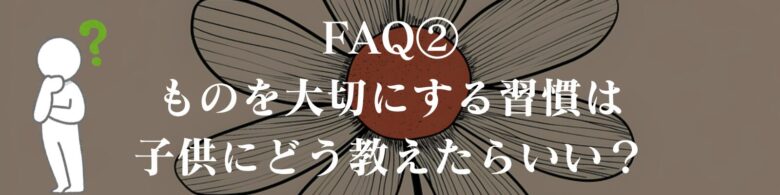
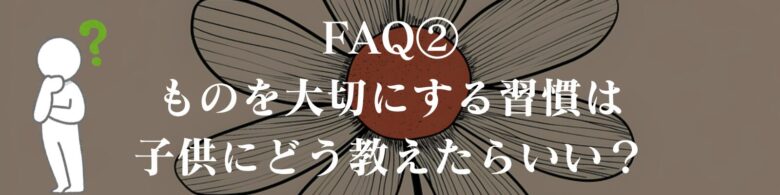
一概には言えませんが、子供に物を大切にする習慣を教えるには、物語を通じて価値を伝えるのが効果的でしょう。例えば、物を修理する様子を見せたり、物にまつわる思い出を話すことで、子供に愛着の大切さを伝える、、といった具合です。
事実、発達心理学の研究では、物語やロールモデルが子供の価値観形成に影響を与えるとされていますね。
参考:Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.
ものを大切にするとメンタルにもよい!習慣化したいなら仲間を作って価値観を共有しよう!


ものを大切にすることは、メンタルにもとても良いことです。ですから、ものを大切にする習慣をみにつけるのは,心穏やかに暮らしたい方にはおすすめといえます。さらにいえば、ものを大切にすることは、経済的節約にもなりますから、一石二鳥です。
ただ、ものを大切にするのはいいですが、ものに対する愛着が過剰になるとものへの執着となってしまうのでその点には注意が必要ですね。例えば、捨てられずにゴミ屋敷になるというのが悪しき状態の最たるものです。そのような執着状態にならないためには、別途日々のメンタルケアを行っていく必要があるといえます。



精神状態が不安定だと、依存が強まりやすいから注意!
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、心軽やかに生きていくための下地を整えていきましょう!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\