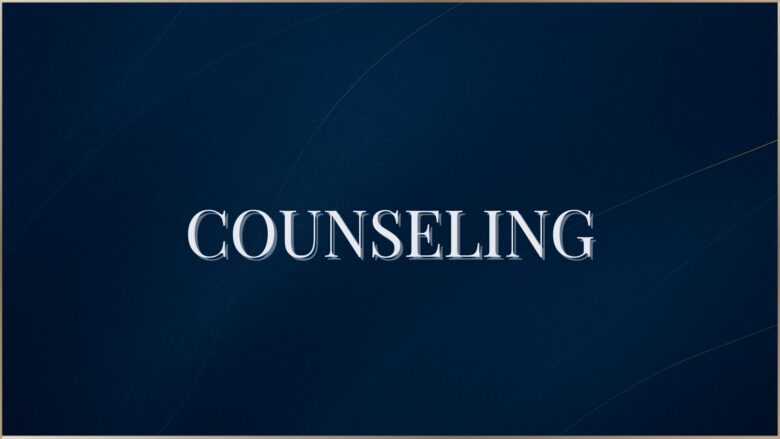おにぎり
おにぎり人は見たいものしか見ないって、誰の名言?



ユリウス・カエサルやね!
心理・自己啓発系発信者たちがよくいく言葉に、「人は見たいものしか見ない」というものがあります。最近のSNSの動向を見てると、思わず「ああ、確かに!」と手をたたいてしまう人も多いのではないでしょうか。本当に、話が通じないというか「君、ポスト読んだ?」みたいな人がたくさんいますもんね。
そんな感じですから、「人は見たいものしか見ない」は、そもそも妥当なのかどうか気になってしまいますよね?結論から言うと、「人は見たいものしか見ない」は基本的に妥当です。人が見たいものしか見ない理由は、以下の通りです。
人が見たいものしか見ない2つの理由
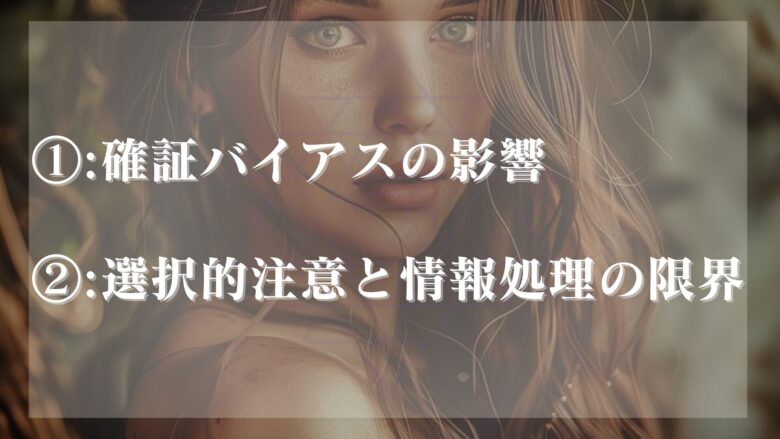
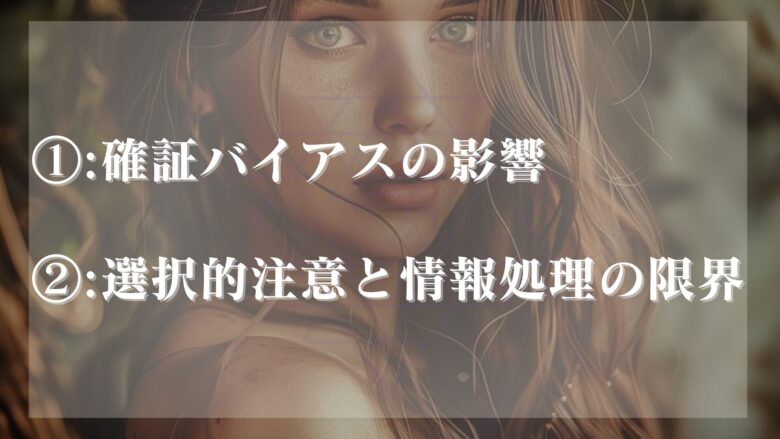



特に、確証バイアスによるところが、大きいね。
「人は見たいものしか見ない」のは、人の認知の癖に由来するものであって、意識的に修正しない事にはなかなか避けられません。当然、現実の事象は複雑ですから、見たいものばかり見ていてはだまされたり失敗したり、、と散々な目にあってしまいます。そのため、努めて視野を広げるようするのが賢明でしょう。
見たいものしか見ない認識の癖に引きずられないためには、日々メンタルケアを徹底して精神状態を安定させるのが重要です。精神状態が安定すればこそ、冷静かつ客観的なものの見方が可能になります。とはいえ、自力で効果的なメンタルケア対策をきちんと行うのは、なかなか大変ですよね?
ですが、メンタルケアアプリのAwarefyを使えば、手軽に日々効果的なメンタルケア(マインドフルネス系も充実)ができるので、とても便利です。また、Awarefyは月額1,600円(税込)から利用でき、経済的負担が大変少ないのも魅力です。日々のメンタルケアをコスパよく行いたい方は、ぜひAwarefyをダウンロードしてみてくださいね!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\
「人は見たいものしか見ない」という言葉の起源





「人は見たいものしか見ない」って、誰が言い始めたん?



大元をたどると、独裁官のユリウス・カエサルやね。
結論から言うと、よくネットで自己啓発系・心理系発信者が拡散している「人は見たいものしか見ない」という言葉は、ローマ時代の独裁官ユリウス・カエサルの以下の言葉に起源を持っています。
Fere libenter homines id quod volunt credunt.(人々はたいてい、自分が望むことを進んで信じる)
この言葉は、歴史家ガイウス・スエトニウス・トランクィッルス(Suetonius)の『皇帝伝』や、歴史家の塩野七生氏の『ローマ人の物語』で紹介され、日本で広く知られるようになりました。
塩野氏の作品では、カエサルが人間の認知傾向を鋭く観察した一言として引用されており、現代の心理学に通じる洞察として注目されています。



やっぱり、昔から人間の認知傾向とか心理って変わらんのね。
また、少々余談ですが、カエサルの言に似たニュアンスを持つ言葉として、フランス生まれの作家アナイス・ニンの以下の言葉が取り上げられることもままありますね。
We don’t see things as they are, we see them as we are(私たちは物事をあるがままに見るのではなく、自分自身のあり方のままに見るのだ)
参考:goodreads
どちらの言葉も、人間心理の本質を鋭くえぐる名言といえます。
人が見たいものしか見ない2つの理由





人が見たいものしか見ない理由って、なんなん?



それは、以下の認知特性等によるせいなんやで。
つぎは、人が見たいものしか見ない理由について、具体的に見ていきたいと思います。人が見たいものしか見ない理由は、以下の通りです。
人が見たいものしか見ない理由
- 理由①:確証バイアスの影響
- 理由②:選択的注意と情報処理の限界



それぞれ、詳しく見ていこう!
理由①:確証バイアスの影響
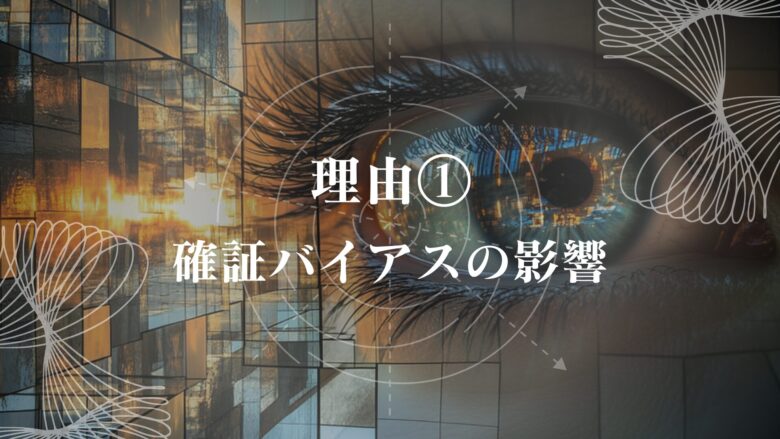
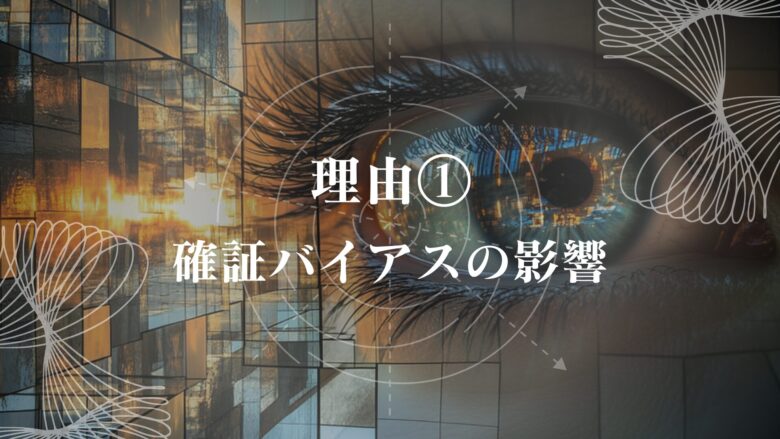
人が見たいものしか見ない理由の1つ目は、「確証バイアスの影響」です。
確証バイアスとは、人が自分の既存の信念や仮説を支持する情報に過度に注目する認知傾向のこと。実際、以下の研究によると、人は自分の考えを裏付ける証拠を積極的に探し、反証する情報には無関心になる傾向があることが確認されています。
参考:Confirmation, disconfirmation, and information in hypothesis testing.
たとえば、政治的信念が強い人は、自分と同じ意見のニュースを信頼して、異なる意見を「偏っている」と感じる傾向にあります。これは脳が認知的不協和(矛盾する情報の不快感)を避けるためで、認知的不協和理論でも説明されていますね。
現代では、SNSのアルゴリズムがユーザーの好みに合った内容を優先的に表示するため、確証バイアスが増幅しされるリスクが非常に高いです。人間の認知特性をテックのロジーが助長させているいい例といえるでしょう。



確かに、言われてみれば本当そうやね。
なお、確証バイアスに陥らないようにするためには、「自分は今、見たい情報に偏っているかもしれない」と気づくようにしたり、日記やメモに「自分はどんな前提を持っているか」を書き出すのが効果的です。また、ニュースやSNSで、自分と反対の立場の情報源を意識的にフォローするのもいいでしょう。
ちなみに、いずれにしても、「自分のものの見方は偏っていないか?」と気づくためには、メタ認知を鍛える必要があります。マインドフルネス瞑想を習慣化すれば、このメタ認知が効果的に鍛えられるので、メタ認知を強化したい方は以下の記事から実践方法を見てみて下さいね。
人が見たいものしか見ない理由には確証バイアスの影響がある
理由②:選択的注意と情報処理の限界
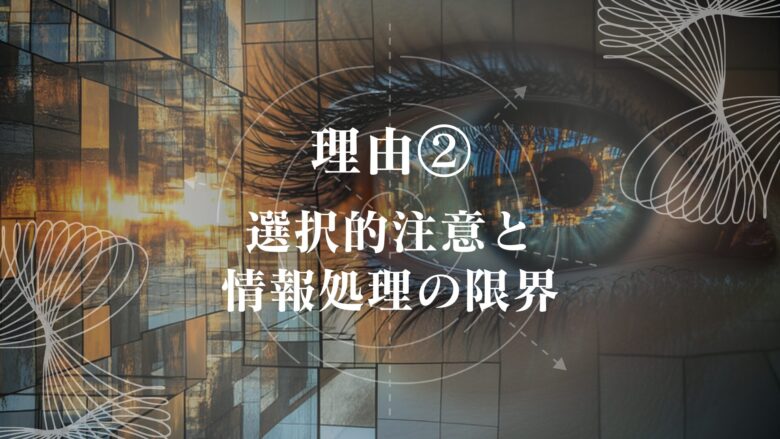
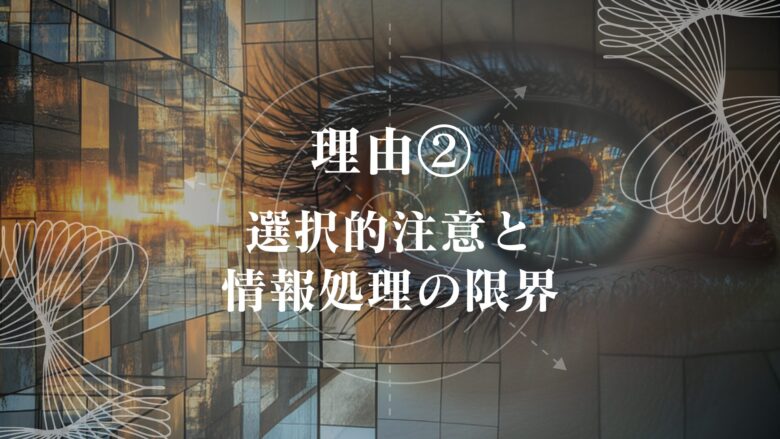
人が見たいものしか見ない理由の2つ目は、「選択的注意と情報処理の限界」です。
人間の脳は、膨大な情報をすべて処理する能力がありません。そのため、選択的注意が働き、関心のある情報だけに焦点を当てます。実際、1999年の「見えないゴリラ」実験では、バスケットボールの動画を見ている被験者が、ゴリラが画面を横切るのに気づかない現象が示されました。
参考:Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events
これは、脳が「見たいもの」に優先的にリソースを割り当て、関連性の低い情報を無視する証拠といえます。この選択的注意は、個人の価値観や感情、環境によって影響を受けるとされており、たとえば、ストレス下ではネガティブな情報に過敏になり、ポジティブな情報を見落としがちになる傾向にありますね。



んー、選択的注意かあ、、、なんか対策はあるんか?
なお、この選択的注意への対策としては、「自分の意見」と「相手の意見」を紙に書いて、両方に根拠を探す練習を繰り返すのが有効です。これを実践することによって、選択的注意が修正されやすくなります。
人が見たいものしか見ない理由には選択的注意と情報処理の限界がある
「人は見たいものしか見ない」がよく分かる3つの事例





もう少し具体的事例を、確認したいねえ。



んじゃ、もう少し具体的に事例を見ていこうかの。
「人が見たいものしか見ない」のは、前述のとおり「確証バイアスの影響」と「選択的注意と情報処理の限界」が理由です。ただ、まだこの2つと「人が見たいものしか見ない」こととのつながりが具体的にイメージできない方もいると思います。
そこで、ここではこの2つをもう少し具体的な事例ベースで、考えていきたいと思います。
「人は見たいものしか見ない」がよく分かる事例は、以下の通りです。
「人は見たいものしか見ない」がよく分かる3つの事例
- 事例①:政治的議論での偏見
- 事例②:恋愛や人間関係での誤解
- 事例③:広告やマーケティングの影響



それぞれ、詳しく見ていこう!
事例①:政治的議論での偏見


「人は見たいものしか見ない」がよく分かる事例の1つ目は、「政治的議論での偏見」です。
先ほど少しふれたように、政治的な話題では、自分の支持する政党やイデオロギーに合った情報だけを受け入れる傾向が顕著です。たとえば、2020年の米国大統領選挙では、支持者がある候補のスキャンダル報道を「フェイクニュース」と一蹴して、自分の信念を支持する情報のみを拡散した例が多発しました。



ああ、なんかあったかも。
またXの投稿でも、特定の政治的話題(例: ワクチンや気候変動)で、反対意見を無視するコメントが頻繁に見られます。
そして、以下Lord et al.(1979)の研究では、死刑制度に関する議論で、賛成派も反対派も自分の立場を支持するデータのみを重視したことが示されていますね。人間のものの見方が以下に偏りやすいかが、よく示されている事例といえるでしょう。
事例②:恋愛や人間関係での誤解


「人は見たいものしか見ない」がよく分かる事例の2つ目は、「政治的議論での偏見」です。
恋愛では、パートナーの良い面だけを見て、問題行動を無視するケースがよく発生します。たとえば、浮気の兆候を「ただの友達付き合い」と解釈する人は、ポジティブな関係性を維持したい願望から、都合の良い情報に注目しているといえるでしょう。



恋は盲目とかそういうやつか。まあ3年も持たない気はするけど。
実際、人は自分の自己像や関係性に対する信念を維持するために、矛盾する情報を無視する傾向があるとされていますね。
事例③:広告やマーケティングの影響


「人は見たいものしか見ない」がよく分かる事例の3つ目は、「広告やマーケティングの影響」です。
企業は確証バイアスを利用して消費者の購買意欲を高めます。たとえば、健康食品の広告では「このサプリで健康に!」と強調し、科学的根拠の薄い主張でも、消費者が「健康になりたい」という願望に合致すれば信じやすくなってしまうものです。



あーー、わかりすぎてやばい、、、。
ちなみに、このような現象は一貫性の原理によって、消費者が一度信じたブランドに固執する傾向で説明されていたりもします。
私達は、知らず知らずに広告戦略にまんまとハマって、いらないものをたくさん買わされているのかもしれませんね、、、。
人は見たいものしか見ないのか気になる時によくある疑問





まだ気になることが。あるんよなあ、、。



うむ、最後に疑問に回答していこうぞ!
最後に、人は見たいものしか見ないのか気になる時によくある疑問について、回答していきたいと思います。
疑問①:この傾向は生まれつきのもの?
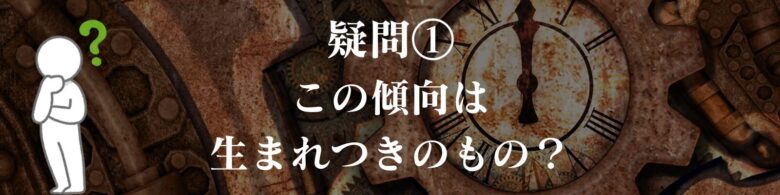
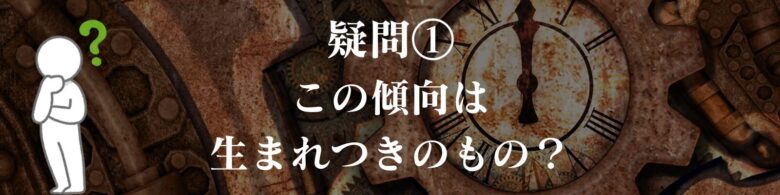
「見たいものしか見ない」という傾向は、基本的に生まれつきの認知メカニズムです。ちなみに、進化心理学では、生存のために迅速な情報処理が必要だったため、選択的注意が進化したとされます。
疑問②:確証バイアスにはポジティブな影響もある?
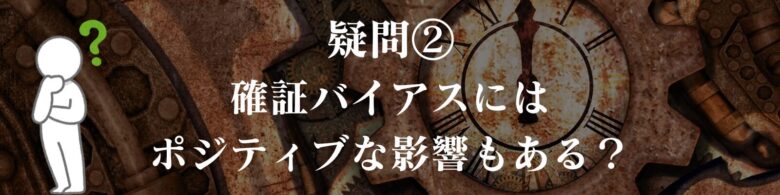
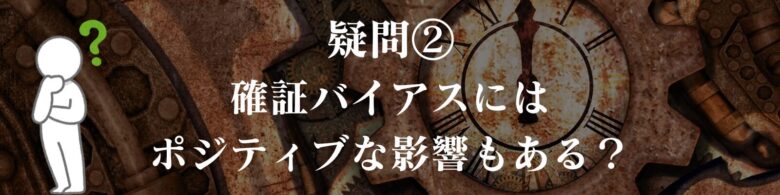
確証バイアスに、はポジティブな影響もあります。たとえば、楽観的な信念を強化することで、ストレス軽減やモチベーション向上が期待できますね。
実際、以下の研究では、適度な「ポジティブな錯覚」がメンタルヘルスに有益だとされています。
参考:Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health.
もっとも、過度なバイアスは現実逃避につながるリスクがあるので、その点は要注意ですね。
人は見たいものしか見ないはガチ!確証バイアスに惑わされないように気を付けよう!


「人は見たいものしか見ない」は、人の認知の癖でありその通りです。そのため、意識的に修正しない限り、人は自分の見たいものばかり見がちになってしまいます。しかし、これでは判断を間違ってひどい目にあうことも多々あるでしょう。
こうした認知の癖を修正するためには、精神状態を安定させて冷静かつ客観的にものを見れる状態を作るのが最善です。特に、マインドフルネス系統のメンタルケア対策を重点的に行うようにすると、意識の使い方がうまくなり、見たいものばかり見る状態に陥っている時に自然と気が付けるようになるのでお勧めですね。



安定した精神状態があってこそ、視野は広がるねん!
ただ、自分だけで日々メンタルケアを効率的かつ適切に行うのは、中々難しいですよね?メンタルケアを手軽かつ効果的に行いたい人には、認知行動療法ベースのメンタルケアアプリAwarefyがおすすめです。Awarefyなら手軽に効果的なメンタルケアができます。
また、Awarefyを使えば月額1,600円(税込)で手軽に効果的なメンタルケア(マインドフルネスを含む)が始められるので、経済面も安心です。さあ、メンタルケアアプリのAwarefyを使って、人間関係と人生を豊かにしていくための下地を整えていきましょう!
\月額1,600円(税込)/
\AIが認知行動療法でメンタルケアを徹底サポート!/
/24時間いつでも悩み相談可能!\!\